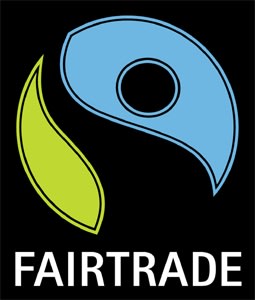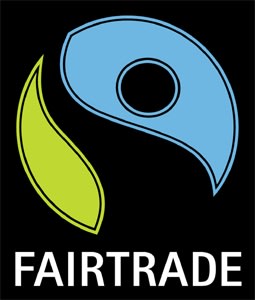 新聞の書評欄で紹介されていたので読んでみました。
新聞の書評欄で紹介されていたので読んでみました。
従来のジャンルでは「南北問題」にカテゴライズされる問題意識にもとづく内容を、企業の社会的責任(CSR:corporate social responsibility)や地球環境環境・貧困等の観点で論じています。
“フェアトレード”等、昨今流行の認証ラベルの実態も明らかにしつつ、世界各地の人々の生活環境・労働環境等の現実を掘り下げている姿勢が新鮮です。
いくつかのレポートが紹介されていますが、たとえば、大手レストランチェーン「レッド・ロブスター」を所有しているダーデン社の場合。
同社の上級副社長は「当社の製品規格には、潜水漁によるロブスターは購入しないと明記している」とコメントしています。
(p51より引用) 大企業の言い分はこうだ。「われわれは潜水によるロブスター漁が悪いことだと知っている。だからその手法で獲られたとわかっているロブスターは買わない」。そして、「潜水で獲られたと分かっているロブスターを買っていないわけだから、何も問題などあるはずがない」
これは立証するのが難しい主張だ。・・・いったん梱包され出荷されてしまえば、そのロブスターがどういう方法で獲られたのかを知る術などないのだ。
本書のタイトルにもなっている“フェアトレード”については、その推進母体である「フェアトレード財団」の活動の実態にも踏み込んでいます。
フェアトレード認証の仕組みとしては、認証を受けた製造業者や流通業者は、フェアトレード財団に手数料(認証料・登録料)を支払うことになっています。
(p78より引用) 卸売業者に課される手数料は、フェアトレード財団が毎年上げている収入の大部分を占める。・・・その半分が認証プロセスの運営・管理にかかる管理費に消えていく。
では、残りの半額は農家の手元に届くのか?答えはノーだ。残りは、フェアトレードのブランドを宣伝するために使われる。
農家等は「フェアトレード価格」での取引という形でメリットを享受する仕掛けですが、現実的には「実態の取引価格」の方が「フェアトレード価格」よりも高いケースが数多く見られるというのです。
また、本来は生産者のもとに還元されるべき「社会的割増金(プレミアム)」についても、財団との対応の窓口たる協同組合もしくはその長が中間搾取しているケースもあるとのこと。
これでは「フェアトレード」の仕組みが「開発途上国の生産者や労働者の生活向上」に貢献しているとは到底言えません。「フェアトレード」のメリットは、参加企業の「CSRへの取り組みのPR」という形で機能しているのが実態なのです。
(p121より引用) 多くの企業がいまだに、CSRから長期的な価値を生み出すよりは短期的に評判を高めるほうに関心をもっている。本当はもっと戦略的に考える必要があるのに、その考えを捨てきれずにいるのだ。
本書では、こういった「CSR」の切り口からのルポルタージュ以外に、従来からの「南北問題」の延長線上にある「貧困」の問題も取り上げられています。
たとえば、周辺国との戦争、さらに悲惨な内戦を経験したコンゴ民主共和国。
当地のスズ石採掘の現場です。国連は紛争地域であるコンゴ産鉱石の取引を禁止しているのですが、実態は別です。
最近の国連報告書で紛争鉱物貿易の中心的人物として名指しされているパンジュ氏はこう語っています。
(p189より引用) 「欧米の倫理はいまや、第三世界の倫理とは両立しないだろう。・・・買い手がやって来て、鉱山で子どもたちを働かせてはいけないと言う。私は言ってやるんだ。『たしかに、それは欧米なら結構だろう。だがここコンゴで、子どもたちに他に何をさせると言うんだ?』ってな。ここには、欧米みたいに学校があるわけじゃない。外を見てみろ。そこらじゅうで子どもたちが働いている。働かなかったら、どうやって食い物を買う金を稼ぐんだ?だれが食わせてくれるんだ?あんたじゃないだろう」
スズ鉱物の利用者である電気機器産業の各社が国際錫研究所に申し入れをして作成された「適正評価計画」もこんな内容とのこと。
(p202より引用) 計画文書に書かれているのは軟弱で骨抜きな中身のない言葉ばかりで、問題を「認識」し、変化を「奨励」して現状に「懸念」を示してはいるが、目に見える変化をもたらせるような責任感と透明性を備えた計画はどこにも書かれていない。
倫理的消費主義の状況の変化により、欧米企業が紛争鉱物貿易の抑制に動き始めていても、中国のような欧米の倫理基準を気にしない新たな買い手がその貿易を引き継いでいるのが現状です。
コンゴのスズ以外、タンザニアの紅茶、コートジボアールの綿などの生産・流通の面においても、大手企業による投資・経営戦略で描かれているスキームと最下層の生産実態との間には大きなギャップが存在しています。
次はアフリカの時代との声も時折聞かれますが、この実態が発展と貧困の共存という二重構造の下部に隠され続ける状況は、決して許されるものではありません。
しかしながら、その解決への道程は長い・・・です。

 池井戸氏の作品は「下町ロケット」に続いて2冊目です。
池井戸氏の作品は「下町ロケット」に続いて2冊目です。