会社の大先輩がSNSで紹介されていて気になった本です。
いつもの図書館に所蔵されていたので、さっそく借りて読んでみました。最新の遺伝子研究の成果から人類誕生以降の足跡を顕かにしようと試みた著作です。
さっそく数多くの私の興味を惹いたところから、いくつか覚えに書き留めておきましょう。
まずは、「ホモ・サピエンス」の起源に関する最新の研究成果です。
(p59より引用) ホモ・サピエンスの誕生については、20世紀の終わりまで支配的だった多地域進化説が、21世紀になって、「アフリカで20万年前に誕生したホモ・サピエンスが、六万年ほど前に出アフリカを成し遂げて、旧大陸にいたホモ・サピエンス以外の人類を駆逐しながら世界に広がった」とする新人のアフリカ起源説に取って代わられました。また、2010年以降には、ホモ・サピエンスが世界展開の過程で他の人類の遺伝子を取り込んだことが明らかになってい ます。
このあたり、化石の形状や年代推定だけでなく、DNAやアミノ酸配列の分析に基づく研究の結果であり、アウストラロピテクス、ネアンデルタール人、ジャワ原人、北京原人、クロマニョン人ぐらいしか習わなかった私の学生時代の知見とは激変してしまっていますね。
こういった大古の人類の探究以外にも、もっと時代が下り、私が「世界史」の授業で習い、より具体的活動が思い描かれるようなトピックにも「遺伝子研究」による新たな発見が見られます。
(p168より引用) 鉄器時代に当たる紀元前八世紀から前二世紀にかけてこの地域を支配した遊牧騎馬民族スキタイは、文化的には共通する要素を持つものの、地域によって遺伝的な構成が異なっていたことがわかっています。スキタイとしてまとめられるグループは、実際には遺伝的に異なる集団の連合体だったのです。
その後ユーラシアステップに登場する「匈奴」や「フン族」も、遺伝的に異なる地域集団の連合体だったとのことです。
同様に、日本列島における「縄文人」と「弥生人」の分布に関する諸説の当否についても「遺伝子研究」の成果が活かされています。
たとえば、まず日本列島に縄文人が拡散し、その後、中央部に弥生人が侵入したため北海道と琉球に縄文人的集団が残ったという「二重構造モデル」も最新の遺伝子研究によってその単純な立論は否定されています。
(p228より引用) 二重構造モデルは、大陸からの稲作文化を受け入れた中央と、それが遅れた周辺で集団の形質に違いが生じたと考えていますが、この発想からは周辺集団と他の地域の集団との交流の姿を捉えることができません。北海道の先住民集団の形成史は、日本列島集団の形成のシナリオに、複眼的な視点を導入する必要があることを教えてくれるのです。
そして、「遺伝子研究からみた人類集団」についての篠田さんのとても重要な指摘です。
(p257より引用) ゲノムデータから集団同士の違いを見ていく際には、同じ集団の中に見られる遺伝子の変異のほうが他の集団とのあいだの違いよりも大きい、ということも知っておく必要があります。
(p258より引用) 遺伝子によって規定されるさまざまな形質や能力は、同じ集団の中での変異が大きいのですから、集団同士をくらべて優劣をつけることには意味がありません。
さらには、こう続きます。
(p267より引用) こうした教科書的記述に欠けているのは、「世界中に展開したホモ・サピエンスは、遺伝的にはほとんど同一といってもいいほど均一な集団である」という視点や、「すべての文化は同じ起源から生まれたのであり、文明の姿の違いは、環境の違いや歴史的な経緯、そして人びと の選択の結果である」という認識です。
こういった科学的な基本認識のもとに「多様な社会」の理解がなされるべきなのでしょう。
本書を読むと、遺伝子分析によると「種」という区分は無意味であり、地域集団の差異は連続的な変化の一断面に過ぎないことが分かります。
さて、最後に、私が本書を読み通して最も印象に残ったくだり、「脳容量の変化と社会構造」というコラムの一節です。ちょっと長いのですが引用しましょう。
(p25より引用) ホモ・サピエンスの脳容積は、誕生してこのかた増加していませんから、その後の歴史は、基本的にはダンバー数程度の理解力しかないハードウェアを使ってなんとか編み上げられたといえます。複雑な社会を形成するために生み出されたのが、言語や文字、物語、宗教、歌や音楽といった文化要素だったのでしょう。これらは人びとが時間と空間を超えて概念や考えを共有する重要な手助けをしています。現在では、大規模な通信ネットワークによってさらに多くの人びとがつながりあい、大量のデータが行き来するたいへん高度な社会環境に私たちは置かれています。自分の脳が処理できるよりもはるかに多量のデータにさらされる状況で、バランスの取れた情報処理ができず、社会の混乱が生じてしまっていることも、至極当然なことといえるのではないでしょうか。
なるほどと首肯できる指摘ですね。
別の言い方をすると、世の中の変化において「人間の思考」が影響するウェイトが減少しているということ、さらに言えば、現代は「人間の知性の相対的劣化」が日増しに進んでいるということかもしれませんね。















![ザ・アウトロー[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51q9EhAC4dL._SL160_.jpg)

![サンダカン八番娼館 望郷[東宝DVD名作セレクション]](https://m.media-amazon.com/images/I/51EYvPr3BAL._SL160_.jpg)



![渚のシンドバッド [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51E3FZwhbIL._SL160_.jpg)


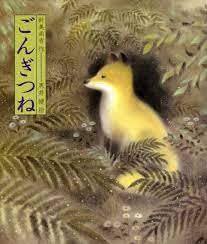


![東京湾炎上 [東宝DVD名作セレクション]](https://m.media-amazon.com/images/I/514vBFmGqwL._SL160_.jpg)

![クロスマネー [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WnKRd0adL._SL160_.jpg)



![あの頃映画 「闇の狩人」 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41MeRYQhppL._SL160_.jpg)

![ボルケーノ・パーク [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51VZR0nZPLL._SL160_.jpg)



![ブラッド・スローン [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51f17OM0liL._SL160_.jpg)







