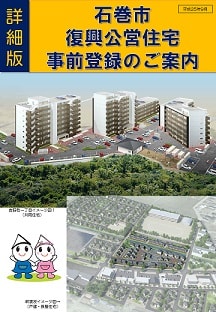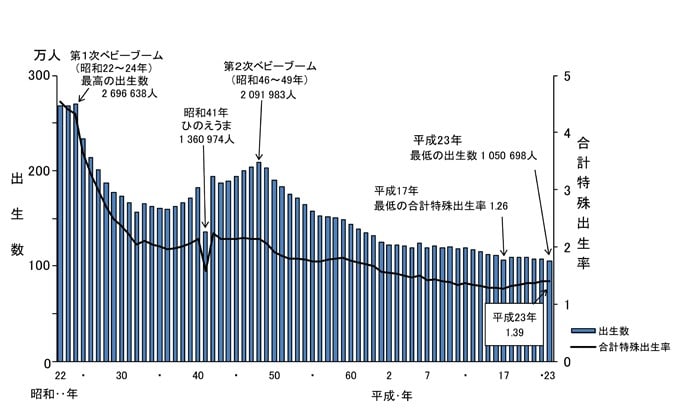「決して忘れてはいけない記憶」というのも正しくないでしょう。それは、まだ「過去のもの」になっていないからです。まだまだ、多くの被災者の方々にとっては“現在進行形”なのです。
本書では、未曾有の被害をもたらした東日本大震災の復興から取り残されている人々の今の姿や、被災者支援のために、今なお様々な分野で尽力している方々の活動、そしてそれらを通して明らかにされた課題の数々を紹介しています。
石巻市立病院開成仮診療所の長純一所長。
長所長の最大の危惧は「要介護認定率の急上昇」です。この要介護者へのケアは介護保険サービス利用のニーズの高まりにつながりますが、おそらくそれでカバーできない状況が容易に想像されます。そこを補うのが「家族」や「コミュニティ」の力なのですが、これが急速に崩壊しつつあるというのです。
(p27より引用) 被災地がまさにこれから直面することとして、「被災者の復興公営住宅(災害公営住宅)への転居が進む中で、仮設住宅で形成されたコミュニティが白紙に戻るとともに、社会的弱者が集中する。復興公営住宅に入居した段階で被災者とみなされなくなるため、行政からの支援も大幅に縮小していく」(長医師)というのだ。
被災現場に在るリアルな生活者の方々を助けるには、単に「住む所」を提供すれば済むというものではないということです。「復興公営住宅」の提供の“負の部分”にどう取り組むのか?行政は、しばしば「住処を提供したのだからいいだろう」と手を引いてしまうのです。
こういった制度や行政の手が届いていない被災者として「在宅被災者」の方々がいます。
(p73より引用) 今回の東日本大震災では、食料や支援物資が避難所に集中し、一部の自治体を除けば在宅被災者への支援がなきに等しかった・・・海外からの義援金を原資にした日本赤十字社の「家電六点セット」も仮設住宅(みなし仮設を含む)だけが対象で、住宅が全壊してすべての家財道具を失ったとしても、在宅被災者には何一つ届けられなかった。在宅被災者は津波をかぶった自宅に戻り、水に浸かった家財道具の運び出しに朝から晩まで追われ、その挙げ句に体を悪くした。
こういった在宅被災者の生活は今現在でもさほど改善されていない、宮城県南部を中止に活動しているボランティアグループ「チーム王冠」の伊藤健哉さんは語気を強めてこう語ります。
(p74より引用) 在宅被災者の多くは今も「不公平な扱いを受けた」と心の底で感じている。・・・伊藤さんによれば在宅被災者の実態がよくわからないのは、彼らが「サイレントマジョリティになっている」ことに原因があるという。「家が残った」というだけで恵まれていると言われた彼らは、「自分たちより、もっと大変な人がいる。その人たちを助けてあげてください」と言わざるをえなかった。
自分が苦境にある中で「ほかの人を助けてあげて」との話す人々の心情を慮ると、本当に心が痛みます。
こういった方々に手を差し伸べる主体こそ行政であるべきですが、実態は、被災者に寄り添うボランティアの活動に頼っているのです。
(p195より引用) 国による東日本大震災の復興予算の支出済み額は2013年度までに20兆円を突破している。・・・にもかかわらず、被災者には十分な資金が回っていない。被災者の生活再建に直接効果のある被災者生活再建支援金の支給額は3006億円、災害弔慰金は590億円にとどまる。これに対して、南海トラフ地震対策など東日本大震災と直接関係のない事業に使われている「全国防災対策」費は14年度までに1兆3674億円に達している。
もちろん、行政としても、全ての被災者の皆さんが満足できるような支援は、残念ながら極めて難しいことでしょう。せめて、少しでも多くの支援を、少しでも不公平感をなくす形で提供できればと思います。
まずは、不要不急の施策や便乗施策を排除する、これは是非とも実現させたいことですね。火事場泥棒的な姿勢は、本当に寂しく思います。可能な限り、限られた財源を「今、苦しんでいる人々」に届けるべきです。もちろん、将来のリスク低減も重要ですが、「今」を乗り越えられない人々には、そもそも「将来」は来ないのです。
もうひとつの「公平性」、これは、更に難しいですね。
まずは、納得できないような制度を何とか変更・廃止して、意味のある制度に再設計すること、ただそれでも、制度を運用する以上は、現実的にはどこかで「線引き」をせざるを得ない、これは避けられません。そこに僅かなりとも納得性の要素を残すことができれば・・・。それは、制度を運用する側、制度の恩恵を受ける(受けられない)側が、それぞれの立場を理解しあうこと、その上で、「申し訳ない」「仕方ない」と想い合うところまで至ることだと思います。
しかしながら、それでも結局、現実的は目の前の生活に困窮する被災者は「0」にはなりません。
この方々に対して何ができるのか・・・、ダメです、私の思考もそこ止まりです・・・。
 |
被災弱者 (岩波新書) |
| 岡田 広行 | |
| 岩波書店 |