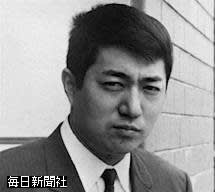いつも読書の参考にさせていただいている「ふとっちょパパ」さんが以前紹介されていたので読んでみました。
いつも読書の参考にさせていただいている「ふとっちょパパ」さんが以前紹介されていたので読んでみました。
「古典」の入門解説というよりも、現代日本語のルーツである「和漢混淆文」に至る日本語の歴史を、「古典」の文章を材料に説いたような内容です。
和漢混淆文は鎌倉時代に登場します。
(p67より引用) 重要なことは、「兼好法師の時代になって、やっと現代人でも読めるような文章が登場する」です。だから、それ以前の古典-『源氏物語』や『枕草子』が読めなくったって、読んでも意味がわからなくったって、べつに不思議でもなんでもないんです。
平安時代は「和歌」の時代でした。
「和歌」は実用的なコミュニケーションツールだったのです。
(p79より引用) 平安時代というのは、まだ「普通の日本語の文章」がなかった時代なんです。日本人が普通に「日本語の文章」を書いて、それが十分に「自分の感情」を伝えられるようになった時、和歌というものは「生活必需品」から「教養」へと転落するのです。
平安時代を代表する著作は、やはり「源氏物語」と「枕草子」です。
それらは「ひらがな」で書かれていました。ひらがなだけで書かれた「和文体」は句読点もなく、主語述語の関係もあいまいです。まさに「話し言葉」をそのまま「ひらがなに起こした」ものです。
著者は、源氏物語の分かりにくさの原因について、「複雑な心理描写の内容」を「かんたんな(ひらがなの)文章」で書こうとしためだと説明しています。
こういった「話し言葉のひらがな」と「書き言葉の漢字」とが程よくミックスされることによって、分りやすい日本語表記法としての「和漢混淆文」が生れました。
(p217より引用) 「和漢混淆文」は、日本人が日本人のために生み出した、最も合理的でわかりやすい文章の形です。・・・「自分たちは、公式文書を漢文で書く。でも自分たちは、ひらがなで書いた方がいいような日本語をしゃべる」という矛盾があったから、「漢文」はどんどんどんどん「漢字+ひらがな」の「今の日本語」に近づいたんです。漢文という、「外国語」でしかない書き言葉を「日本語」に変えたのは、「話し言葉」なんです。
本書には、古典に対して興味がわくようないくつものネタが仕込まれています。
たとえば、「万葉ぶり」をキーワードにした2人の人物、「武の上皇」と「文の将軍」の紹介。
その2人とは、新古今和歌集を編んだ文化人でありつつも武士に武力で対抗しようとした後鳥羽上皇と、武士の棟梁でありながら都にあこがれ、自らの歌を金槐和歌集にまとめた源実朝です。
著者によると、源実朝は「おたく青年の元祖」だというのです。
また、「古典の訳」についても、著者ならではのセンスが溢れています。
古文の授業では必ず取り上げられる代表的な単語「あわれ」と「をかし」の訳し方です。
「あわれ」は「ジーンとくること」、「をかし」は「すてき」。
さらに、有名な「徒然草」の冒頭も、橋本流ではこうなります。
(p192より引用) 《つれづれなるままに日くらし硯に向かひて、心にうつりゆくよしなし事をそこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ》-この文章の訳は、「退屈でしょうがないから、一日中硯に向かって、心に浮かんでくるどうでもいいことをタラタラと書きつけていると、へんてこりんな感じがホントにアブナイんだよなァ」になります。一体なんなんでしょう?
最後に、著者が説く「古典」の楽しみです。
(p219より引用) 古典が教えてくれることで一番重要なことは、「え、昔っから人間てそうだったの?」という、「人間に関する事実」です。・・・古典は、そういう「とんでもない現代人」でいっぱいなんです。
 |
これで古典がよくわかる (ちくま文庫) 価格:¥ 714(税込) 発売日:2001-12 |
↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!



![]()
TREviewブログランキング