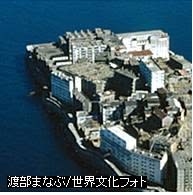本書で紹介されている老舗の経営者の方は、どこか常人離れ?しているところがあります。
本書で紹介されている老舗の経営者の方は、どこか常人離れ?しているところがあります。
常人離れという言い方は正しくないかもしれません。矮小化された小賢しい才覚ではなく、大局観をもった経営哲学をもっているのです。
たとえば、醗酵技術による「日本型バイオテクノロジー」の先駆者勇心酒造の徳山さんの「水平思考」です。
(p90より引用) ・・・徳山さんは、醸造業界低迷の大きな原因を「垂直思考の弊害」と考えた。
「『お酒はおいしい』とか『お米をもっと食べましょう』といったPRの仕方自体、垂直思考に凝り固まっている証拠なんですね。お米の場合、清酒や味噌、醤油、酢、みりん、あるいは焼酎、甘酒といった非常に優れた醸造・醗酵・抽出の技術があるんですけれども、明治以降、新しい用途開発がまったくと言っていいほどなされていなかった。・・・近代科学が行き詰っているいまだからこそ、米作りのような農業と醸造・醗酵の技術とをもう一度リンクさせて、付加価値の高いものを作ろうと、お米の研究に取りかかったわけです」
これを徳山さんは、「垂直思考」から「水平思考」への切り換えと宣言した。
また、徳山さんの「西洋と東洋の方法論の違い」についても、一家言お持ちです。
(p98より引用) 「西洋のヒューマニズムを『人道主義』と訳してきたのは、とんでもない誤訳やと思うんです。ある学者が言うてましたが、あれは『人間中心主義』と訳すべきなんです。つまり、何事も人間を中心に『生きてゆく』という発想。・・・一方、東洋には自然に『生かされている』という発想があります。・・・方法論でも、西洋が『単一思考』『細分化』であるのに対して、東洋は『相対合一論』『総合化』や、と。『相対合一論』というのは、相反することを合一しながら真実ひとつを目指してゆくということことです。・・・」
セラリカNODAの野田さんは、面白い切り口から論を進めます。
(p112より引用) 「脊椎動物の最終形態が人間なら、無脊椎動物の最終形態は昆虫なんです」
という話から始まり、
(p112より引用) 「人間は地球の王様みたいになりましたが、昆虫のほうはおよそ百八十万種もの多様な生物種として存在している。それなのに、人間が“益虫”とみなして利用してきたのは、ミツバチとカイコくらいで、あとのほとんどは“害虫”と邪魔者扱いしてきました。・・・こういった人間からの価値付けだけで、邪魔者を排除する発想が、開発のために自然を破壊する行為にもつながっているんですね」
と、「人間中心の価値付け」が環境問題の根源にあることを指摘します。
さらに、邪魔者を排除する「殺す発想」から「生かす発想」への転換を求めるのです。
(p113より引用) 最近の日本人は、農薬のかかっていない有機農産物をもてはやす一方で、夜中にゴキブリが一匹でも出てくると、大騒ぎをして殺虫剤で殺そうとする。農薬イコール殺虫剤なのだから、こんな矛盾した話はないと野田さんは苦笑したが、すぐ真顔になった。
「こういう感性を不思議に思わないところに、現代を生きるわれわれの問題の根底があると思います。・・・いままでの『殺す発想』から『生かす発想』に転換する必要があると思うんですね」
今に生き続け、独自の地位を築いている老舗企業は、やはりどこかひとつ「心棒」が通っています。
そういう軸がしっかりしていると、いつか世の中がついてくることもあるのです。
銅の精錬から現在では廃物処理という環境事業に携わっているDOWAの渡辺さんの「何が幸い」という話です。
(p78より引用) 「いや、まったく何が幸いするかわからないですよねえ。ここ、高度経済成長の時代には、全然マッチしていなかった工場なんですよ。・・・それが二十一世紀になったら、産業社会のほうが切り換わって、リサイクル社会ということになった。そうしたら、時代に全然マッチしていなかった工場が、一番役立つ工場になったということなんです。世の中での存在理由が出てきたんです。・・・」
 |
千年、働いてきました―老舗企業大国ニッポン (角川oneテーマ21) 価格:¥ 740(税込) 発売日:2006-11 |