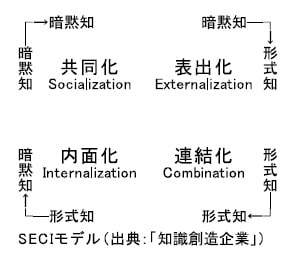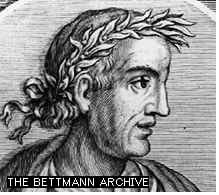本書の前半は、野中氏の知識創造理論のアウトラインが説明されていますが、後半には、知識創造を実現しているいくつかの企業のケーススタディが紹介されています。
本書の前半は、野中氏の知識創造理論のアウトラインが説明されていますが、後半には、知識創造を実現しているいくつかの企業のケーススタディが紹介されています。
それらの中から私の興味を惹いたものをご紹介します。
まずは、「第8章 対話と実践による事業展開」の中から、「良品計画」の例です。
「MUJI」「無印良品」のブランドで有名は「良品計画」では、その商品開発に顧客参画を活用していることはよく知られていますが、そのほかにも「取引先の知」を利用する仕掛けを有しています。商品企画担当者が「知の綜合」に関わるのです。
(p317より引用) メーカーは特定の専門分野に強いが、自分の分野以外のさまざまな技術との組合せによる商品化や市場性への理解という面が弱い。メーカー単独の商品化発想では限界があり、せっかくの技術や製品を広く応用できないままで抱えている場合もある。そこで、マーケットの知識を持つ良品計画がコーディネートし、複数のメーカーの技術を組み合わせる、マーケット情報と結びつけて共同で応用の方法を考える、といった方法で新商品開発へつなげていくのである。
外部からの刺激を取り入れるプロセスを組み込むというのは、組織活性化の王道です。が、これがなかなか「言うは易し、行うは難し」です。内部のコミュニケーションの円滑化・活性化すら思ったようには進みません。
また、「第9章 リーダーシップ」で採り上げられたのが「三井物産」。
総合商社の雄ですが、業績優先主義に走るあまり2000年代初、コンプライアンスに反する事件を惹起させました。その反省からスタートした企業再生の道程が説明されています。その中でのシンボリックな価値基準が、「良い仕事」という言葉でした。
(p335より引用) お客様の期待に応えているか?
新しい価値を創造しているか?
正当なプロセスを踏んだ仕事か?
社会にとって意味のある仕事か?
シンプルですが大事な視点ですね。
そしてもうひとつ、三井物産の「成果主義」の弊害を簡潔に言い表した言葉。
(p333より引用) 「最大のデメリットは、人と人とのつながりを大事にする社内風土から、人と人とが競争する風土に変わったこと。それにより商社が持つべき『人と人とのつながりに基づく総合力』を発揮できなくなっていった」
組織全体で知識を共有しようという風土がなくなり、知識創造のスパイラルが停止してしまったというのです。
いままでも成果主義については様々な評価がなされていますが、この「人的関係性の崩壊」という指摘はとても重いものがあります。
組織としてのシナジーの根本は、多種多様な人の知恵の化学反応による新たな知識創造にあることを踏まえると、こういった弊害の発生は企業にとって致命的です。成果主義を全否定するものではありませんが、「成果の把握単位」「成果への貢献因」に「他者(チーム)」という要素をうまく入れないと、「利己的成果至上主義」に陥ってしまうということです。
さて最後に、本書のテーマからは少々外れますが、なるほどと思ったグラフィックデザイナー故田中一光氏の言葉を書き留めておきます。
(p328より引用) 日本の精神文化を背景にした美意識。故田中一光さんは、簡素が豪華に引け目を感じることなく、簡素に秘めた知性や感性が誇りに思える価値体系を日本は持っており、世界に発信すべきだと言っていました。
侘び寂び・禅の世界についても、もっと勉強しなくてはなりません。
 |
流れを経営する ―持続的イノベーション企業の動態理論 価格:¥ 3,360(税込) 発売日:2010-06-25 |
↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!




![]()
TREviewブログランキング