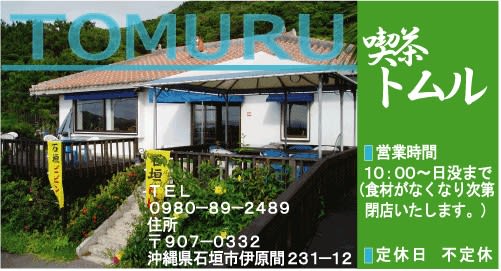紳助さんが本書で紹介している自らの「商売の秘訣」は、いわゆるマーケティングの教科書的なセオリーから見たとき、どう評価できるでしょう。
紳助さんが本書で紹介している自らの「商売の秘訣」は、いわゆるマーケティングの教科書的なセオリーから見たとき、どう評価できるでしょう。
紳助さんならではの語り口で語られていますが、その内容は、結構オーソドックスなものです。
それらの中で、私の関心を惹いたいくつかのフレーズをご紹介します。
まずは、「紳助さん流の会員制」の着眼についてです。
(p52より引用) 僕は、お客さんにたくさん入ってほしいからこそ、厳格な会員制にして敷居を高くした。
なぜなら、バーというものは、お客さんが作るものだからだ。
どんなに店の内装に凝って、優秀なバーテンダーを置いて、いい酒を揃えたって、1人でも大声で騒ぐお客さんがいたらすべては台無しになる。・・・
賑やかなのに、品がいい。誰もが心からくつろいで、サラリーマンが1日のストレスを発散できるバー。しかも毎日行っても、財布の負担にならないくらい安い。
どうしたらそういうバーを作れるか、考えた結果が会員制だった。
ここでのコンセプトは「優良顧客の囲い込み戦略」の一つのヒントになります。
この「囲い込み」をさらに堅固なものにするために、差異化の要素を加えます。
(p54より引用) もちろんそうはいっても、会員制なんて面倒なシステムにするからには、それでもお客さんがウチのバーに来たいという付加価値がなければいけない。
その付加価値がフォークソングだ。
私も年代的には近いので、このあたりの着眼には、結構シンパシーを感じます。
その他、思いつきから実際の起業にもっていくまでの、思いのほか?堅実な考え方について。
(p85より引用) 単なる思いつきでしかないものを、実現可能なアイデアに成長させるには、しっかりした情報が必要だ。
300円でとびきり美味いラーメンを食べさせる店を見つけたら、その店がどうして300円でやっていけるのかを正確に分析すれば、それがアイデアにつながる。
最後に、お客様が払う「値段」に、その「満足感」を収斂させる考え方について。
これば、関西芸人の紳助さんらしいストレートなコメントとも言えますが、おそらく「商売における真実の瞬間」の本質的な姿かもしれません。
(p132より引用) 客というものは、いつも無意識のうちに、自分の感じた満足感と値段とが見合っているかどうか判断しているのだ。・・・
客は料理だけを食べているわけじゃない。店の人の気持ちも一緒に食べているのだ。
そしてどんなに頑張って美味しい料理を出そうとも、最後の勘定で納得させられなければ、すべては台無しになる。料理を売るのが料理屋の商売である以上、値段は店の良心そのものだからだ。
お店が、「値段」で表わしているものが何なのか、「高い値段」とはお客にとって何なのか・・・
(p136より引用) 金を持っているやつほど偉く感じるというのと同じで、高い料理を出している料理人ほど偉いという錯覚がここにもある。
それは料理屋に限らず、どんな商売でも同じだ。
そして、商売人のそういう考え違いを、客は冷ややかな目で見ている。
おそらく、ほとんどのお客はそうでしょう。
しかしながら、「高い値段を払った」「高い値段の店に行った」ということ自体に何がしかの「価値」を感じているお客が存在していることも、また現実ではあります。
 |
ご飯を大盛りにするオバチャンの店は必ず繁盛する―絶対に失敗しないビジネス経営哲学 (幻冬舎新書 し 4-1) 価格:¥ 735(税込) 発売日:2007-05 |