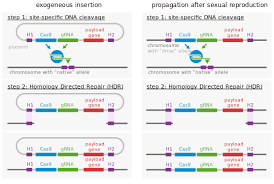“禅”について少しでも見識を深めたいと思い、だいぶ前に岩波文庫の「臨済録 (入矢義高)」を読んだことがあるのですが、ほとんど理解できませんでした。
ということもあって本書を手に取ってみたのですが、結果は・・・、見事に“返り討ち” にあった気分です。やはり駄目でした。
宗教という捉え方ではなく「仏教哲学」として理解しようとすると、やはり「心」ではなく「頭」で受け取ってしまいます。そうすると、如実に、基礎知識や思考能力の欠如が顕かになってしまいますね。臨済師(有馬師)が言わんとすることが、全く頭の中で「論理的」に整理できないのです。
かといって、教えの“本質”をザクっと捉えられるかというと、それこそキャパシティオーバーで・・・、というか、どこから近づけばいいのかすら「???」という情けない様なのです。
まあ、また懲りずに、少し間をおいてチャレンジしてみましょう。