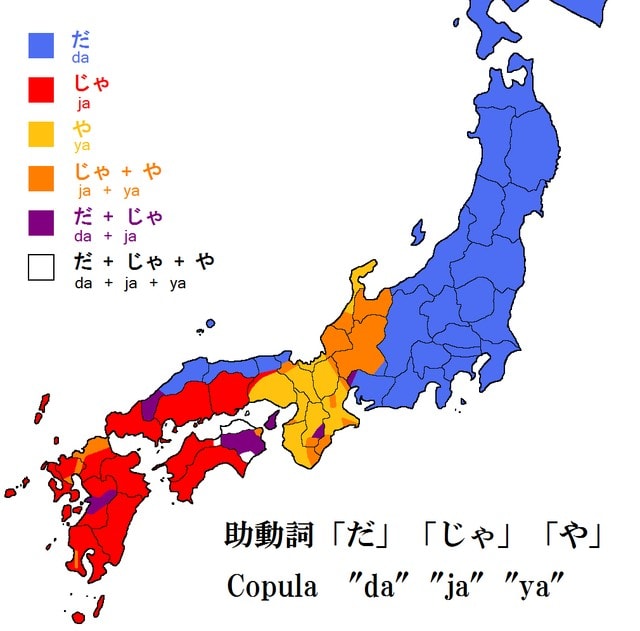蔵本由紀氏の著作は2冊目です。
先に同じ集英社新書から発刊された「非線形科学」という本も読んでみたのですが、これらの本で解説されている「同期現象」は、私が興味をもっているテーマのひとつです。
マングローブの木にとまっている何万匹ものホタルが同じ周期で明滅している映像はかなり有名ですが、そういったマクロリズムも、多くの場合、無数のミクロリズムが同期したものだという考え方があります。このミクロリズムの最小単位は「細胞」です。
(p120より引用) 心拍ほど身近なリズムはありません。・・・いのちの中心にあるこのリズムは、細胞集団の同期がもたらすマクロリズムです。
こういった細胞レベルでリズムを生じさせる仕組みには3種類あります。
第一は、細胞膜を通して各種のイオンが出入りすることによる「膜電位の振動」、第二は、特定の蛋白質により遺伝子の発現が抑制されたり促進されたりする「遺伝子発現のリズム」、そして第三は、細胞内で起こる「化学反応の振動」です。
本書では、こういった仕掛けで生じる生物界における「同期現象」だけではなく、振り子時計の同期やローソクの炎の同期、電力の送電ネットワークの同期等、さまざまなジャンルにおいて見られる現象をとりあげ、その発生メカニズム等を平易に解説しています。
そして、著者の関心は、こういった「同期現象」が学際的な観点から深く研究されることによる新たな革新の可能性にあります。
(p44より引用) 「リズムは同期を好む」という自然に潜む自己組織化の能力は新しい技術の原理として大きな可能性をもっているように思います。
全ての指令を司る制御中枢を持たず、複雑な作業を自律的に実行してくれるシステムへの期待です。
(p239より引用) 「分解し、総合する」一辺倒ではない科学のありかたが可能なことは、もっと広く知られてよいと思います。それは分解することによって見失われる貴重なものをいつくしむような科学です。・・・複雑世界を複雑世界としてそのまま認めた上で、そこに潜む構造の数々を発見し、それらをていねいに調べていくことで、世界はどんなに豊かに見えてくることでしょうか。
昨今のビッグデータ解析は圧倒的なデータ処理能力を活用した「分析型」解明スタイルという側面があります。とはいえ大量高速処理によるシミュレーション機能の向上は、複雑系世界の研究に大きく貢献するものでしょう。
本書における「同期」や著者の前著における「カオス」のような概念は、異分野を横断的に統合する力を持つもので、その研究の進展はとても楽しみなものです。そう感じるのは、集中制御と自律分散のどちらを好ましく思うかという私の思考の傾向によるのかもしれませんが。