検察による冤罪事件の被害者たる元厚生労働事務次官村木厚子さんの著作です。
以前、podcastで村木さんの穏やかながらも理路整然としたお話ぶりを聞き、一度その著作を読んでみたいと思っていました。
期待どおり、「まえがき」からいきなり印象的な言葉が飛び込んできました。
村木さんは、自らが37年間従事していいた「官僚」を「国民の願いやニーズを制度に変える翻訳者」と“意味づけ”ていらっしゃいました。
また、国としての変革スピードを加速させる方法として、村木さんはこう語っています。
(p6より引用) 先が読めない、変化が速い時に、一人のリーダーに変革をゆだねるのはリスクが高すぎます。それなら、どうやってこの国の変革のスピードを加速できるのか。どのように組織を変えていくべきなのか。様々な仕事を経験する過程で私が重要だと感じたのは、組織の一人ひとりがあるべき方向性を主体的に考えることのできる組織を作ることです。それを「静かな改革」と呼んでくれた方もいます。そうした仕事の進め方の経験が、日本型組織の硬直化した部分を変えていくヒントになるならば、とてもうれしく思います。
至極、納得ですね。
このコメントに代表されるように、本書で示されている村木さんの指摘はとても納得できるものです。
「第3章 日本型組織で不祥事がやまない理由」の章では、こういった指摘がされています。
(p99より引用) 自分たちが「ずれた」状況に陥っていないかどうかを点検するのに、いい言葉があります。
「必要悪」という言葉です。冷静に見れば「悪」なのに、「これは仕方なかった」とか「このためにはこうする必要があった」など、自分たちの行為を正当化しようとする時に使われやすいこの言葉や考え方が出てきたら、要注意です。
これも「なるほどそうだ」と思いますね。こういう“言い訳”的な言葉はつい使ってしまいがちです。
それから、キャリア官僚として入省してからの「お茶くみ」に係る村木さんの考え方。これも人柄が滲み出ます。
(p150より引用) お茶くみは断固拒否、そんなふうに闘えたらどんなにいいでしょう。でも、そうできない臆病な私としては、何か意に染まないことや、客観的に見ておかしいと思った時は、胸に抱えながら次のチャンスを待つしかありません。それでも完全に諦めたり、考えるのをやめてしまったりしなければ、いつかチャンスはやってきます。スマートとはいえなくても、時間をかけて乗り越えていく方法もあると思います。
巻末の「解説」で読売新聞の猪熊律子さんが、“村木さん流の改革”をこうまとめてくれています。
(p228より引用) 当事者や、現場で活動をしている人の声をよく聞き、新しいアイデアを柔軟に取り入れながら、諦めずに、みんなと力を合わせながら活動を続ける。官僚時代に手がけた仕事にも見られた手法で、粘り強い活動がいつしか人々の意識を変え、制度をも変えていく。地道で、しなやかで、「静かな改革」とも呼べそうなこのやり方は、見方を変えれば、非常に現実的で、実践的で、合理的なやり方といえるだろう。
さて、本書を読み通しての感想ですが、村木さんの人柄そのもののような“邪心”を一切感じさせない近年では稀な著作だと思います。
語り口も至って自然体で穏やかで、そこに開陳されている考え方そのものがとても“真っ当”なんですね。
平尾誠二さんにちなんだ著作は以前も何冊か読んでいます。
本書は、平尾さんによる過去の著作6冊の中で語られた心に刺さる言葉を紹介したものですが、それぞれの章の冒頭に掲げられた羽生善治さん・岡田武史さん・山中伸弥さん・山口良治さん・佐渡裕さん・土田雅人さん・・・、平尾さん所縁の方々による寄稿で改めて平尾さんの“人となり”を思い抱くことができました。
加えて、長年平尾さんを撮り続けた岡村啓嗣氏の写真とのコラボレーションとして構成されているのが特徴的ですね。数々の写真は、文章とはまた別の感慨を呼び起こします。
さて、改めて本書で再会した平尾さんの、とりわけ彼らしい言葉を書き留めておきます。
(p68より引用)
伝統の継承とは、
以前からあるものに否定形をつけて、
新しいものを創造すること、
破壊から新たな創造を生み出すこと
もうひとつ “「個」と「組織」”に関する平尾さんの信念。
(p209より引用) 強いチームの根幹をなすのは、強い「個」である。個を個として自立させその能力を最大限に引き上げなければ,強い組織はつくれない。組織を強くするためには、まず個を強くすることだ。・・・
個々の選手のキャパシティが広がれば、そこへ新しい知識や戦術を引き込むことができる。そうなったとき、チームとしてのキャパシティはさらに広がり、もう一段高い領城に我々は登ることができる。
「個」が強くならなければ、強い「組織」などつくれるはずがない、まさに私も完全に同意する平尾さんの考え方です。
そして最後は、“One for all, all for one”。
私も間違って理解していましたが、このフレーズ、「ひとりはみんなのために、みんなはひとつのために」なんですね。
最終目標は、“みんなでボールをつないでひとつのトライを取る”こと。確かに、その解釈の方が圧倒的にしっくりと納得できます。
ちょっと前に、後藤正治さんの「拗ね者たらん」を読んで、ともかく本田靖春さんの著作を読んでみたくなりました。で、まず手に取ったのが、代表作のひとつを言われている本書です。
確かに緻密な事実の堆積に加え、それを描き切る本田氏の並々ならぬ筆力を感じます。
(p246より引用) 泉検事は国家権力を半ば暴力的に行使して、彼自身の同僚であり、同時に立松と交情のある検察関係者を売り渡すよう、背信行為を迫ったのである。
「最後の誇りまで捨てさせないで下さい」と立松が懇願するようにいったのは、新聞記者の矜持から出た峻拒というよりも、それこそ最後の一枚を剥ぎ取られかかった生身の悲鳴に近い。立松は裏切者にはならなかった。しかし、屈辱の思いは刻み込まれたのである。
評判どおりの骨太で高密度のノンフィクション作品ですね。
ただ、私の好みかといえば、どうもちょっとしっくりこないものがありました。
私がよく読んでいたのは吉村昭さんや柳田邦男さんたちの作品群だったのですが、「どうしてかな?」と考えてみたところ、ひとつ気づくところがありました。
この「不当逮捕」には著者の本田氏本人も主人公と深い因縁をもつ関係者のひとりとして登場するんですね。ここにおいて、著者は第三者ではなく、作品も「完全なる客観性」に徹した記述ではなくなっているわけです。
もちろん吉村作品や柳田作品に主観的記述がないかといえば、そうではないでしょう。ただ、主人公への思い入れの浸潤度合いは、質的にも量的にも異なっています。
ノンフィクションとしての是非ではなく、私が抱いた(私が思うノンフィクション作品との)“違和感の源”はここだと思いました。
図書館でも実際に学校で使っている「教科書」を借りることができるということなので、ちょっとトライしてみました。小学校6年生用の「道徳」の教科書です。
まず、最初に「道徳学習の目的と学習姿勢」について書かれています。
(p4より引用) 道徳は、心について考え、自分の心を豊かにしていく時間だよ。思ったことをすなおに話そう。
みんなで話し合って、考えを深めよう。そして、自分をすなおに見つめよう。
そして、教材ですが、教室での進め方として、たとえば、こんなふうに書かれています。
(p97より引用) 言葉のプレゼント
これから「言葉のプレゼント」をします。友達に, おうえんや, 励ましの言葉をおくりましょう。
1.4人グループをつくります。
2.グループの人に、どんなおうえんやはげましの言葉を贈るかを, 96ページのシートの (1)に 書きましょう。
3.グループの中の一人に、残りの人から、 シートに 書いたことなどを大きな声で言って, 言葉のプレゼントをおくります。
ほかの人から言葉のプレゼントをもらった人は、「言葉のプレゼント、 ありがとう。」と言って受け取ります。
言葉のプレゼントをもらう人は, 一人ずつ交代します。 グループの全員に、 同じように言葉のプレゼントをおくります。
4.言葉のプレゼントをもらって, 気づいたこと、感じたことなどをシートの(2) に 15 書きましょう。
5.クラス全体で振り返りをします。
気づいたこと, 発見したことなどを 発表しましょう。
違和感がありますねぇ。
ここまで細かく「こうするんですよ」と示すやり方は、 “ひとつの望ましいとしている型にはめていく”ようで、どうもにも気持ちが悪くなります。「ほかの人から言葉のプレゼントをもらった人は、「言葉のプレゼント、 ありがとう。」と言って受け取ります。」とかになると、頭がクラクラしてきます。
6年生にこんな「取ってつけたお芝居のようなセリフ」を言わせて・・・、彼ら彼女らこれで素直な気持ちになれるでしょうか、より精神的に自律した成長ができるでしょうか?
もうひとつ、「せんぱいの心を受けついで」とのタイトルの教材から、気になったくだりを書き出してみます。
(p112より引用) 広美は、ふと作文集の中の名前に目がいきました。家の近くの米屋のおじさんの名前でした。「キクづくりで学んだこと」という題で書かれています。その中で広美が心をひかれたのは、「キクづくりによって学校中の人たちの心が一つになった」というところと、「こうした学校のよい伝統をこうはいに引きつぎたい」というところでした。
さっそく、帰りに米屋に寄ってこのことを話すと、おじさんは、
「そんなことを書いたかなあ。ても、作文はともかくとして、キクづくりは学校のほこりだよ」
と、にこにこしながら広美に言いました。広美は自分が褒められたような気持ちで家に帰りました。
ここに至っては、完全に「ある価値観」を称揚していますね。
その価値観の是非が問題ではありません。こういった進め方で、子供たちは“自分で考えた自分の価値観”を築くことができるでしょうか。ひとによっては、「伝統墨守」よりも「因習打破」という考え方があってもいいはずです。
道徳教材の作りを辿ってみての感想です。
児童に「自分で考える」姿勢を身に着けさせようと目指していることは認めます。そのこと自体は絶対的に正しいことですが、さらに「考える内容や方向」まで規定しようという意思がどうにも教材から透けて見えてきます。
私は、それは望ましいゴールではないと思います。
ちょっと前に小田島雄志先生の「ぼくは人生の観客です (私の履歴書)」を読んだのですが、少々欲求不満感が残ったので、改めて先生の「シェイクスピア」に関する本を読んでみたくなりました。
1590年の「ヘンリー6世」から1613年の「ヘンリー8世」まで、第一期(1590-4)の修業時代、第二期(1594-1600) の成長時代、第三期(1601-8)の絶頂期、 第四期(1608-13)の晩年と分け、すべてのシェイクスピアの作品をスコープにいれた小田島流の解説が楽しいですね。
やはり、最初に書き留めておく作品は「ロミオとジュリエット」です。
小田島先生はこのシェイクスピアの代表的作品の魅力をこう記しています。
(p99より引用) 『ロミオとジュリエット』というと、ロマンティックな悲恋物語をイメージする人が多いけれど、実は、そのアクションだけでは制しきれないさまざまな要素をふくんでいる劇なのである。対照しあう各要素は、数例の引用にもあきらかなように、抒情的なところは思いきって抒情的に飛翔し、猥雑なところは思いきって猥雑に横行し、悲しいときは精いっぱい号泣し、おかしいときは腹の底から哄笑し、二人の悲恋はこの上なくロマンティックに歌いあげ、青春の群像はひたすらエネルギッシュに疾駆し、それぞれが劇的統一をうち破ってまで自己主張している。ぼくはそこに『ロミオとジュリエット』の爽快な魅力を感じとり、そのような世界を〈ごった煮の世界〉と呼びたいのである。
次は、やはり「ハムレット」。
小田島先生の説く“ハムレットとの接し方”です。
(p183より引用) 近代心理的リアリズム劇に慣らされた目でハムレットを見ようとすると、その言動の一つ一つに心理的動機を探りたくなり、四苦八苦することになる。だが、この時期のシェイクスピアが追究していたのは、ありあまる動機がありながら非行動という形の行動にとどまったり、理性的裏づけがないまま感情に駆られてわれを忘れて衝動的行動に出てしまったりする人間像であった。
その点さえおさえておけば、「文学のモナ・リザ」と呼ばれたり、「スフィンクスが英語をしゃべったらハムレットのようにしゃべるだろう」と言われたりする、この謎に満ちた悲劇の主人公も、その謎のほとんどが氷解して、熱い血の流れている一個の人間として、ぼくたちに身近な存在となる。・・・
その言動を、バラの香りのように直接感じとるのが、ハムレットにたいする正当な接しかただろう。
そして、最後は「あとがき」で語られる“小田島先生にとってのシェイクスピアとは”。
(p248より引用) ぼくにとって、シェイクスピアは学問上でも舞台上でもいわば発見の連続としてあった。読むたびに見るたびに、人間とはこのように愛し、このように悲しみ、このように悩み、このように行動する存在であるのか、という発見を、驚きと喜びをもって胸中に刻みつけてくれるのである。
この本の出版は1982年ですが、ちょうどこのころ(ほんの少し前)に私も教養学部で小田島先生の講義を履修していたんですね。もう40年以上前になりますが、うすぼんやりと先生の熱量の高い講義模様が思い出されます。


























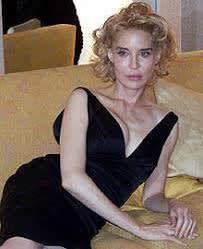








![新しい道徳 6 新訂 [令和2年度] (小学校道徳科用 文部科学省検定済教科書)](https://m.media-amazon.com/images/I/512K2EbGRoL._SL160_.jpg)











