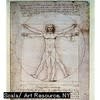 レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci 1452~1519)は、盛期ルネサンスを代表する芸術家でもあり科学者でもあった「万能の才人」です。
レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci 1452~1519)は、盛期ルネサンスを代表する芸術家でもあり科学者でもあった「万能の才人」です。
ダ・ヴィンチに関する本は、以前、「ダ・ヴィンチ天才の仕事―発明スケッチ32枚を完全復元」を読んだことがあります。
今回読んだ「知をみがく言葉」という本は、彼が遺したノート(手稿)から芸術・科学・人生にまつわる言葉を抜粋したものです。
本書に収録されているダ・ヴィンチの言葉のなかから、いくつかをご紹介します。
まずは「絵画」について。
ダ・ヴィンチにとっての絵画は、「科学」のひとつの表現形式だったのでしょうか。こういった言葉が連なります。
(p16より引用) 絵画を軽んじる者は、哲学も自然も愛することはない。
(p18より引用) 絵画‐やがては滅んでしまう存在の移ろいやすい美しさを留めておくことができる素晴らしい科学。
(p19より引用) 絵画には、文学のようにいくつもの言語に翻訳する必要がない。
また、「芸術作品に対する判断」について。
(p62より引用) 作品に寄り添い過ぎると、判断を大きく誤る恐れがある。
(p63より引用) 他人の作品では、過ちをすぐに見つけられるのに、自分の作品ではなかなか見つけられない。
人の過ちは小さなものでも見咎めるのに、自分の過ちは大きなものでも無視してしまうことがある。
このあたりのくだりは、私たちでは当然のことですが、「かのダ・ヴィンチですらそうか」という感じです。
その他「科学」のジャンルに分類されているものから、「経験に根ざした真実」を重視するダ・ヴィンチの言葉です。
(p98より引用) 良い判断というのは、明確な理解から生じる。
明確な理解は正しい法則から、
正しい法則は、正しい経験から生じる。
正しい経験は、すべての科学と芸術の共通の母である。
ダ・ヴィンチは、「経験から真実に至る論理的プロセスの重要性」を語ります。
ロジカル・シンキングの基本動作です。
(p104より引用) 手続きは体系的でなくてはならない。
命題にはいくつもの部分から成るものがあるので、部分と部分の区別が必要になる。
それができれば混乱は生じず、他人からも理解しやすくなる。
最後は、「真実」を称えるダ・ヴィンチの言葉です。
(p250より引用) 真実は素晴らしい。
たとえ、取るに足らないものを褒める言葉でも、真実ならばそれは気高い。
 |
知をみがく言葉 価格:¥ 1,365(税込) 発売日:2008-06 |
↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!




TREviewブログランキング












 1970年代から80年代にかけての手塚治虫氏の対談集です。
1970年代から80年代にかけての手塚治虫氏の対談集です。















