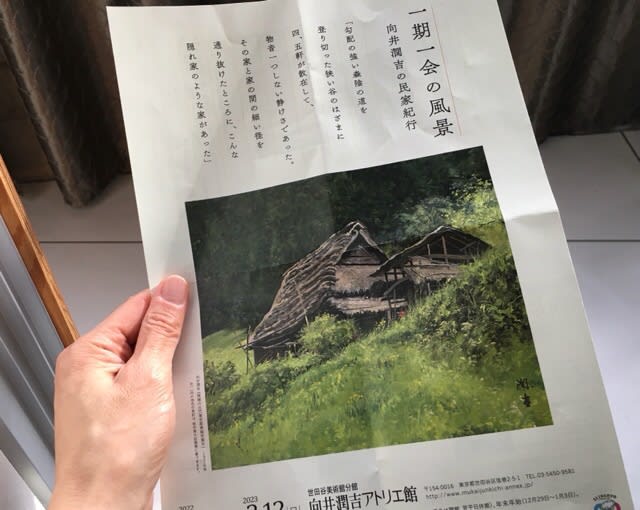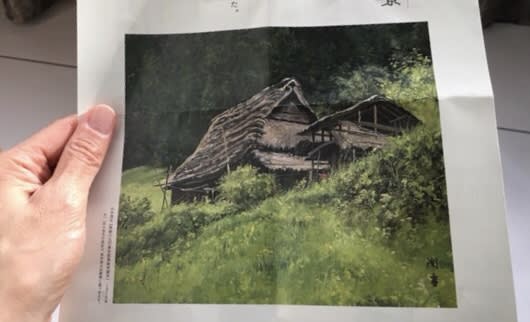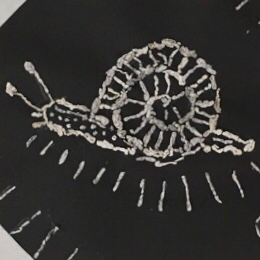世田谷代田駅周辺の戦災焼失区域を朱色で表した昭和20年の地図を見ています。
前回は、世田谷代田駅から南斜面に位置する円乗院や住宅地の戦災痕を取り上げてみましたが、今回は駅の北側部分で朱色が広がる箇所に焦点を当てて、終戦間際に壊滅的な被害に遭った井の頭線を復旧させるべく新設した幻の線路跡を探してみたいと思います🐾
しかし、不思議ですよね。。🤔
今でも都会の喧騒から上手に外れている代田の丘の小さな住宅地や駅周辺に、当時何故たくさんの爆弾が落とされたのでしょうか。
しかも、すぐ隣には、二つの私鉄が交差する下北沢駅があるのに、地図の朱色範囲を見る限りは被害がずいぶんと少なく見える。。
当時、代田の町には標的となるような人物、もしくは対象物があったのでしょうか❓❓

さて。こちらは世田谷代田駅に新しく併設された舗道です👀
駅前の案内板の説明を読むと、舗道の明るいレンガタイルのデザインは、戦災で失われた井の頭線車両を補給するために、この駅から新代田駅までを突貫工事で繋いだ臨時線路をイメージしているそうです。
実際、連絡線はこの柵の向こう側に敷設されたようですが、実は世田谷代田駅って、小田急線のなかで唯一戦災に遭っている駅舎なんだとか。。
しかし、当時は同じ小田急系列だった井の頭線の方が、被害がより深刻だったようでして、昭和20年5月末の大空襲でほとんどの車両が壊滅的な被害を受けたために、急遽に他社から戦災応急復旧車を導入せざるを得なくなり、連絡線の必要が生じたわけなんですね。
そんな史実を、このタイルのデザインは伝えていたなんて、しょっちゅう、ここを歩くが知りませんでした💧

お次の写真は世田谷代田駅裏手の住宅地から。。。🚃
かつての連絡線跡は、現在更地になっているこのあたりを抜けていたようですが、さすがに当時の面影は皆無ですね。
どうやら、連絡線は焼失した個人の敷地内に造られたようですが、戦後しばらく経った昭和28年に元の住民らから土地返還の訴えが起こり、いよいよ廃線になったのだとか。。
つまり、この路線は戦時下の強制発動で人の土地に敷設されていたために、戦後、再び平和とともに土地を取り戻した人々らがそこに新たな暮らしを築きあげれば、必然的にその痕跡すべてが埋没してしまうわけですよね。。
これでは、痕跡など見つからないわけだっ💧

と、そんななか👀
土が剥き出しの或るお宅の奥に面白そうなものを捉えました。
これはガンタ積みの壁のようですね。。

かつての線路はここを通っていた可能性が高いため、このガレキは戦災痕、、もしかすると1ヶ月で完成したといわれている突貫工事ならではの線路敷設の道床に混じっていたものかもしれませんね❗️
注)たまたま大家さんからお話を聞くことができたのですが、ここは土の中にもこうした石が埋まってるよ、、とのことでした。写真は許可を得て撮っています。

その先。見えない線路はこの敷地の壁のすぐ内側を真っ直ぐに続いていたようだぞ🚃

井の頭線の新代田駅近くなると、線路は道に沿ったカタチにゆるくカーブしながら続きます。

向こうに井の頭線の電車が見えてきましたが、おそらくこのあたりから連絡線は井の頭線と合流していたようです。
それは、外壁が斜めにプランニングされたアパートの敷地に沿って、少し土地が盛られている奥の建物側を連絡線が走っていた、、と想定するとわかりやすいですね❗️

こうして、80年前にこの連絡路線を使って、戦災で応急処置された車両や他社からの応援車両が、当時瀕死の状態だった井の頭線へとどんどん送り込まれていったわけですねっ。
ところで、、この駅が周りよりも低く見えるのは、ここが谷間だったからだと、今回地図を見て気づきました👀
戦災焼失図ではこの駅舎あたりは朱色、、ということは、世田谷代田駅同様に、ここも戦火に遭っているようなので、谷間の駅ではかなりの火の勢いだったかもしれませんね。

そう気づくと、、👀
駅ホームに今も残されている安山岩らしき石垣がやけに赤いのは、そんな時代の死線をかいくぐった証だったりするのかな、、と最後はふと思ってしまったのでした。
因みに当時の両駅名は、世田谷代田が世田谷中原駅で、新代田は代田二丁目駅だったことを加えておきます。