きのうの朝、いつものように東名高速の港北PA に入っていったとき、クルマ
に入っていったとき、クルマ の積算距離メーターが、90,000kmを表示していることに気づきました。
の積算距離メーターが、90,000kmを表示していることに気づきました。
どうかクルマを停めるまでこのままでありますように とソロソロとクルマを進め(速度が速かろうが遅かろうが、走行距離には変わりないのですけど…
とソロソロとクルマを進め(速度が速かろうが遅かろうが、走行距離には変わりないのですけど… )、駐車スペース
)、駐車スペース に停めたら、、、
に停めたら、、、
メーターの表示は「90,000km」のままでした
よかった、よかった…
こちらで書いたように、「88,888km」を記録したのが10月29日で、「77,777km」が6月27日でした。
「4ヶ月で1万km」のペースで、淡々と走行距離を積み重ねています。
この分ですと、来年3月初めには、「99,999km」に、そして続けざまに「100,000km」 に達しそうです。
に達しそうです。
この時も、しっかりと写真 に収められるシチュエーションだと良いのですが…
に収められるシチュエーションだと良いのですが…

 これはきのうの記事の中で書くべきだったと思いますが、今夜は「MISIA 星空のライヴVII -15th Celebration-」の能代公演でした。
これはきのうの記事の中で書くべきだったと思いますが、今夜は「MISIA 星空のライヴVII -15th Celebration-」の能代公演でした。
今回のツアーでは、「生MISIAは初めて 」の聴衆の比率が一番高いかもしれない能代公演、どんなライヴになったのでしょうかねぇ…
」の聴衆の比率が一番高いかもしれない能代公演、どんなライヴになったのでしょうかねぇ… 。
。
冬 の日本海側は寒いけれど、湿度たっぷり
の日本海側は寒いけれど、湿度たっぷり なので、MISIAの喉には絶好のコンディション
なので、MISIAの喉には絶好のコンディション だったと思うのですが…
だったと思うのですが…
ちなみに私、能代市に行ったのは、もう数十年前 に、親の知人の親戚の家(複雑…
に、親の知人の親戚の家(複雑… )に出かけた1回きり(通過
)に出かけた1回きり(通過 or 乗り換え
or 乗り換え しただけなら数回あります)。
しただけなら数回あります)。
思い起こすと、実家にいた頃、秋田市より県内南部に出かける機会は結構あったと思いますが、男鹿半島より北には、ほんの数回しかありません…
ずっと小坂町には行ってみたいと思っているのですけど…
 そして2年後…:2015/08/11 帰省ドライブ&観光の2日目は超満足
そして2年後…:2015/08/11 帰省ドライブ&観光の2日目は超満足











 」
」
 の
の など、
など、 に出演することがなかったMISIAが紅白歌合戦に出演することになった経緯について、
に出演することがなかったMISIAが紅白歌合戦に出演することになった経緯について、
 (私の感想は
(私の感想は

 と思っています
と思っています から歌声を響かせて欲しいと思っています
から歌声を響かせて欲しいと思っています のですが、もしMISIAが今年の紅白歌合戦に出演するとなれば、
のですが、もしMISIAが今年の紅白歌合戦に出演するとなれば、
 に、
に、
 ぅ~
ぅ~
 私の
私の で完全に
で完全に
 」
」 に帰り着いたら
に帰り着いたら
 していたそうで、私としては
していたそうで、私としては の開花も
の開花も




 なっていました。
なっていました。
 されていました
されていました ですが、どうか
ですが、どうか の
の
 ようにしか見えないのですが…
ようにしか見えないのですが…

 を迎えています。
を迎えています。

 には、
には、


 を片手にベンチに腰掛けて
を片手にベンチに腰掛けて
 が行われていて、
が行われていて、

 にしているのは、この
にしているのは、この



 が多すぎるし、
が多すぎるし、 点で、
点で、

 、
、






 というものです。
というものです。

 」
」 を求めて、どれほど
を求めて、どれほど を
を
 (
(

 では
では






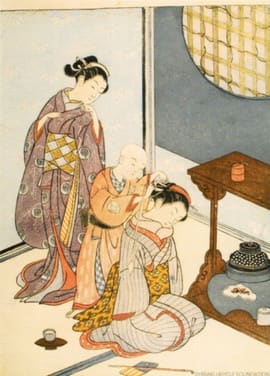

 の表紙にもなった
の表紙にもなった
 たち
たち しました。
しました。

 この時代
この時代


 に向かうつもりで、事前に
に向かうつもりで、事前に
 始めましたが、
始めましたが、 で見る
で見る
 というもので、いかにも
というもので、いかにも 番組では、
番組では、 なんぞも、保有・展示されるだけでなく、
なんぞも、保有・展示されるだけでなく、
 に興味を持っている人は、他のチャンネル
に興味を持っている人は、他のチャンネル
 は
は


 に乗って登った? はたまた駕籠に乗って登った?
に乗って登った? はたまた駕籠に乗って登った? 
 がキツい…
がキツい…










 と同様に2日連続となる
と同様に2日連続となる




 を
を















 をお祝いするお祭りだったのです(そもそも
をお祝いするお祭りだったのです(そもそも

 が近そうでしたし、
が近そうでしたし、









