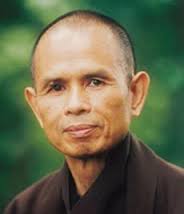人間の知性はどこまでもとらえ切れるということでしょうか?
Young Man Luther 『青年ルター』p192の第4パラグラフから。
フィチーノは、この視点をその価値の限界まで引き延ばしました。フィチーノの言葉は、多くの点で、私どもの世界観が価値の点からみて大丈夫、限界があるのかを示していました。フィチーノが言うには、「人は、天国を作った神と同程度の天才を持ち合わせているということを否定できるでしょうか、否定などできません」ということです。人は天国さえも作れるということを否定できるのでしょうか、出来ませんね。人はその道具と、天国の素材を手に入れることだってできることを否定できるでしょうか、これもできません、という訳です。
神をも恐れぬ、という言葉があります。ルネッサンスの人々は、その危険に陥っていったのでした。