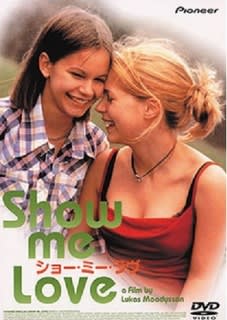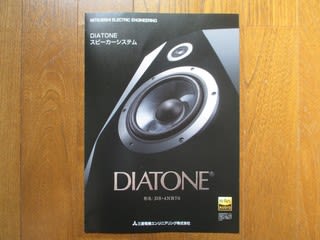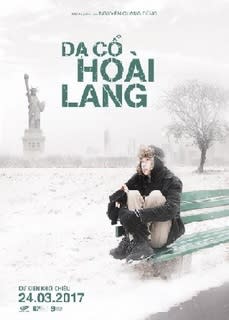低調な出来だ。実話を基にしているらしいが、リアリズムで押し通している気配は無い。かといってコメディにして笑い飛ばそうとしている様子は見受けられないし、ファンタジー映画にしてしまうほどの思い切りの良さも無し。まことに居心地の悪い映画なのだ。
熊篠慶彦(通称クマ)は、脳性マヒで車椅子の生活を送りながら、障害者の性への理解を訴え続ける活動家である。ある日クマは、新著のPRを兼ねた講演会で、ソープ嬢のミツと知り合う。勝手にクマに愛を告白し、やたらハイテンションで付きまとうミツは、実は人格障害を負っていた。初めは戸惑うクマだったが、ミツの一途な想いに心を動かされ、本気で彼女と付き合うようになる。しかし、周囲のシビアな状況が2人の行く手を阻む。熊篠自身の体験談をベースにした作品とのことだ。
どうしてミツがクマに惹かれたのが分からない。第一、なぜ彼女がクマの講演を聞きに来ていたのか、その理由さえ示されていない。見るからにインテリっぽい連中が客席を埋める会場ではミツの存在は浮いているのだが、その構図が納得出来るような“御膳立て”が無い。当初のシチュエーションから斯様な体たらくなので、あとの展開は言わずもがな。
クマの介護をしている恵理の性格付けは明確ではなく、その夫の悟との関係性もぎこちない。ミツの身元引受人の晶子は怪しげな占い師で、ミツに対するフォローも“怪しい”ままである。クマが自宅で転倒して命の危険にさらされる場面を除いて、ストーリーは何ひとつリアリティが感じられない。
ミツが入院してクマとの接触を禁じられてからの筋書きは、まるで絵空事だ。何やら“悪の結社”みたいな病院のスタッフと主人公2人との追っかけシーン(?)に至っては、ヘタな寸劇を見せられているようで脱力した。こんな状態で“幸せになるためのパーフェクト・レボリューションを達成する”だの何だのとシュプレヒコールをブチあげられても、観ているこちらは鼻白むばかりである。
脚本も担当する松本准平監督の仕事ぶりは、ハッキリ言って下手だ。話の練り上げ方も、ドラマの盛り上げ方も、まるで及第点には達していない。クマを演じるリリー・フランキーはよくやっていたと思うが、ミツに扮する清野菜名はヒドい。ちっとも障害者に見えないし、何よりあのキンキンした声が不快だ。もっとも、それは松本監督の演技指導が万全ではないためかもしれない。事実、小池栄子や岡山天音、余貴美子といった面々を脇に揃えていながら、まるで機能させていないのだ。
とにかく、題材は悪くないのに作り方を間違えたような映画で、あまり観る価値は無いと言える。