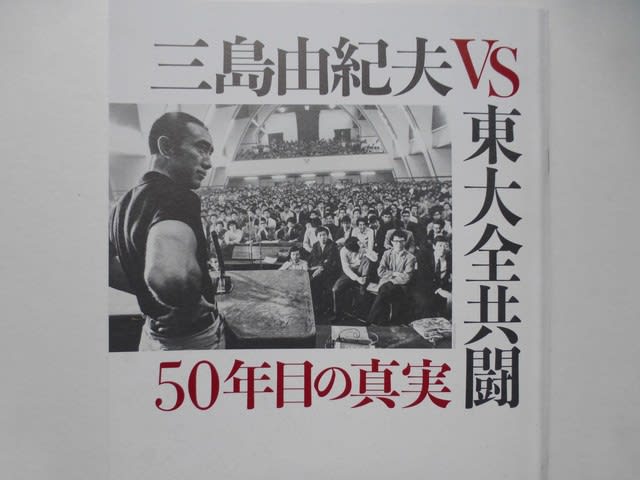今のアメリカを舞台に、中年カップルの離婚闘争を描いた作品で、先日のアカデミー賞では、作品賞をはじめ主演女優、主演男優、助演女優、脚本、作曲と6部門にノミネートされた。惜しくも、今回は「パラサイト 半地下の家族」に話題を持っていかれたが、私は、本作はもっと注目されてもよいと感じたので、昨年の公開だが、今回、取り上げた。
女優と舞台監督という立場で知り合い結婚し、子供を一人授かった夫婦が、ニューヨークとロサンゼルスを拠点に仕事をしながら、人生を歩んできた。しかし、結婚生活がうまくいかなくなり、離婚に向かうことを決意するところからこの物語が始まる。最初は、二人で話し合って協議離婚を目指していたが、それもうまくいかなくなり、弁護士を立てての争いに発展してしまうのである。その辺りから、「離婚」というものが、一度は愛し合った二人が痛みを伴いながらも、次の人生をスタートさせるという人間の感情的な部分は排除され、離婚をひとつのビジネスとして捉える人達によって牛耳られ、肝心の二人の気持ちはどこかにいってしまうのである。裁判で勝利を掴み取るにはどうすれば良いのかの1点に集中するのである。その部分は特に今の時代を表していると感じた。お金という物差しで測る、勝ち負けをはっきりさせる最近の風潮であろうか。
何が正解で、何が間違いか。何事にも「ずばり正解!」を私も自然と求めてしまっているし、世間もそれを追求する時代。効率を優先し、間合いや譲り合いは後回しする。「〇〇ファースト」もその一環だろうか。声が大きい人の意見に皆が偏り、それ以外の存在自体がかき消される。でも、実際の人生はそうではない。分かろうとするが、何か掴めない、そういったモヤモヤした気持ちを抱えながらも、人は走っていく。ラストシーンがそれを示している。少し救われた気持ちになった。決して、ハッピーエンドではない、完璧ではないが、それが人間である。どういう結果が出ようが、お互いに気持ちが吹っ切れて、新しい形を模索する可能性が感じられて良かった。
賞レースでは、本作で唯一アカデミー賞を獲得したローラ・ダーン(助演女優)は、とても印象に残った。前述の離婚をビジネスに捉える弁護士役で、テンションが高く高圧的で嫌味っぽく話す難しい役柄だが、「こんな人必ず居るね」と感じた。他の助演女優賞候補作をすべて観ていなかったが、獲得の可能性は一番高いのではと思った。賞は逃したが、スカーレット・ヨハンソンとアダム・ドライバーの微妙な表情や、話し合いながら、徐々に気持ちが高ぶってしまうシーン等も良かった。
また、1979年米映画「クレイマー、クレイマー」との比較がよく取り上げられていたので、急遽、観なおした。40年前以上の映画なので、時代背景はあるものの、何が夫婦にとって良いのか?何が家族にとって良いのか?何が子供によって良いのか?を問い掛ける意味では同じと感じた。その当時は、まだまだ男尊女卑の意識が色濃く残る時代(多分!)に「離婚」というテーマを性別関係無く取り上げた意味では画期的だったのかもしれない。なので、アカデミー賞作品賞を受賞したのだろう。私は85年頃に観たと記憶しているが、最初の印象は、女性が子供を捨てて出ていくことが衝撃だった。私も男尊女卑の気持ちがあるのかもしれない。それと、変な題名だなという印象だった。原題は、「Kramer vs.Kramer」、クレイマーさんとクレイマーさんとの闘い。その後、この作品は、それまで私が観てきた(数年程度だが)ハッピーエンドのハリウッド映画とは違うなと感じたことが記憶に残っている。今、観なおすと、時代を先取りした映画だったように思う。今回観なおして、テーマ曲の旋律に改めて聞き入ってしまったのと、ファーストシーンのメリル・ストリープの演技と監督の演出には身震いした。
以下2つの情報は、映画評論家の町山智浩さんの番組で見た内容だが、本作は監督の実体験をベースにした作品とのこと。元妻は「ヘイトフル・エイト」のジェニファー・ジェイソン・リーでその離婚協議の際に、相手側(相手側というのが面白い!)の弁護士だったのが今回のローラ・ダーンが演じた役のモデルだった!真に迫る演技が生まれたのは当然だった?しかも、その彼女は、ブラッド・ピットとアンジョリーナ・ジョリーが離婚調停する際にも弁護士として活躍していたとのこと。ちなみに、そのアンジョリーナ・ジョリーの元夫はビリー・ボブ・ソーントンという人で、ローラ・ダーンの元恋人。ハリウッドは狭い中でくっついたり離れたりしている。何とも複雑。
また、本作はNetflix配給である。昨年のアカデミー賞受賞(外国語映画賞)「ROMA/ローマ」に続き、「アイリッシュマン」、そして本作とかなりの勢いである。公開対象が広いので、ハリウッド(所謂スタジオ系)より会社規模は大きいらしい。映画が映画館で観る時代が変わろうとしている。最近の新聞記事では、コロナウィルス感染を防ぐため家庭で過ごす人が増え、全世界でかなり契約件数が伸びているそうだ。今は、映画館が厳しい状況だが、コロナ収束後は、ハリウッドにも頑張ってほしい。そういう意味では、授賞式が2月よりもう少し遅かったら、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」が受賞していたかも・・・。
(kenya)
原題:Marriage Story
監督・脚本:ノア・バームバック
撮影:ロビー・ライアン
出演:スカーレット・ヨハンソン、アダム・ドライバー、ローラ・ダーン、アラン・アルダ、レイ・リオッタ他
女優と舞台監督という立場で知り合い結婚し、子供を一人授かった夫婦が、ニューヨークとロサンゼルスを拠点に仕事をしながら、人生を歩んできた。しかし、結婚生活がうまくいかなくなり、離婚に向かうことを決意するところからこの物語が始まる。最初は、二人で話し合って協議離婚を目指していたが、それもうまくいかなくなり、弁護士を立てての争いに発展してしまうのである。その辺りから、「離婚」というものが、一度は愛し合った二人が痛みを伴いながらも、次の人生をスタートさせるという人間の感情的な部分は排除され、離婚をひとつのビジネスとして捉える人達によって牛耳られ、肝心の二人の気持ちはどこかにいってしまうのである。裁判で勝利を掴み取るにはどうすれば良いのかの1点に集中するのである。その部分は特に今の時代を表していると感じた。お金という物差しで測る、勝ち負けをはっきりさせる最近の風潮であろうか。
何が正解で、何が間違いか。何事にも「ずばり正解!」を私も自然と求めてしまっているし、世間もそれを追求する時代。効率を優先し、間合いや譲り合いは後回しする。「〇〇ファースト」もその一環だろうか。声が大きい人の意見に皆が偏り、それ以外の存在自体がかき消される。でも、実際の人生はそうではない。分かろうとするが、何か掴めない、そういったモヤモヤした気持ちを抱えながらも、人は走っていく。ラストシーンがそれを示している。少し救われた気持ちになった。決して、ハッピーエンドではない、完璧ではないが、それが人間である。どういう結果が出ようが、お互いに気持ちが吹っ切れて、新しい形を模索する可能性が感じられて良かった。
賞レースでは、本作で唯一アカデミー賞を獲得したローラ・ダーン(助演女優)は、とても印象に残った。前述の離婚をビジネスに捉える弁護士役で、テンションが高く高圧的で嫌味っぽく話す難しい役柄だが、「こんな人必ず居るね」と感じた。他の助演女優賞候補作をすべて観ていなかったが、獲得の可能性は一番高いのではと思った。賞は逃したが、スカーレット・ヨハンソンとアダム・ドライバーの微妙な表情や、話し合いながら、徐々に気持ちが高ぶってしまうシーン等も良かった。
また、1979年米映画「クレイマー、クレイマー」との比較がよく取り上げられていたので、急遽、観なおした。40年前以上の映画なので、時代背景はあるものの、何が夫婦にとって良いのか?何が家族にとって良いのか?何が子供によって良いのか?を問い掛ける意味では同じと感じた。その当時は、まだまだ男尊女卑の意識が色濃く残る時代(多分!)に「離婚」というテーマを性別関係無く取り上げた意味では画期的だったのかもしれない。なので、アカデミー賞作品賞を受賞したのだろう。私は85年頃に観たと記憶しているが、最初の印象は、女性が子供を捨てて出ていくことが衝撃だった。私も男尊女卑の気持ちがあるのかもしれない。それと、変な題名だなという印象だった。原題は、「Kramer vs.Kramer」、クレイマーさんとクレイマーさんとの闘い。その後、この作品は、それまで私が観てきた(数年程度だが)ハッピーエンドのハリウッド映画とは違うなと感じたことが記憶に残っている。今、観なおすと、時代を先取りした映画だったように思う。今回観なおして、テーマ曲の旋律に改めて聞き入ってしまったのと、ファーストシーンのメリル・ストリープの演技と監督の演出には身震いした。
以下2つの情報は、映画評論家の町山智浩さんの番組で見た内容だが、本作は監督の実体験をベースにした作品とのこと。元妻は「ヘイトフル・エイト」のジェニファー・ジェイソン・リーでその離婚協議の際に、相手側(相手側というのが面白い!)の弁護士だったのが今回のローラ・ダーンが演じた役のモデルだった!真に迫る演技が生まれたのは当然だった?しかも、その彼女は、ブラッド・ピットとアンジョリーナ・ジョリーが離婚調停する際にも弁護士として活躍していたとのこと。ちなみに、そのアンジョリーナ・ジョリーの元夫はビリー・ボブ・ソーントンという人で、ローラ・ダーンの元恋人。ハリウッドは狭い中でくっついたり離れたりしている。何とも複雑。
また、本作はNetflix配給である。昨年のアカデミー賞受賞(外国語映画賞)「ROMA/ローマ」に続き、「アイリッシュマン」、そして本作とかなりの勢いである。公開対象が広いので、ハリウッド(所謂スタジオ系)より会社規模は大きいらしい。映画が映画館で観る時代が変わろうとしている。最近の新聞記事では、コロナウィルス感染を防ぐため家庭で過ごす人が増え、全世界でかなり契約件数が伸びているそうだ。今は、映画館が厳しい状況だが、コロナ収束後は、ハリウッドにも頑張ってほしい。そういう意味では、授賞式が2月よりもう少し遅かったら、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」が受賞していたかも・・・。
(kenya)
原題:Marriage Story
監督・脚本:ノア・バームバック
撮影:ロビー・ライアン
出演:スカーレット・ヨハンソン、アダム・ドライバー、ローラ・ダーン、アラン・アルダ、レイ・リオッタ他