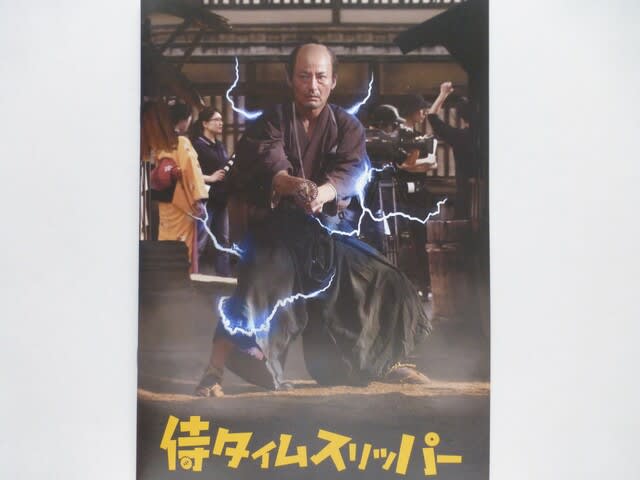スペインで3世代に渡って桃農園を営んでいる家族の物語。ある時、突然、地主から夏の終わりに土地を明け渡すようにとの連絡を受ける。その土地を使用してソーラーパネルの事業を始めるというのである。驚く家族だが、農園を始めた当初、土地を使用するにあたっては、口頭での話のみで、“契約書”は存在しない。それに対抗すべく方法策も見出せず、時間だけが過ぎていく。オロオロする祖父。イライラする2代目父親。心配する家族。無邪気に遊ぶ子供達。と言いつつも、それぞれの方法で、桃園を取り戻そうとするが、嚙み合わず、纏まらなく、そのまま、明け渡しの日が近づく。果たして、どうなることやら。。。
第72回ベルリン国際映画祭金熊賞(最高賞)受賞。全体的に抑揚が少なく、接写が多く、ドキュメンタリー風の映像。演者はプロの俳優ではなく、地元の人々を起用したとのこと。確かに、その土地、その仕草に足は付いている感じはする。なので、ドキュメンタリーと感じたのか。その狙いは、ドンピシャだが、商業映画として、もう少し抑揚がほしいところである。ただ、人間の日常は、毎日抑揚がある訳ではなく、淡々と過ぎていくもの。3世代の大家族のやりとりが、淡々と綴られていく静かな作品。父親は常にイライラしている。明け渡しの日が近づくが、何も対策が打てない自分への苛立ちと、この仕事しか知らず、新しい仕事への恐怖があると思う。その気持ちは分かるような気がした。ラストシーンは、明るく前向きになりたいものだが、本作は、その逆で、暗い気持ちになった。この先、この大家族はどうしていくのか。全員が不安な目をしてカメラを見つめて(その先にはショベルカーでの伐採が進む農園)いるので、こちらまで気持ちが沈んでしまった。近代化の波が押し寄せる地方農園の現実と捉えると、よくあるケースなのか。
大家族のエピソードの中で、息子が一晩遊び惚けて明朝帰ってきた時の、母親の行動には愛情を感じた。演出ではなく、俳優の地の演技のように感じた。父親から子供への叱責対応を諫める一撃も頼もしい。一瞬のシーンだが、見応えがあった。
映画は、言葉の説明は極力避けるというのが定石かと思うが、創作でも良いが説明や抑揚があった方が、商業的にもヒットするかもと思った。ただ、ベルリン国際映画祭は、社会派が取り上げられる傾向があるとのこと。選出されるタイプの作品かもしれない。
(kenya)
原題:Alcarras
監督・脚本:カルラ・シモン
撮影:ダニエラ・カヒラス
出演:ジョゼ・アバット、アントニア・カステルス、ジョルディ・プジョル・ドルセ、アンナ・オティン、アルベルト・ボッシュ、シェニア・ロゼ、アイネット・ジョウノ、モンセ・オロ、カルレス・カボセ、ジョエル・ロビラ、イザック・ロビラ、ベルタ・ピボ、エルナ・フォルゲラ、ジブリル・カッセ、ジャコブ・ディアルテ
第72回ベルリン国際映画祭金熊賞(最高賞)受賞。全体的に抑揚が少なく、接写が多く、ドキュメンタリー風の映像。演者はプロの俳優ではなく、地元の人々を起用したとのこと。確かに、その土地、その仕草に足は付いている感じはする。なので、ドキュメンタリーと感じたのか。その狙いは、ドンピシャだが、商業映画として、もう少し抑揚がほしいところである。ただ、人間の日常は、毎日抑揚がある訳ではなく、淡々と過ぎていくもの。3世代の大家族のやりとりが、淡々と綴られていく静かな作品。父親は常にイライラしている。明け渡しの日が近づくが、何も対策が打てない自分への苛立ちと、この仕事しか知らず、新しい仕事への恐怖があると思う。その気持ちは分かるような気がした。ラストシーンは、明るく前向きになりたいものだが、本作は、その逆で、暗い気持ちになった。この先、この大家族はどうしていくのか。全員が不安な目をしてカメラを見つめて(その先にはショベルカーでの伐採が進む農園)いるので、こちらまで気持ちが沈んでしまった。近代化の波が押し寄せる地方農園の現実と捉えると、よくあるケースなのか。
大家族のエピソードの中で、息子が一晩遊び惚けて明朝帰ってきた時の、母親の行動には愛情を感じた。演出ではなく、俳優の地の演技のように感じた。父親から子供への叱責対応を諫める一撃も頼もしい。一瞬のシーンだが、見応えがあった。
映画は、言葉の説明は極力避けるというのが定石かと思うが、創作でも良いが説明や抑揚があった方が、商業的にもヒットするかもと思った。ただ、ベルリン国際映画祭は、社会派が取り上げられる傾向があるとのこと。選出されるタイプの作品かもしれない。
(kenya)
原題:Alcarras
監督・脚本:カルラ・シモン
撮影:ダニエラ・カヒラス
出演:ジョゼ・アバット、アントニア・カステルス、ジョルディ・プジョル・ドルセ、アンナ・オティン、アルベルト・ボッシュ、シェニア・ロゼ、アイネット・ジョウノ、モンセ・オロ、カルレス・カボセ、ジョエル・ロビラ、イザック・ロビラ、ベルタ・ピボ、エルナ・フォルゲラ、ジブリル・カッセ、ジャコブ・ディアルテ