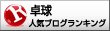航空会社間では、1980年にマレーシア航空の提唱で、WOFIA(Wings Of Friendship Inter-Airlines)という国際大会が始まり、2001年の22回大会まで続いた。第4回と第19回は、東京での主催大会のマネジャーとして、すべての大会運営を経験することもできた。特に1983年の第4回大会は250人(海外から200人)もの参加者がいたので、今思い返すと想像を絶するものがあった。個人的に参加したのは、第2回ハンブルク、第3回パリ、第7回コペンハーゲン、第13回クアランプール、第16回ハンブルク、第17回中国中山市、第22回バンクーバー大会だけであるが、多くの外国人と卓球交流という貴重な経験をすることができた。トップ選手ならともかく我々愛好家レベルでこれだけ国際交流を経験している幸せ者も少ないものと感謝している。
その後、1985年から4年間、ドイツでも地元のクラブに所属し、クライスリーガ(ブンデスリーガのはるか下のリーグ)でプレイし、クラブの仲間と汗を流し、ドイツ人との交流試合を数多く経験できたこともラッキーであった。卓球を通じての国際交流は、まさにピンポン外交で自分にとって大きな財産となっている。
ワルドナーといえば、自分がドイツに住んでいた1985~1989年頃、世界で活躍していたトップ選手で、当時、ニッタク(卓球メーカー)社が主催するワルドナーの日本での講習会に協賛したことがある。航空チケット代を一部提供する代わりに、プログラムや記念Tシャツへの社名の露出をしてもらった。
ドイツでは、地元のスポーツクラブに所属し、ドイツ人仲間とブンデスリーガのはるか下のクライスリーガに参戦していた。1チーム6名で、12シングルスと3ダブルスの15試合で勝敗を競うが、試合開始は、夜8時頃、終わるのは11時すぎで、その後、飲み会が行なわれるので、相当きついスケジュールであった。クラブ仲間は、ポン友のルフトハンザのエンジニアの他に、自動車教習の先生、煙突掃除のマイスター、ダルムシュタット工科大学の学生とか普通なら知り合うことのないドイツ人と交流することができた。
また、当時、ブンデスリーガのフランクフルトチームの中国人プロとひょんなことで知り合いになり、一緒に練習する機会にも恵まれた。彼は、かって全中国チャンピオンになったこともあり、その後、日本の実業団で何年かプレイした後、ドイツのブンデスリーガにプロとして加わったとのことである。当時、日本のトップ選手がヨーロッパに遠征して来た時、仮想中国選手として練習の相手を務めていた。当時は、今と違って、21点先取だったが、練習試合で、15本のハンディをもらって、挑戦したことがあるが、一度も勝つことはできなかった。とにかく、ラケットを振るスピードが速く、ボールがどこに飛んでくるか予測できないので、返球しようにもできないのである。今では貴重な経験ができたことに感謝している。
本人が何らかの理由でメールアドレスを変えたのに、単に連絡をくれていないのであればいいが、何かトラブルがあったことも心配される。何十年も同じメー-ルアドレスを使っていたので、ここにきて変更するとも思われない。携帯電話に電話を試みたが、「現在使われていません」との応答。久しく、国際電話をかけていないので、かけ方が悪いのかも知れない。携帯電話の頭は、0175-で始まるが、日本からはどうやってかけるのか不確かである。ソフトバンクの携帯からかける時、010-0175-xxxx xxxxなのか、0を取るのか、携帯でも国番号がいるのか、よくわからない。コロナ関連かソフトバンクに問い合わせることもできない。どなたかヨーロッパの携帯への国際電話のかけ方を知っている人がいれば教えてほしいところである。
彼は、今、ハンガリーの片田舎に一人住まいしており、身の安否も心配なので、国際郵便のハガキを出すことにした。近況報告を求めるハガキを書き、郵便局に持って行き、一旦受理してくれたが、後で、ハンガリー宛の郵便物は、飛行機が飛んでいないので、受付できないとわかり、係員がわざわざハガキを家に戻しにきた。コロナ問題で国際郵便も機能していないことを初めて知った。国際郵便は、いつかは再開されるはずなので、それまで待つしかないも知れない。メールが一旦トラブルと全く連絡不能に陥ることをもろに感じた。
彼とは、卓球を通じて知り合った友人で、フランクフルト駐在中も同じスポーツクラブチームで卓球を楽しんだ仲である。今は、ハンガリーに住んでいるが、フランクフルトの家を人に貸していることもあり、帰国後もフランクフルトに行くたびに、フランクフルトまで来てくれ、車でいろいろなところに案内してもらっていた。我が家に泊まったこともあるが、ハンガリーの家に泊まりに行ったこともある。まさに、ポン友(朋友)ともいえる仲であるが、彼も80才近い年令になっているので、何かあったのではないかと心配な今日この頃である。
初級女子シングルスの部には、24名が参加し、我がクラブからも4名参加したが、見事、優勝と第3位(2名)を獲得し、好成績を残すことができた。自分も65才以上男子シングルスの部に参加し、惜しくも第3位に終わったが、商品券1000円をいただいた。参加人数はそんなに多くはないが、1年ぶりにラケットを握ったことを考えると、上出来と解釈すべきであろう。また、130才以上混合ダブルスの部にも参加したが、これも上位トーナメントには進めなかったが、下位トーナメントで見事第1位を獲得し、靴下の賞品をゲットした。
最近は、ラージボールだけをやっている人達も多くなっているようであるが、卓球愛好家が増えることは大変いいことだと思う。我がクラブの顧問をやっていただいている人がこのラージボールの発案者であるので、感慨深いものがある。全国的には年寄りを中心にラージの愛好者が増えているようであるが、まだまだ認知度は低いような気がする。気軽にできてボケ防止には最適なスポーツの一つであるので、可能が限り続けていきたいと思う。
1月16日の朝日新聞夕刊の三面記事に「脱ネクラ、卓球イメチェン成功」という見出しの記事が出た。見出しの文言は、さらに「80年代、テレビでいじられ。。。協会奮起」「台やユニホーム華やかに 強化も実る」「いいとも!で」とある。さらに、「中高少子化でも部員増加」「愛ちゃん人気も」と見出しが踊っていた。
記事にもあるが、昔から、卓球といえば、地味で暗いイメージが強く、タモリが「笑っていいとも!」で、「卓球は、ネクラ」と揶揄していたことは有名な話である。自分も大学時代卓球部に入っていたが、今になって当時の写真を見るとボールが白いので、見やすくするために、ユニフォームは、単色のダーク系のものがほとんどで、台の色もダークグリーンだったので、まさにそんなイメージであったことは間違いない。
新聞にある通り、タモリのおかげで、日本卓球協会は、荻村伊智朗会長の下、まさに、脱ネクラ、イメチェンの取り組みに力を入れ、台の色をスカイブルーに変えたり、ボールをオレンジ色にしたり、ユニフォームをカラフルなものに変えたり、卓球のディナーショーを企画したり、ラージボール卓球を導入したり、まさに、卓球のイメチェンに成功したものである。この取り組みを積極的に推進した人が今、我が卓球クラブの顧問をやっていただいている人である。ご本人は、もう80代になられているが、時々、クラブでいっしょに卓球を楽しんでいる。
2000年代になって、卓球人気を加速させたのは、まさに愛ちゃん人気であるが、昨今では、日本の技術レベルが飛躍的に向上し、中国との格差は急速に縮まり、東京オリンピックでのメダル獲得も決して夢物語ではない、張本智和や伊藤美誠選手のような世界に通じるスターも出現しており、テレビやマスコミでも取り上げられる機会も増えている。中高の部活でも卓球部は人気のクラブになっているという。卓球愛好家にとっては、嬉しい話である。
卓球のラリー戦はテレビで見ていても面白いが、いざやるとなるといかに難しいが実感するはずである。卓球は、「空間、時間、回転の芸術」のスポーツともいわれ、競技レベルと温泉卓球レベルの格差はとてつもなく大きい。初心者が挑戦したとすると、まず、1球か2球で終わり、ラリーを続けることはまず不可能である。年寄り向けには、回転がかかりにくいラージボールもあるので、やったことのない人は、健康のためにも、卓球に挑戦してみては?
画像は、最近のユニフォームと朝日新聞の記事(1月16日夕刊)