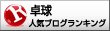武漢にいる日本人にために、ANAのチャーター便が運航されているが、帰国した人の内、症状が全く出ていない人から新型のウィルスが検出されているあたりが不気味である。ウィルスに対する特効薬はないし、我々は何に気をつけたらいいのか、何をしたらいいのか皆目わからないのが現実である。ワクチンができるのも数ヶ月かかると思われる。世界中で知恵を絞って収束に向けて取り組まないと健康被害だけでなく、経済的影響も計り知れない。現に株価が大幅にダウンしており、真っ青である。チャーター便に利用料金として、平然と当初8万円を請求するとしていたり、帰国者を相部屋に入れたり、邦人救出という緊急レベルとは考えていないような気がする。重症者を武漢に置き去りにしていることもひどい話である。対策を間違えると、オリンピックどころではなくなる恐れもあるので、日本政府の真剣な取り組みを期待したい。
武漢にいる日本人にために、ANAのチャーター便が運航されているが、帰国した人の内、症状が全く出ていない人から新型のウィルスが検出されているあたりが不気味である。ウィルスに対する特効薬はないし、我々は何に気をつけたらいいのか、何をしたらいいのか皆目わからないのが現実である。ワクチンができるのも数ヶ月かかると思われる。世界中で知恵を絞って収束に向けて取り組まないと健康被害だけでなく、経済的影響も計り知れない。現に株価が大幅にダウンしており、真っ青である。チャーター便に利用料金として、平然と当初8万円を請求するとしていたり、帰国者を相部屋に入れたり、邦人救出という緊急レベルとは考えていないような気がする。重症者を武漢に置き去りにしていることもひどい話である。対策を間違えると、オリンピックどころではなくなる恐れもあるので、日本政府の真剣な取り組みを期待したい。
タージ・マハルは、ムガル帝国の第5代皇帝のシャー・ジャハーンが、1631年に死去した妻のムムターズ・マハルのために建設した霊廟で、22年かかって、1653年に完成したとされる。左右対称のシンメトリーが印象的で、総大理石の美しい建物で、もちろん世界遺産に指定されている。アーグラという古都にあるが、2004年にニューデリーで行われた世界ハーフマラソン選手権の際、大会翌日に大会役員数名といっしょに訪ねることができた。シャー・ジャハーン王と奧さんとの純愛物語は有名だが、今は、二人仲良く並んで埋葬されているという。行きにくい場所にあるが、やはり一度は訪ねたい世界遺産である。
ニューデリーとタージ・マハル旅行記(2004年):
https://youtu.be/ddiZ5W3gVdg
本来の確定申告は、2月17日からであるが、医療費控除申請だけであれば、それ以前でも受付可能ということで、混雑を避けるために毎年1月中にやっている。朝8時40分頃には行ったが、思った以上に混んでいた。パソコンへの入力は係員にやってもらうので、楽であるが、毎年やっているのに、そのデータは蓄積されておらず、住所をはじめ、データ入力はすべて一からやり直しとなっている。前回のデータからの修正であれば、入力も早く終わるのに、いちいち入れ直しているので、時間を食うこと甚だしい。マイナンバーの入力もあるのだから、それに結びつけてデータを維持することなど簡単なはずなのに、なぜ無駄な作業を繰り返しているのであろうか?お役所仕事の典型で、改善が急務であると感じた。
ふるさと納税についても、個別にすべてのデータを打ち込む必要があり、時間ばかり食っていた。日本中でふるさと納税をやっているので、パソコン上、やっている市町村を探すだけでも時間がかかる非生産的な処理をやっている感じがした。寄附した分、地元の区や都の税金が減額されると勝手に思っているが、実際、どういう仕組みで減額されるかは、入力担当の係員もよく知らないとのことで、不明のままである。返礼品をもらうが、ふるさと納税の仕組みや納税額がどんな感じになるのか誰か詳しく教えてほしいものである。
今回は、医療費が前年度に比べると大幅に減っているので、戻ってくるお金は前年ほどではないが、それでも年金生活者にとってはありがたい話である。むしろ、医療費が減っていることに感謝すべきであろう。それでも、今回の還元額は、予想よりだいぶ多く、8万円近くあったので、ちょっとしたお年玉として、二人で山分けすることにした。ありがたい話である。
石垣島では、川平湾の美しい海の印象が強く残っているが、どこで宿泊したかは記憶にない。また、船で近くにある竹富島に渡り、そこでも1泊した。当時、乗り物は軽トラックが1台あるだけという小さな島で、民宿では、薬草料理をご馳走になったことを覚えている。石垣島からはやはり船で台湾の基隆に向かったが、台湾海峡は、大荒れで有名なところのようで、この船旅は大揺れの連続で、荷物が船室の中で、揺れるたびに移動する始末で、ほとんど全員が船酔い状態であった。
台湾の基隆に上陸したが、これが人生最初の外国訪問である。今では、102か国を訪問しているが、台湾はその1号なので、印象深い。台北では、安くあげるためにYMCAのホテルに宿泊し、観光としては故宮博物館、龍山寺、中正紀念堂等を見て回った後、新北投温泉にも宿泊した。そこから、有名な日月潭の湖にも足を運んだ。その後は、列車に乗って、彰化→台中→台南→高雄へと移動したが、その列車内での中国語による車内アナウンスの美しい響きにうっとりしたことを鮮明に覚えている。これがその後、鄧麗君(テレサ・テン)による美しい中国語の魅力に取りつかれた原点である。日本語と違って、中国語の流れるような旋律の響きの美しさは世界一であると感じた。
台湾滞在中に、日本の歌謡曲が中国語で歌われ、ヒットしていることを知った。そこで、テレサ・テンのことを知り、中国名の鄧麗君の歌うレコードやカセットテープもいっぱい売られていた。いくつかを買って帰ったが、彼女が日本でデビューする4年も前のことである。その時からのオールドファンはあまりいないかも知れない。テレサ・テンの他では、「一路順風」(花笠道中)と「說聲對不起」(女のみち)が流行っていた。「女のみち」は、今でも中国語で歌える唯一の曲である。
高雄から高速列車で台北に戻り、そこから香港にノースウェスト航空機で移動したが、これが2回目の飛行機搭乗で、香港が2番目の外国となった。香港では、ビクトリアピークはじめ定番の市内観光とマカオまで足をのばした。香港から那覇までは、初めて日の丸の飛行機に乗り、那覇から羽田行の帰国便に乗ったのは、よど号ハイジャック事件の翌々日であったので、緊張したことを覚えている。あれから、もう50年、時に流れを痛感する今日この頃である。
特に、キャッシュレス決済については、目から鱗情報も多く、まさに「にわか」知識がついた。
キャッシュレス決済といっても、
①プリペイド(交通系、流通系の電子マネー)
②銀行系、国際ブランド系のデビットカード
③モバイルウォレット(QRコード、バーコードを使うペイペイ等の何とかペイ)
④クレジットカードという4種類がある。
驚いたのは、世界のキャッシュレス化普及率で、2016年データで世界一は、韓国の96.4%、次いで、イギリスが68.7%、オーストラリアが59.1%、シンガポールが58.8%と続くが、中国でさえ、2015年データで60%となっている。一方、日本は、19.8%にとどまっている。韓国はクレジットカード、スウェーデンは、デビットカードが主流とか決済方法は異なっているのが現状のようである。韓国の96.4%には驚いたが、クイズによれば、1000円以上のキャッシュレス決済をすれば、宝くじに参加できるというらしい。なるほど普及するのも頷ける。韓国に負けているのは悔しい思いである。
日本は、この分野では世界から遥かに遅れている感があるが、ここにきて日本政府主導でキャッシュレス化が一気に推進されつつある。スマホの普及に伴い、ペイペイ、ラインペイ、楽天ペイなどがポイント還元を武器にどんどん普及しつつあるし、小売店でも政府肝いりでキャッシュレス5%還元の張り紙が出ているお店も急速に増えている気がする。自分自身、従来のクレジットカードや電子マネーに加え、ペイペイと楽天ペイを利用しており、現金で買物する機会が極端に減ってきた。現金を使うのは、路上や安売りの野菜販売くらいで、スーパー、コンビニ、レストラン、床屋までキャッシュレス決済となっている。番組によると、お年玉、お賽銭までキャッシュレスになっているところもあるようである。しかし、スマホを持っていない年寄りも多いので、買い物難民があふれそうな気もする。レジで小銭を出して、もたもたしているおばちゃんを見てイライラすることも多いので、レジが早くなるキャッシュレスがもっと普及し、早く後進国から脱却してほしいものである。
もう一つは、1/4にテレビ朝日で放映された「博士ちゃん~仏像博士12歳—初詣にご利益!国宝&珍仏像」で紹介された有名な仏像の内、滋賀県の長浜市にある正妙寺にある千手千足観音立像が上野にある「びわ湖長浜KANNON HOUSE」で3月15日まで特別に展示されているとの情報を得たので、覗いてみることにした。この仏像は、他に例のない「千本の足」を持つ観音像で、そのムカデのような姿はひと際目を引く。忿怒相で眉目をいからせ、口を開き、額には縦に第三眼を刻む。天冠台上に九つの小面が横に並び、中央には仏面が一段高く載る。何とも異様な姿で、江戸時代のものであるが、詳しくはよくわからないようである。こちらも入場無料であったが、展示品はこの仏像のみであった。こちらは写真撮影OKであったので、しっかりとその姿をカメラにおさめた。まさに、知る人ぞ知る稀有な仏像であった。仏像博士ちゃんに感謝したい。
写真は、大日如来坐像(運慶)と千手千足観音立像



番組の中で、民放共同プロジェクトとして、桑田佳祐が作詞作曲した応援ソング「SMILE~晴れ渡る空のように~」が初披露された。オリンピックに向けて、この曲が頻繁にテレビで流れることになると思うが、間違いなくヒットの予感がする。一方、NHKのテーマソングは、二つあって、一つはNHK2020ソング「カイト」(嵐)、もう一つは「パプリカ」(foorin)で「2020応援ソング」かつ「東京2020公認プログラム」と銘打たれているが、ともに米津玄師の作詞・作曲である。これとは別に新しいテーマソングが出るのであろうか?NHKの中継番組の中では、どの曲がどのように流れるのであろうか?NHKと民放5社の視聴率争いも面白そうだが、同じ映像が流れる民放5社の視聴率争いにも興味が沸く。
過去のNHKテーマソングは、「サザンカ」「Hero」「風が吹いている」「BLESS」「GIFT」「栄光の架橋」など名曲ばかりである。オリンピック期間中頻繁に耳にするので、そのメロディが焼き付いてしまうほどである。あと半年というところまで来たが、楽しみが徐々に増してきている。
画像は、お台場のライトアップ
一緒にやろう2020大発表スペシャル: https://youtu.be/7B55nYfuHWA
カイト: https://youtu.be/ETLT0WXFX1E
パプリカ: https://youtu.be/MFnpnDI3oQQ
この人は、お金があれば何でもできると勘違いしているのではないかと思うほど、月旅行一番乗りをお金で買ったり、とにかく話題作りで自分が注目されることにのみ生きがいを感じているようである。今回のお見合い相手募集もいかにも彼らしいが、応募した愚かな女性が2万8000人もいるということで、ビックリ。お金に釣られる女性がこんなにもいるとは悲しい話である。マスコミに取り上げられ、行く末どうなるかわかっているのであろうか?見事、合格した女性が幸せな人生を送ることなどあり得ないとみる。あの捨てられた剛力彩芽も馬鹿だったと思うが、早くに別れてよかったと思うべきであろう。どんな人が当選するのか見ものであるが、応募するお金目当ての女性を大体的に取り上げるであろうマスコミもマスコミである。嫌な世の中になったものである。
会社の管理職・OB向けの講演会が時々行われているが、会場が家から自転車で5-6分のところにあり、しかも無料なので、よく出掛ける。1月22日は、元NHKヨーロッパ総局長でもあった磯村尚徳氏の講演会で、演題は「日本人が考えるほどヨーロッパはヤバではない」であった。久し振りにお顔を拝見したが、とても90歳とは見えないほどお元気で、お話しぶりも全く年を感じさせない印象であった。
イギリスのEU離脱問題で揺れているヨーロッパであるが、講演の主なポイントは下記のようなものであった。
・イギリスは、かっての大英帝国のほどの影響力はもうない。
・今のヨーロッパを引っ張ているのは、3人の女性
①ドイツのフォンデアライエン女史(初のEUの女性欧州委員長)
②フランスのラガルド欧州中央銀行総裁
③デンマークのベステアー欧州委員(GAFAの天敵)
ドイツとフランスが引っ張るEUは極めて強力であるという。
・ドイツの強みは、
①国歌にもなっている「世界に冠たるドイツ」は健在で、財政黒字
②ドイツの製造業(モノづくり)は卓越
③人の養成が上手(難民も多数受入れ、熟練工育成)
④政治家が優秀(大連立、大人の政治)
⑤1963年の仏独協力条約(ドゴールとアデナウアー間)-- 800万人の若者の交流・共通の歴史教科書作成等や1969年エアバスの開発 ⇒ EUの土台
⑥生活の質が高い(休暇もしっかり取る、皆5時には帰宅)---自分の経験からも、ドイツは日本より遥かに進んでいるとの実感を持っている。就業環境などは雲泥の差である。
フランスの強みは、
①地の利がいい(農産物に恵まれている)
②教育が素晴らしい---幼稚園から哲学を教えている(物事に疑問を持つこと)。読み書きソロバン(国語、算数)及び哲学重視
③文化(最上の安全保障)だけでなく、外交的手腕がある---国連の常任理事国になっている
強みのある仏・独率いるEUは強い。日本はアングロサクソンになびいてきたが、1864~1868年の幕末には、フランスは日本の近代化に大きな影響を与えた。横須賀に作った造船所もその一つである。日本の英語教育の在り方にも問題を提起していた。
結論としては、EUを離脱しようとしているイギリスは、アングロサクソンの呪縛にかかっており、フランス・ドイツを中心とするヨーロッパは、まさに、日本人が考えるほどヤバではなく、EUの底力を見誤るとこれからの世界は読めないということであった。久し振りに世界の政治動向の話を聞いたが、大変勉強になった。
1月16日の朝日新聞夕刊の三面記事に「脱ネクラ、卓球イメチェン成功」という見出しの記事が出た。見出しの文言は、さらに「80年代、テレビでいじられ。。。協会奮起」「台やユニホーム華やかに 強化も実る」「いいとも!で」とある。さらに、「中高少子化でも部員増加」「愛ちゃん人気も」と見出しが踊っていた。
記事にもあるが、昔から、卓球といえば、地味で暗いイメージが強く、タモリが「笑っていいとも!」で、「卓球は、ネクラ」と揶揄していたことは有名な話である。自分も大学時代卓球部に入っていたが、今になって当時の写真を見るとボールが白いので、見やすくするために、ユニフォームは、単色のダーク系のものがほとんどで、台の色もダークグリーンだったので、まさにそんなイメージであったことは間違いない。
新聞にある通り、タモリのおかげで、日本卓球協会は、荻村伊智朗会長の下、まさに、脱ネクラ、イメチェンの取り組みに力を入れ、台の色をスカイブルーに変えたり、ボールをオレンジ色にしたり、ユニフォームをカラフルなものに変えたり、卓球のディナーショーを企画したり、ラージボール卓球を導入したり、まさに、卓球のイメチェンに成功したものである。この取り組みを積極的に推進した人が今、我が卓球クラブの顧問をやっていただいている人である。ご本人は、もう80代になられているが、時々、クラブでいっしょに卓球を楽しんでいる。
2000年代になって、卓球人気を加速させたのは、まさに愛ちゃん人気であるが、昨今では、日本の技術レベルが飛躍的に向上し、中国との格差は急速に縮まり、東京オリンピックでのメダル獲得も決して夢物語ではない、張本智和や伊藤美誠選手のような世界に通じるスターも出現しており、テレビやマスコミでも取り上げられる機会も増えている。中高の部活でも卓球部は人気のクラブになっているという。卓球愛好家にとっては、嬉しい話である。
卓球のラリー戦はテレビで見ていても面白いが、いざやるとなるといかに難しいが実感するはずである。卓球は、「空間、時間、回転の芸術」のスポーツともいわれ、競技レベルと温泉卓球レベルの格差はとてつもなく大きい。初心者が挑戦したとすると、まず、1球か2球で終わり、ラリーを続けることはまず不可能である。年寄り向けには、回転がかかりにくいラージボールもあるので、やったことのない人は、健康のためにも、卓球に挑戦してみては?
画像は、最近のユニフォームと朝日新聞の記事(1月16日夕刊)