●ジョリス=カルル・ユイスマンス『大伽藍』⑤
プロン神父との会話の中でデュルタルは「伽藍の魂」というものに思いをめぐらす。今度は大伽藍の建築物としての側面ではなく、マリア信仰の側面について、現状はどうなっているかについての議論である。「神の加護の下に人間が伽藍を建立した時の、まさにその時の伽藍の魂」は、今どうなっているのか。
このことについてデュルタルは、パリの大聖堂を初めとして次々と、シャルトル以外の大聖堂の現状を批判していく。デュルタルはその原因を明確に示しているわけではないが、パリ大聖堂におけるミサや聖体拝領、礼拝式や聖歌などの宗教的日課の堕落ぶりを指摘し、「伽藍の魂」が失われてしまっていることを嘆いてみせる。
パリの場合には「図々しい観光客をやたらと出入りさせている」こともその一因とされているが、本当の原因は何なのだろうか。パリだけでなく、アミアンやランの大聖堂についても、デュルタルは魂の喪失を言うのである。しかしシャルトルだけは例外である。
「でも、シャルトルほどの聖堂はどこにもありはしないのです。シャルトルの御堂でほど充実した祈りのできる伽藍はどこにも絶対にありはしないのです。」
一体なぜなのか。実はその理由もまた、前にデュルタルが言っていた聖母マリアの偏在にこそある。デュルタルは具体的に言う。
「シャルトル以外の御堂では、マリアさまのお顔を拝むのに次の間でさんざん待たせられるありさまなのですからね。しかも待たされたあげくが、今日はこれまで、ということさえ稀ではありません。ところがシャルトルの御堂では、マリアさまはそのままのお姿ですぐにもお顔を見せて下さいます。」
デュルタルは続いて、シャルトル大聖堂にある二つの黒い聖母像を、奇跡のようなマリア像と褒め称えるが、「伽藍の魂」とは町のブルジョア女や教区の財産管理委員どもの「魂」ではないと言い、次のように結論づける。
「シャルトルの魂は、修道女たちや近在の農婦たち、修道院寄宿学校や神学校の生徒たち、わけても、聖母の柱に接吻して黒いマリアの前に跪く、あの聖歌隊の少年たちにこそ、命を吹き込まれているのです。」
こうした庶民によるマリア信仰は、中世ゴシック大聖堂の原点にあったものだということを、私は酒井健に教えられたが、そのような信仰の主体が生き残っているのは、シャルトル大聖堂だけだというのである。ユイスマンスの高踏的デカダン趣味から、一種のポピュリズムへの回帰の姿をここにはっきりと見ることができる。
しかし私にとって理解できないのは、ユイスマンスのこのような信仰のありかたである。崇高美の極致とも言うべき建築物としてのゴシック大聖堂への偏愛と、母性原理への回帰と言うべき聖母マリアへの帰依とは、矛盾するものではないのだろうか。
だからその疑問はユイスマンスの信仰の姿に対してだけではなく、聖母マリアを戴くほとんどのゴシック大聖堂のあり方にも向けられる性質のものである。あの荘厳で、厳めしく、無骨とも言えるゴシック大聖堂が、聖母マリアに捧げられるということに矛盾はないのであろうか。
私はエドマンド・バークの議論を思い出すのである。崇高と美の観念のよって来たるところの二つの正反対の要素、男性的原理と女性的原理に関しての議論である。
言うまでもなく、崇高は男性的原理を背景としているのに対して、美は女性的原理を背景としているのである。もう少し詳しく思い出してみよう。












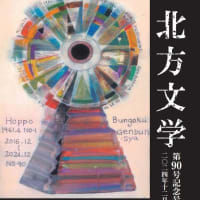
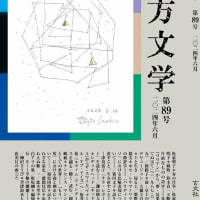
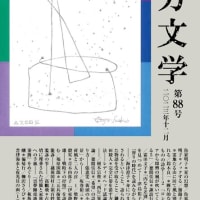

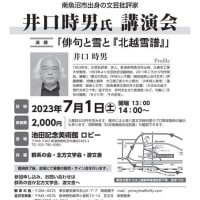

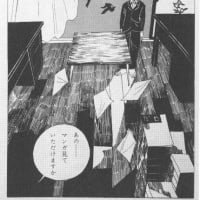
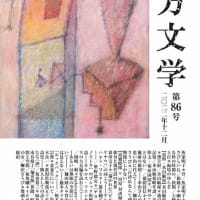
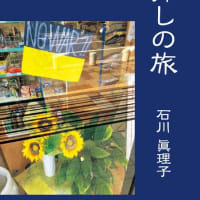
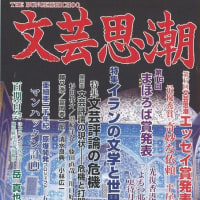






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます