読んだ順に書いていくとすれば、次はアベ・プレヴォの『マノン・レスコー』ということになる。この魔性の女を描いた古典的名作を私はほとんど評価できない。マノンにどんなにひどい目に遭わされても、決定的な浮気をされても、それでも愛を貫くデ・グリューという男の気持ちが私には理解できないし、いわゆるFemme fataleというものを登場させた最初の小説というが、それ自体が虚構的な概念であって、マノンは私にとって存在感に乏しい。
18世紀フランスの小説なら、サディスムの元祖マルキ・ド・サドの作品や、ラクロのすけこまし小説『危険な関係』のほうがずっといい。プレヴォには〈愛〉に対する全幅の信頼があるが、サドやラクロにはそれがないからである。フランスの小説にはその方が似合っている。ということで『マノン・レスコー』はパスすることにする。
次はバルザックの『従妹ベット』である。『ゴリオ爺さん』に比べてこちらは倍くらい長い小説で、じっくりとバルザックらしさを味わうことのできる傑作と思う。
小説は町人上がりのクルヴェル大尉が、この小説の主人公ユロ男爵の家に夫人を訪ねていく場面から始まる。なんとユロ家の窮乏をネタに夫人との関係を迫りに来たのである。フランスの小説にはこのようなことはありふれたことで、貴族が愛人を囲うのは当たり前だし、それだけでなく貴族の奥方が公然と恋人を持つことも当たり前に行われていたらしい。
『ゴリオ爺さん』の二人娘もちゃんと愛人を持っていたし、ラスチニャックが社交界に接近するのも、貴族の奥方に取り入ってその愛人となり、引き立ててもらうためなのであった。そんなことが当然のことのように書かれているのを読むと、当時のフランス社会の恐ろしさを感じるのである。
とにかくクルヴェルはユロ男爵夫人アドリーヌに言い寄るのであった。しかも彼女は自分の一人娘をその息子に嫁がせた相手であって、親戚同士なのである。ほとんど狂っているではないか。後で分かることだがこの小説の主要な登場人物は、皆狂っているとしか思えないのだ。
クルヴェルは「下ぶくれの赤ら顔」で太鼓腹の醜い男として描かれている。では戯画化された存在感の薄い人物かというとそうでもない。フローベールのルウルウなどよりかは、よほど存在感を発揮する人物なのである。
クルヴェルが親戚の夫人をかどわかそうなどという気持ちを起こしたのも、ユロ男爵の放埒な行いによっている。クルヴェルはユロ男爵に愛人を盗られた復讐の念からそうするのであり、ここからクルヴェルとユロ男爵の女性をめぐる戦いが始まる。読者は最初の場面からこの小説は品行正しい物語ではなく、女色をめぐる戦いの物語なのだと了解する。表面的にはとても卑俗なお話なのだ。
うっかりしていたが、この小説の主人公を、私はユロ男爵だと言った。『従妹ベット』だからベット、つまりアドリーヌの従妹リスベットが主人公なのではないかといわれるかも知れないが、『ゴリオ爺さん』と同様、リスベットはこの小説の主人公としての重量感を示していない。
リスベットはユロ男爵の家で暮らしているが、アドリーヌの美貌に対して醜い風貌の女で、昔からアドリーヌとは対照的な扱いを受けてきた。リスベットは嫉妬深い中年女性なのである。バルザック自身が「嫉妬がこの女のeccsentricityにみちた性格の基準を示している」と書いているくらいである。
リスベットには愛する男がいるが、その男シタインボックが、アドリーヌの娘オルタンスと婚約するに及んで、リスベットのユロ男爵一家に対する復讐が始まるのである。
『従妹ベット』の少なくとも前半のプロットを動かしているのは、間違いなくリスベットの嫉妬であって、彼女の名がタイトルになっているのは理由のないことではない。しかし、リスベットは陰険で、二枚舌で、ずるがしこい女であって、読者は彼女の復讐心に同調することができないのである。
オノレ・ド・バルザック『従妹ベット』(1974、東京創元社「バルザック全集」第19巻)水野亮訳












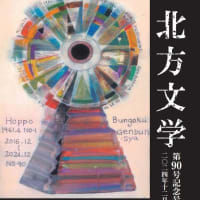
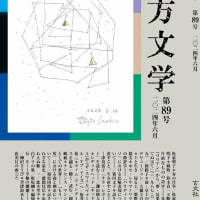
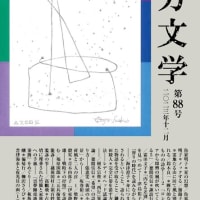

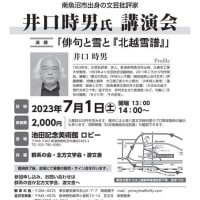

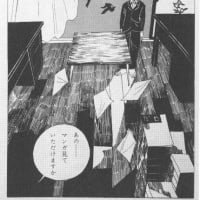
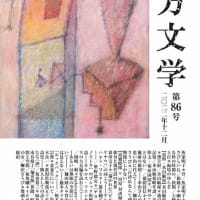
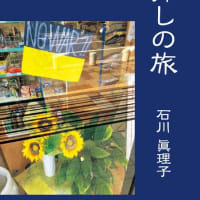
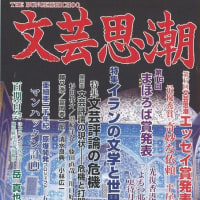






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます