『ねじの回転』では本当に幽霊が出たのかそうではなかったのかについての解答は与えられていないし、ヘンリー・ジェイムズはどちらともとれるようにこそ書いたのに違いない。『ねじの回転』の原題はThe Turn of the Screwであり、直訳すれば「ねじの回転」だが、普通の日本語に訳せば「ひとひねり」ということである。
つまりジェイムズはこれまでの恐怖小説に「ひとひねり」を加えたかったのであって、超常現象があったのかなかったのか読者が読んでも分からない小説を目指したのだ。ジェイムズはそのように書いても「これだけ怖いのが書ける」と『ねじの回転』に自信を持っていたはずだ。
ホッグの『悪の誘惑』も編者からみれば悪魔など存在しないのであり、主人公からみれば悪魔に唆されて数々の悪事を働いてしまうという二重の構造になっている。そこにこそこの作品の新しさがある。
悪魔が登場するゴシック小説はたくさんあるが、殆どが悪魔を実体化していて底が割れている。『悪の誘惑』の第1部が真実で悪魔など存在しないとすれば、さらには第2部の主人公の告白が妄想であったとするならば、そこにこそ本当の“怖さ”があるのだと言うことも出来る。
逆に第2部が真実で第1部が表面の現象だけをみているのだとしても、第2部でホッグがロバートの手記を通して、悪魔を迫真の筆力で描いていること、悪魔に憑かれる事の恐怖を臨場感をもって描き切っていることを否定することは出来ない。
悪魔が妄想だとしても、妄想こそが真の恐怖を生む。『ねじの回転』についても同じ事が言えるだろう。幽霊と悪魔の違いはあれ。
ところで、悪魔あるいは悪魔の妄想はどこから生まれてくるのか? それが神への狂信からであることをこの小説は暴き出している。『悪の誘惑』の文学的価値はそこにこそあると私は思っている。最後にそのことに触れなければならない。
つまりジェイムズはこれまでの恐怖小説に「ひとひねり」を加えたかったのであって、超常現象があったのかなかったのか読者が読んでも分からない小説を目指したのだ。ジェイムズはそのように書いても「これだけ怖いのが書ける」と『ねじの回転』に自信を持っていたはずだ。
ホッグの『悪の誘惑』も編者からみれば悪魔など存在しないのであり、主人公からみれば悪魔に唆されて数々の悪事を働いてしまうという二重の構造になっている。そこにこそこの作品の新しさがある。
悪魔が登場するゴシック小説はたくさんあるが、殆どが悪魔を実体化していて底が割れている。『悪の誘惑』の第1部が真実で悪魔など存在しないとすれば、さらには第2部の主人公の告白が妄想であったとするならば、そこにこそ本当の“怖さ”があるのだと言うことも出来る。
逆に第2部が真実で第1部が表面の現象だけをみているのだとしても、第2部でホッグがロバートの手記を通して、悪魔を迫真の筆力で描いていること、悪魔に憑かれる事の恐怖を臨場感をもって描き切っていることを否定することは出来ない。
悪魔が妄想だとしても、妄想こそが真の恐怖を生む。『ねじの回転』についても同じ事が言えるだろう。幽霊と悪魔の違いはあれ。
ところで、悪魔あるいは悪魔の妄想はどこから生まれてくるのか? それが神への狂信からであることをこの小説は暴き出している。『悪の誘惑』の文学的価値はそこにこそあると私は思っている。最後にそのことに触れなければならない。












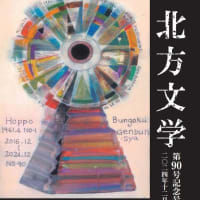
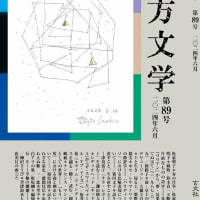
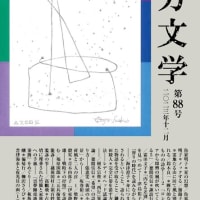

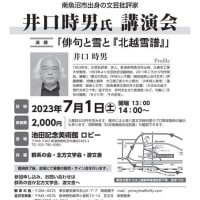

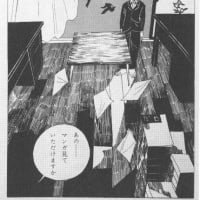
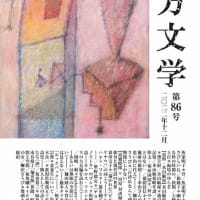
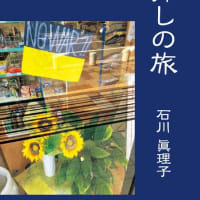
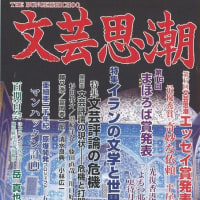






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます