『ゴリオ爺さん』がバルザックの代表作と言われ、一般によく読まれているのはやはり、ゴリオの悲劇的な臨終の場面があるからだろう。死の床でゴリオはアナスタジーとデルフィーヌの二人の娘が来てくれることを最後の望みとしているが、二人とも財産的な危機に瀕していて、考えることはお金のことばかり、最後にゴリオを看取るのはラスチニャックとその友人のピアンションの二人に過ぎない。
ラスチニャックとピアンションの献身的な看護は、二人の娘の冷酷さと強い対比をなしていて、読者はゴリオの最期に涙するのである。しかし、バルザックはこの場面をそれほど悲劇的なものとして描いているわけではない。ピアンションは死に臨んでも娘達のことを心配するゴリオを見て次のように言うが、自制の効いた言葉である。
「『デルフィーヌ! わしのかわいいデルフィーヌ! ナジー!』などと聞かされると、こん畜生と思いながらもつい涙がでちまったぜ。ほんとに泣けて泣けてしようがなかったよ」
バルザックはむしろゴリオの臨終の場面を、喜劇的に描いていると言ってもよい。なにせ「人間喜劇」の中の一編なのだから。ゴリオは娘たちを溺愛した罰によって死ぬのである。ゴリオの臨終の言葉……。
「娘たちを愛しすぎた罪は、十分に贖ったじゃありませんか。あの子たちはわしの愛情に仇をなし、拷問人のように、鉄鉗(やっとこ)で挟んでさいなんだではございませんか。ところが父親っていうものは、じつに愚かなもんですなあ! 可愛くてたまらずに、またぞろ娘のところに足が向いてしまいましたわい。ちょうど賭博好きが賭場を見限れないのと同じこった。娘たちはわしにとって悪い道楽であり、色女であり、つまりはすべてなんでしたわい!」
結局ゴリオは自業自得で死ぬのである。それにしてもここでゴリオが、娘への溺愛を賭博狂いや女道楽と同類のものと考えているのは興味深い。つまりゴリオはバルタザール・クラウスやユロ男爵と同類なのである。
バルタザールの死もユロ男爵の死も、家族を犠牲にしてでも好き勝手なことをやって人生を全うした末の死であり、少しも悲劇的なところがないように、ゴリオの死も悲劇的ではない。それを悲劇的と考えて涙するのは、単なる感傷に過ぎない。
しかし、二人の娘に対するラスチニャックやピアンションの怒りはまた別の問題である。ラスチニャックは冷酷な娘たちを前にして、次のように内心では思うのである。
「世間じゃただけち臭い罪悪しか行われていない。考えてみればヴォートランのほうがずっと偉いや」
田舎からパリにでてきたラスチニャックは、ゴリオの死を通してパリの社会を学んでいく。ゴリオの娘たちの仕打ちに対する怒りも、ラスチニャックがこれからパリの社会に出ていくための世間智のひとつなのだ。もちろんヴォートランとのいきさつもまた、ラスチニャックが世間智を得ていくための通過儀礼なのだ。
だから『ゴリオ爺さん』の主人公は決してゴリオではなく、ヴォートランでもなく、ラスチニャックに違いない。彼の最期の言葉がそのことを証している。
「さあ、これからはパリとおれの一騎打ちだ」
娘にひどい目に遭うゴリオの設定はシェイクスピアの『リア王』からきているというが、私は『リア王』を読んでいないのでそれについて何か言うことはできない。ただしシェイクスピアの四大悲劇に数えられる『リア王』の悲劇性と、『ゴリオ爺さん』の喜劇性ははっきりと対称的なものであるだろう。そして『従妹ベット』も喜劇的な作品なのであった。












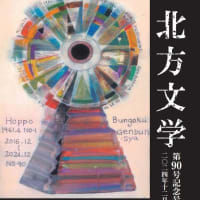
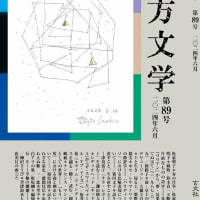
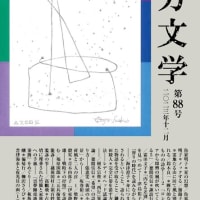

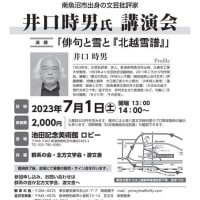

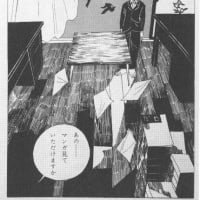
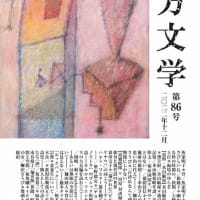
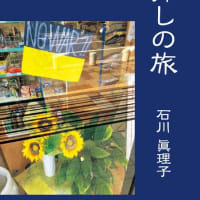
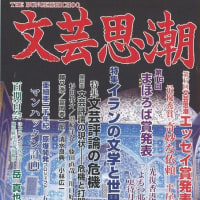






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます