●酒井健『ゴシックとは何か』⑨

ノートル=ダムからエッフェル塔を遠望
こうしてゴシック・リヴァイヴァルは近代から現代へとつながっていく。ゴシックの系譜をエッフェル塔まで視野に入れた時、何が見えてくるのか、そのことを酒井は書いていない。
ヴィオレ・ル・デュックの極めて近代的な考え方についても、それほど高い評価を与えておらず、酒井の評価の軸はやはり、ヨーロッパ中世へと向かい、ゴシックの精神の中に庶民的で自由、柔軟で懐の深い宗教性を見出してそれを高く評価する。デュックは酒井にとって十分に反近代的ではなかったのである。
ならば、ゴシック・リヴァイヴァルがカトリック・リヴァイヴァルとしての側面を見せる時、酒井はそれを最大限に評価することになる。シャトーブリアンの『キリスト教精髄』への高い評価、さらにはカトリックへと回心したJ・K・ユイスマンスの『大伽藍』に対して「カトリック・リヴァイヴァルの宝と言ってよい文学表現」と、手放しの評価を与えていることもその例証となる。
しかし酒井のように近代への否定が中世への評価につながっていくケースはそれほど独創的なものではない。ゴシック・リヴァイヴァルを先導したとされるゴシック・ロマンスの担い手達も、近代の合理主義的精神の否定の末に、中世の理想化に至ったようにも見える。
あるいは近代合理主義批判は現在の日本にあっても猖獗を極めていて、それらは理想の過去を縄文時代に求めたり、神代に求めたり、あるいは江戸時代に求めたり、明治の初期に求めたりと、忙しいこと極まりない。
彼らが忘れているのは理想の過去というもの自体が、近代の意識によって作り出されたものに過ぎないという認識である。人類の歴史上、人々が豊かで、平和で、自由に、創造的に暮らした時代などというものはあり得ない。人々がキリスト教の大聖堂の下で、自由で豊かに暮らした中世などというものがあり得ないのと同じである。
私がゴシックの歴史の中で気になるのは、キリスト教による異端審問とそれに続く魔女狩りの時代のことである。それらはゴシックの時代とほぼ重なっていて、キリスト教の暗黒の側面を代表している。酒井は一切そのことに触れようとしない。
ならばジュール・ミシュレの『魔女』を読んでみる必要があるだろう。そのことへの考察は『魔女』を読むまで保留としておくが、酒井がゴシックの精神を理想とするあまり、キリスト教の暗部を見過ごしているのは、看過できない誤りだと思う。

金網がなければ最高のアングル
ところで最後にパリのノートル=ダム大聖堂のキマイラ達のことに立ち返る約束であった。
私はシャルル・メリヨンの〈吸血鬼〉という作品に出会った時に、広くは「思索者le penseur」と呼ばれているこの像を初めとする怪物達の像は、古くからそこにあったものだと思っていた。だからそれは中世から近代に至る800~900年もの間、パリの歴史を眺め続けてきたものと思い込んでいたのである。
しかし実際にはそれらの像は、1850年頃にヴィオレ・ル・デュックによって復元された(と言うよりも再現された)ものであって、メリヨンが〈吸血鬼〉を描いたのが1853年であるから、まだできて間もない頃彼はノートル=ダムの塔に登って、それを描いたということになる。
そもそもなぜ一般には「思索者」と呼ばれていた像に「吸血鬼vampire」などというタイトルを付けたのか? メリヨンの銅版画をパトグラフィーの視点から読み解いた、気谷誠の『風景画の病跡学』によれば、それはメリヨンがユゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』(1831)の女主人公エスメラルダに邪な欲望を抱き、彼女を破滅させてしまう司教補佐クロード・フロロのイメージを仮託しているからであるからという。
しかし、〈吸血鬼〉には薄汚れた欲望に身を焦がす邪悪なイメージは感じられないし、実物もそんなイメージを持ってはいない。まさに「思索者」という呼称通り、パリの街を見下ろしながら物思いにふける異形の悪魔というイメージなのだ。
メリヨンが数ある怪物の中からこの像を選んだのも、怪物達の中でこの像だけが獣性から逃れて、精神の領域へと踏み込んでいるからだと思われる。またメリヨンという銅版画家は、もっぱらパリをモチーフとした風景画を描いた人であるが、どの作品を見てもそこにメリヨン自身の精神の投影を感じないわけにはいかない。ピエール・ジャン・ジューヴが『ボードレールの墓』で次のようにいっているその言葉は、まったくその通りだと言わざるを得ない。
「メリヨンはパリである。彼はパリを通して自らの歴史を綴る。」
ならば「思索者」だけでなく、その背景に広がるパリの眺望も、乱れ飛ぶカラス達もまた、メリヨン自身なのである。この〈吸血鬼〉という作品は深い自省のうちに世界を開示する作品なのである。
同時代にメリヨンを正しく評価したのは、シャルル・ボードレールただ一人であった。ボードレールはめまぐるしく変貌していくパリの風景を目の前にして、それを単に否定するのではなく、そこに〝近代〟の表れを見てとって、積極的に詩のテーマとした。彼にはメリヨンの仕事がよく分かっていたのである。
こうしてメリヨンの〈吸血鬼〉は近代の思索者としての姿を現す。同時にモデルとなったデュックの像もまた、多くの怪物達の中でもっとも近代的な精神を体現するものとして生まれ変わるだろう。
メリヨンもまたゴシック・リヴァイヴァルの潮流の中で生き、かつ描いた人であった。ノートル=ダム大聖堂もよく描いたが、セーヌ川から後陣を眺望した作品を一枚掲げておく。後陣の尖塔が見当たらないところを見ると、デュックによる修復以前の姿を止めようとしたのかも知れない。

シャルル・メリヨン〈ノートル・ダム寺院の後陣〉1854年頃
気谷誠『風景画の病跡学』(1992,平凡社)
ピエール・ジャン・ジューヴ『ボードレールの墓』(1976、せりか書房)道躰章弘訳
(この項おわり)












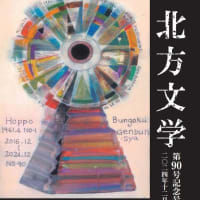
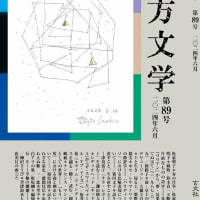
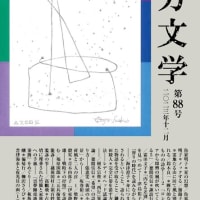

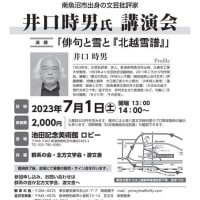

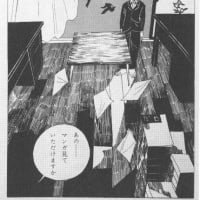
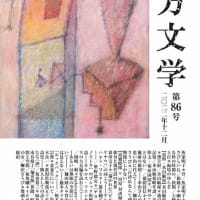
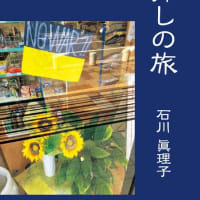
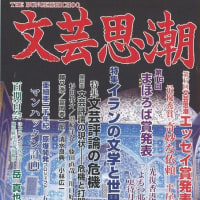






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます