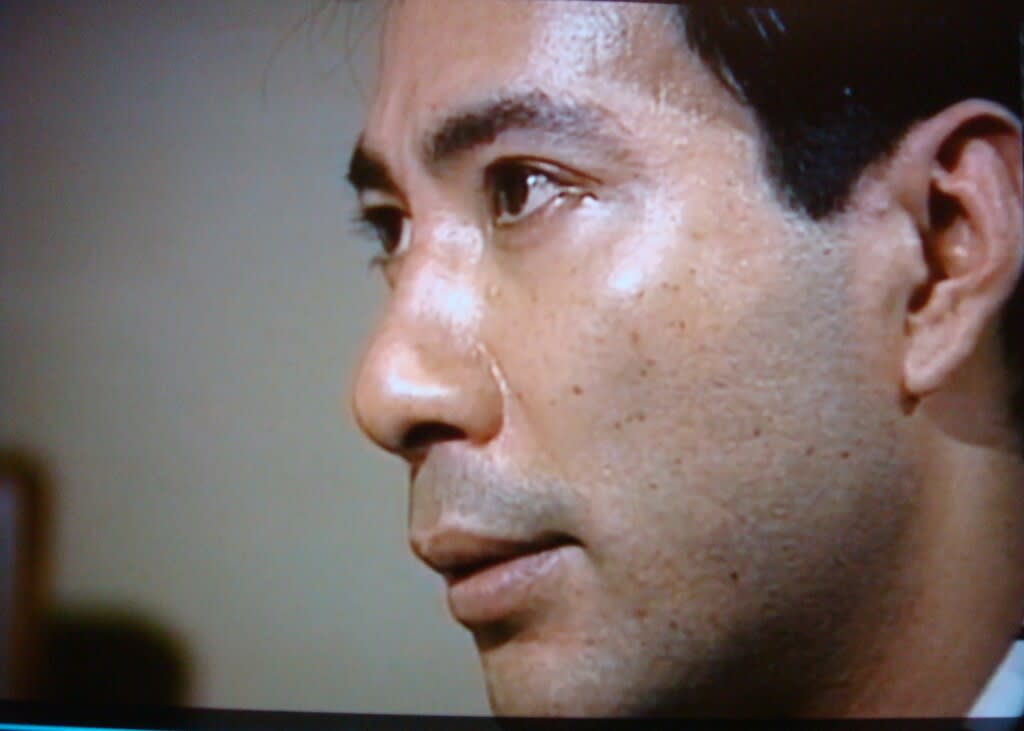「序の舞」を四番観た。
● 能 「姨 捨」 シテ(里女 老女の霊) 梅若 紀彰 (4月9日 横浜能楽堂)
笛:松田 弘之 小鼓:大倉 源次郎 大鼓:國川 純 太鼓:前川 光長
(年老いて山に捨てられた女。中秋の名月が限りなくその光を放つ中、老女の霊が現れ若き日を偲んで舞う。)
●能 「采女」 シテ(采女) 坂真太郎 (4月10日 矢来能楽堂)
笛:一噌 隆之 小鼓:鵜沢 洋太郎 大鼓:原岡 一之
(かつて天皇の情けを受けた采女。だがはかなくも、その心変わりを恨み猿沢の池に入水する。弔う僧の前に幽霊となって現れ、天皇への想いを込めて舞う。)
●能 「檜垣」 シテ(老女・檜垣女) 大槻 文蔵 (5月7日 横浜能楽堂)
笛:杉 市和 小鼓:大倉 源次郎 大鼓:亀井 忠雄
(その老婆、檜垣という名の女は若いころ美貌を誇った白拍子だった。それゆえに多くの人々を惑わした罪で成仏できずにいる。その老残を晒し、昔を偲び弱々しく舞い、僧に救いを求める。)
●能「杜若」 シテ(杜若の精) 中所 宜夫 (5月8日 矢来能楽堂)
笛:杉 信太朗 小鼓:大倉 源次郎 大鼓:澤田 晃良 太鼓:佃 良勝
(杜若の精が、在原業平の形見の初冠と二条后の形見の唐衣を着し、昔を偲び、舞う。)
いずれの曲目も在りし日の罪科で成仏できず、冥界に漂う霊魂が、容を現し舞を舞うというもの。
それぞれの背景が異なるゆえに、きまり切った「序の舞」を舞手がどのように表現するのかとても楽しみだった。
立ち姿で、観客に主人公の「老い」を感じさせるには、演者から「老い」相応の風姿を観客が感じ取れるオーラのようなものが無いと面白くない。
老人の仕草を真似ただけではダメなのだ。「・・もどき」ではなく「そうなんだ」と思える主人公。
「檜垣」は良かった。また老女ではないけれど「采女」も良かった。