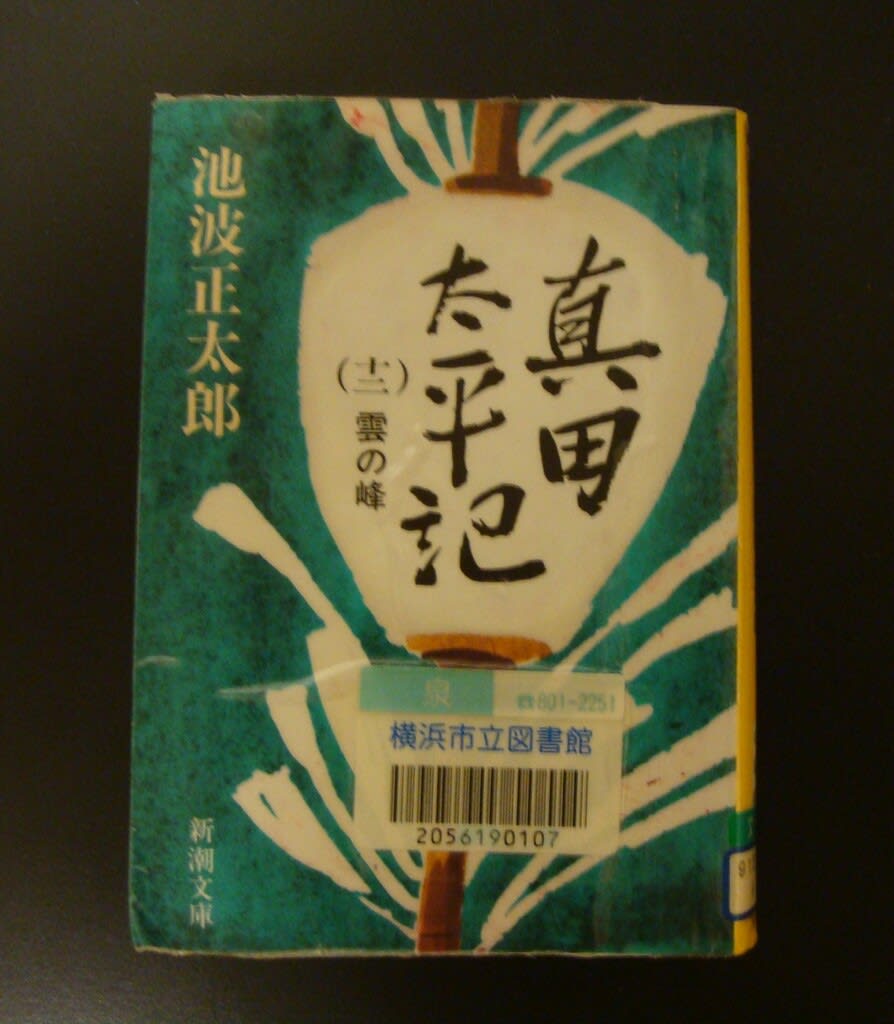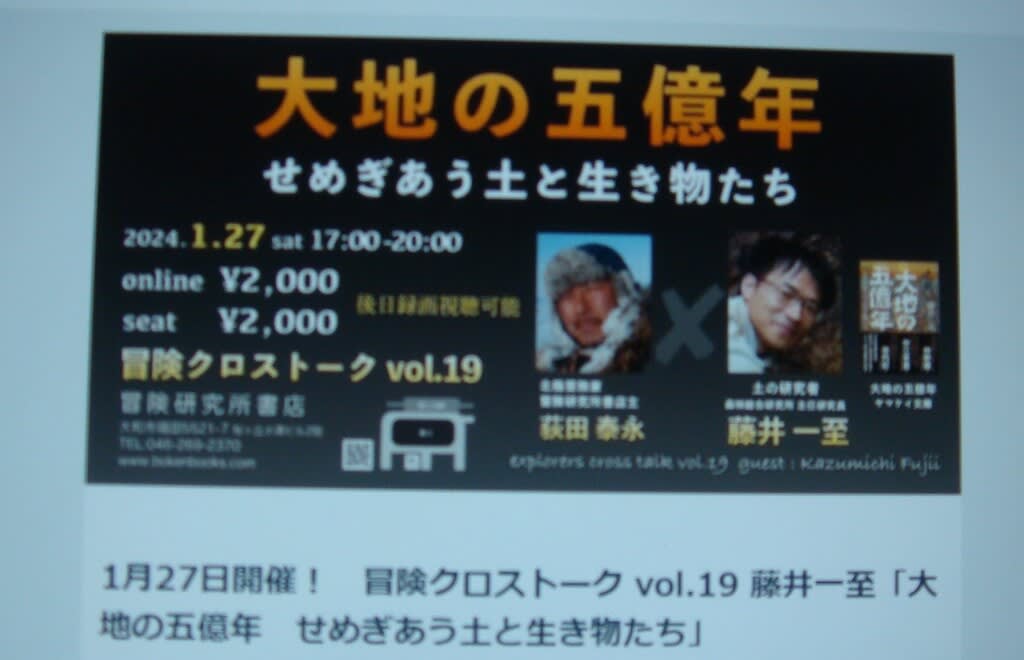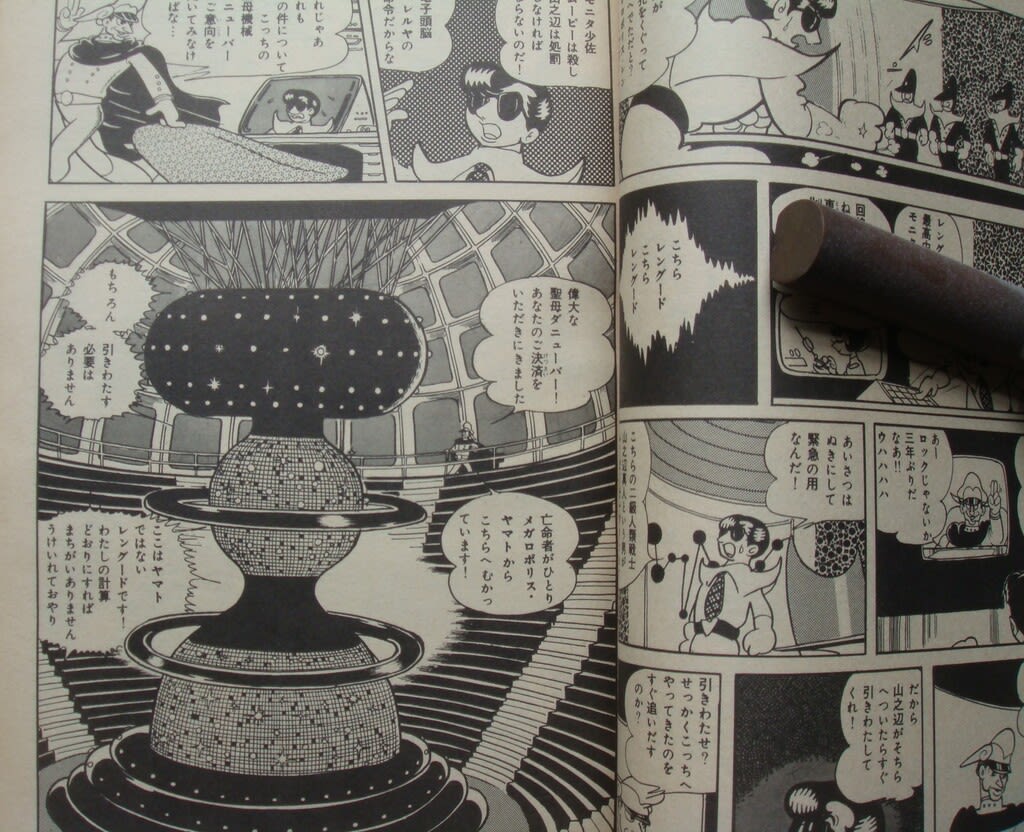今年の1月に 市の図書館システムが 全面的に刷新された
スマホ使用にも耐えられるよう サービスが向上し より便利になった
なかでも 自分が借りた本の履歴が見れるようになったのは有難い
借りた本を読み進めてゆくうち これは読んだぞ と思うことが度々あった
面白い本ならば何でもよいのだが 面白さはこれですと なかなか一概に言えない
読書歴から AIが推定して 読む本を推薦してくれないかな と思ったりする
最近では ブロガーさんの推薦本を参考にすることが多くなった
いろいろな世界を感じ取るのは読書の楽しみと思う
『天祐なり』 幸田真音
高橋是清の一代記 是清は1854年 徳川時代末期に 政治家とは何の繋がりのない家に生まれた
13歳でアメリカに留学し 英語を理解した
その英語力と人柄 物事の理解力が優れていたのか 是清は次々と明治を創った人物と 誼を得てゆく
海外にも人脈を築き 又 時節にも恵まれ 財政家として日本に貢献するようになる 天運にも恵まれ 大蔵大臣 総理大臣 をも歴任・・
そして 1936年の2・26事件で暗殺されるまでの物語
『真田太平記』 池波正太郎
今からザッと500年前 信州の小大名 真田一族
戦国の世をいかに生き残るか 著者は史実とフィクションを交え物語る
武田が滅びた後 秀吉の恩を受け 秀頼に味方する 真田昌幸・幸村親子
一方 真田の長男信之は 徳川の養女を妻に娶っており 徳川に味方し 関が原に臨む
信之は生き残ったとはいえ 外様の真田へは厳しい幕府だった
強いものが生き残り 弱いものは滅びる 明解な時代を綴った歴史小説
『盤上の向日葵』 柚木裕子
将棋に命を懸けた男のミステリーフィクション
大酒のみで賭けマージャンにうつつを抜かす父親 極貧のなか凄絶に生きる男の子
そんな子の唯一の息抜きは廃品回収での将棋雑誌だった
・・・師との生死をかけた一番 頭の中の将棋盤に 決め手が閃く そこに一面に向日葵が咲く
必死の時の向日葵 それは狂気の血が成せる仕業か