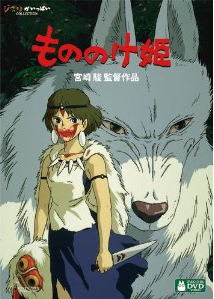(1)中国で儒教やキリスト教が流行している。拝金主義の蔓延、所得格差の拡大といった状況の中で、中国の庶民は「こころ」に目を向け始めた、とNHKスペシャルは伝える。胡錦濤総書記も、宗教を社会システムの一部として公認した。【注1】
だが、一斉に親の肩を揉み、一斉にその足を子が洗う儒教グループの儀式や、キリスト教会における乱暴と見えるほど粗っぽい洗礼、アジ演説を連想させる説教の模様には、異様な印象を受ける。
(2)キリスト教とは何か、キリスト教徒とは誰か、ある人が神の前でキリスト教徒と認められるか否かは、教会に毎日曜日に行って、ある一連の典礼(儀式)に参加するか否かとか、洗礼を受けたことがあるか否かとかいった形式的なことによって決まるのではない。その人の信仰内容をもってのみ決まる。その人が何を信じるか、という信仰内容によってのみ決まる、というのがキリスト教の基本的考え方だ。
キリスト教徒とそうでない人々とを分ける箇条書きの信仰内容を、ひとまとまりの告白分の形(各文の頭が「我信ず・・・・」で始まる)にしてまとめたものが「信条(creed)」だ。
信条の内容は、時代や信者集団によって微妙に変化していくが、ときどき大変化することがある。大きく変化すると、これまで真理だと信じられていたことが、突然、まったくの偽りと見なされるようになったりする。信仰内容のパラダイム・チェンジがそこで起きたわけだ。その結果、その変化についていける人と、ついていけないで、これまでの信仰内容のほうが正しく、新しい教えは偽りないし悪魔の教えだ、と見る人々が出て、両者が分裂してしまう。分裂のたびに正統と異端が分かれていく。<例>16世紀の宗教改革。
(3)キリスト教には、もともと三つの神概念がある。「父なる神」「子なる神」「聖霊なる神」だ。
その三つの神が、三つにして一つ、三つの神の本質部分はまったく同一であり、違いがあるのは「位格」だけ・・・・というのが三位一体論だ。
「位格」の原語(ギリシア語)はペルソナだ。ペルソナとは、ギリシア演劇で役者がかぶる仮面のことだ。役者は、いろんな仮面をかぶることで、いろんな劇中人物になる。それと同じで、神は人間界に出てくるときは、いろんな仮面をかぶって出てくる。どの仮面をかぶっているときも、神の本質は同じだが、人間が認識できる姿、現れ方が違う。これを位格(ペルソナ)というわけだ。
同じ樹に根があり、幹があり、実があるが、そのすべてが統一の樹木であり、違いは現れ方の違いにすぎない。・・・・これは三位一体のたとえとして、よく用いられる。
しかし、そのたとえでは一人三役の三位一体にしかならない、という批判もある。一人三役割だと、子なる神(キリスト)の受難死も実は天父が死んだことになり、天父受難説という異端思想になってしまう、という批判だ。
アリウスが唱えていたのはまさにそれで、アリウスは神はあくまで一人である、とする唯一神の立場に立った。神だけが神であり、神の子であろうと、子は神ではなく、子と神とは異質である、とした。子は天父の意志によって、無から創造された被造物である、とした。
それに対して正統派は、天なる神も子なる神(キリスト)もまったく同質で、神の子は被造物ではなく、この世のありとあらゆるものを創り出した創造神であり、存在の始まりを持たない永遠の存在である、としている。
クリスチャン以外には、このあたりがちょっと分かりにくいところだ。キリストはマリアから生まれたのだから、そのときをもって存在し始めたのであり、それ以前(生まれる以前)から実はキリストが存在していたのだ、という主張は常識的には分かりにくい。しかし、聖書に従えば、この常識に反する主張のほうが正しい。【注2】
(4)キリスト教が今日知られている教理に落ち着くまでには、教会規律や儀式典礼のあり方、戒律などに関して、いろいろな異論が出てきて、何が正しいのか、混乱が生じたことが一度ならずあった。こうしたとき、カソリック世界の有力な教会の代表者を集めて議論を十二分に闘わせた上、後は投票で決めよう・・・・という趣旨で行われたのが公会議(プロテスタントでは総会議という)だ。多数の支持を集めたほうが正統となり、少数の支持しか集まらず、排斥されたほうが異端となる。
第1回のニカイア公会議(325年)では、三位一体説に反対して、父なる神だけが真の神であり、子なる神のキリストは神ではない、としたアリウス派が異端とされた。ニカイア公会議で定められたキリスト教の基本的教義をニカイア信条という。
三位一体を正統とする教義がここで確立された・・・・かというと、必ずしもそうではない。三位一体説には分かりにくい部分がある。単純に父なる神だけが神で、子なる神のイエス・キリストは本当は人間である、と考えるアリウス派のほうがすっきりした分かりやすい主張だったこともあって、実はアリウス派的主張はその後も繰り返し現れる。
そもそも、ニカイア公会議を召集したコンスタンティヌス・東ローマ皇帝自身が、ニカイア公会議が終わると、本当はアリウス派のほうが正しい気がする、などと言い出したのだ。
今日、米国で特にインテリ層を中心に少なからぬ支持を集めているユニテリア教会も、イエスは人である、という主張をしている。
イエスには人性と神性の二つの性格がある、とするのがキリスト両性論だが、キリストは神ではなくて人である、とするのがキリスト単性説だ。キリスト単性説は、すなわちユニテリアンだ。
(5)その後も、公会議はいろいろな大問題(<例>十字軍問題やプロテスタント問題)が起きるごとに開かれ、これまでに21回開催された。
キリスト教の基本的な教義は、初期の8回で決まった、とされるが、その中でも大きな分岐点になったのが、第3回のエフェソス会議(431年、聖母マリア問題)だった。ここで、マリアを神の母(テオトコス)と認めた。【注3】
これに最後まで反対したネストリウス派は異端とされ、キリスト教の主流から放逐された。ネストリウス派は、その後も中東地方で根強い支持を集め続けたが、第4回のカルケドン公会議(451年)でも敗北し、最終的に教会から追い出された。しかし、ネストリウス派は、その後ペルシアを経て中国にまで教えを広め、唐の太宗の時代に長安に寺院を建て、大秦景教を名乗る。この教えは日本にも伝わり、広隆寺(京都)はこの流れを汲む寺院とされる。
【注1】このくだりは、2013年10月13日放映のNHKスペシャル「中国激動 "さまよえる"人民のこころ」に拠る。
【注2】以下、「【本】欧米理解に不可欠なこと ~『立花隆の書棚』~」の(4)を参照。
「【本】欧米理解に不可欠なこと ~『立花隆の書棚』~」
【注3】以下、「【本】土着の宗教と結びついたキリスト教 ~『立花隆の書棚』(2)~」の(1)を参照。
□立花隆/写真:薈田 純一『立花隆の書棚』(中央公論新社、2013.3)の第2章、第7章
【参考】
「【本】イスラム世界におけるペルシアの独特な立ち位置 ~『立花隆の書棚』(4)~」
「【本】旧約聖書には天地創造神話が2つある ~『立花隆の書棚』(3)~」
「【本】土着の宗教と結びついたキリスト教 ~『立花隆の書棚』(2)~」
「【本】欧米理解に不可欠なこと ~『立花隆の書棚』~」
↓クリック、プリーズ。↓



だが、一斉に親の肩を揉み、一斉にその足を子が洗う儒教グループの儀式や、キリスト教会における乱暴と見えるほど粗っぽい洗礼、アジ演説を連想させる説教の模様には、異様な印象を受ける。
(2)キリスト教とは何か、キリスト教徒とは誰か、ある人が神の前でキリスト教徒と認められるか否かは、教会に毎日曜日に行って、ある一連の典礼(儀式)に参加するか否かとか、洗礼を受けたことがあるか否かとかいった形式的なことによって決まるのではない。その人の信仰内容をもってのみ決まる。その人が何を信じるか、という信仰内容によってのみ決まる、というのがキリスト教の基本的考え方だ。
キリスト教徒とそうでない人々とを分ける箇条書きの信仰内容を、ひとまとまりの告白分の形(各文の頭が「我信ず・・・・」で始まる)にしてまとめたものが「信条(creed)」だ。
信条の内容は、時代や信者集団によって微妙に変化していくが、ときどき大変化することがある。大きく変化すると、これまで真理だと信じられていたことが、突然、まったくの偽りと見なされるようになったりする。信仰内容のパラダイム・チェンジがそこで起きたわけだ。その結果、その変化についていける人と、ついていけないで、これまでの信仰内容のほうが正しく、新しい教えは偽りないし悪魔の教えだ、と見る人々が出て、両者が分裂してしまう。分裂のたびに正統と異端が分かれていく。<例>16世紀の宗教改革。
(3)キリスト教には、もともと三つの神概念がある。「父なる神」「子なる神」「聖霊なる神」だ。
その三つの神が、三つにして一つ、三つの神の本質部分はまったく同一であり、違いがあるのは「位格」だけ・・・・というのが三位一体論だ。
「位格」の原語(ギリシア語)はペルソナだ。ペルソナとは、ギリシア演劇で役者がかぶる仮面のことだ。役者は、いろんな仮面をかぶることで、いろんな劇中人物になる。それと同じで、神は人間界に出てくるときは、いろんな仮面をかぶって出てくる。どの仮面をかぶっているときも、神の本質は同じだが、人間が認識できる姿、現れ方が違う。これを位格(ペルソナ)というわけだ。
同じ樹に根があり、幹があり、実があるが、そのすべてが統一の樹木であり、違いは現れ方の違いにすぎない。・・・・これは三位一体のたとえとして、よく用いられる。
しかし、そのたとえでは一人三役の三位一体にしかならない、という批判もある。一人三役割だと、子なる神(キリスト)の受難死も実は天父が死んだことになり、天父受難説という異端思想になってしまう、という批判だ。
アリウスが唱えていたのはまさにそれで、アリウスは神はあくまで一人である、とする唯一神の立場に立った。神だけが神であり、神の子であろうと、子は神ではなく、子と神とは異質である、とした。子は天父の意志によって、無から創造された被造物である、とした。
それに対して正統派は、天なる神も子なる神(キリスト)もまったく同質で、神の子は被造物ではなく、この世のありとあらゆるものを創り出した創造神であり、存在の始まりを持たない永遠の存在である、としている。
クリスチャン以外には、このあたりがちょっと分かりにくいところだ。キリストはマリアから生まれたのだから、そのときをもって存在し始めたのであり、それ以前(生まれる以前)から実はキリストが存在していたのだ、という主張は常識的には分かりにくい。しかし、聖書に従えば、この常識に反する主張のほうが正しい。【注2】
(4)キリスト教が今日知られている教理に落ち着くまでには、教会規律や儀式典礼のあり方、戒律などに関して、いろいろな異論が出てきて、何が正しいのか、混乱が生じたことが一度ならずあった。こうしたとき、カソリック世界の有力な教会の代表者を集めて議論を十二分に闘わせた上、後は投票で決めよう・・・・という趣旨で行われたのが公会議(プロテスタントでは総会議という)だ。多数の支持を集めたほうが正統となり、少数の支持しか集まらず、排斥されたほうが異端となる。
第1回のニカイア公会議(325年)では、三位一体説に反対して、父なる神だけが真の神であり、子なる神のキリストは神ではない、としたアリウス派が異端とされた。ニカイア公会議で定められたキリスト教の基本的教義をニカイア信条という。
三位一体を正統とする教義がここで確立された・・・・かというと、必ずしもそうではない。三位一体説には分かりにくい部分がある。単純に父なる神だけが神で、子なる神のイエス・キリストは本当は人間である、と考えるアリウス派のほうがすっきりした分かりやすい主張だったこともあって、実はアリウス派的主張はその後も繰り返し現れる。
そもそも、ニカイア公会議を召集したコンスタンティヌス・東ローマ皇帝自身が、ニカイア公会議が終わると、本当はアリウス派のほうが正しい気がする、などと言い出したのだ。
今日、米国で特にインテリ層を中心に少なからぬ支持を集めているユニテリア教会も、イエスは人である、という主張をしている。
イエスには人性と神性の二つの性格がある、とするのがキリスト両性論だが、キリストは神ではなくて人である、とするのがキリスト単性説だ。キリスト単性説は、すなわちユニテリアンだ。
(5)その後も、公会議はいろいろな大問題(<例>十字軍問題やプロテスタント問題)が起きるごとに開かれ、これまでに21回開催された。
キリスト教の基本的な教義は、初期の8回で決まった、とされるが、その中でも大きな分岐点になったのが、第3回のエフェソス会議(431年、聖母マリア問題)だった。ここで、マリアを神の母(テオトコス)と認めた。【注3】
これに最後まで反対したネストリウス派は異端とされ、キリスト教の主流から放逐された。ネストリウス派は、その後も中東地方で根強い支持を集め続けたが、第4回のカルケドン公会議(451年)でも敗北し、最終的に教会から追い出された。しかし、ネストリウス派は、その後ペルシアを経て中国にまで教えを広め、唐の太宗の時代に長安に寺院を建て、大秦景教を名乗る。この教えは日本にも伝わり、広隆寺(京都)はこの流れを汲む寺院とされる。
【注1】このくだりは、2013年10月13日放映のNHKスペシャル「中国激動 "さまよえる"人民のこころ」に拠る。
【注2】以下、「【本】欧米理解に不可欠なこと ~『立花隆の書棚』~」の(4)を参照。
「【本】欧米理解に不可欠なこと ~『立花隆の書棚』~」
【注3】以下、「【本】土着の宗教と結びついたキリスト教 ~『立花隆の書棚』(2)~」の(1)を参照。
□立花隆/写真:薈田 純一『立花隆の書棚』(中央公論新社、2013.3)の第2章、第7章
【参考】
「【本】イスラム世界におけるペルシアの独特な立ち位置 ~『立花隆の書棚』(4)~」
「【本】旧約聖書には天地創造神話が2つある ~『立花隆の書棚』(3)~」
「【本】土着の宗教と結びついたキリスト教 ~『立花隆の書棚』(2)~」
「【本】欧米理解に不可欠なこと ~『立花隆の書棚』~」
↓クリック、プリーズ。↓