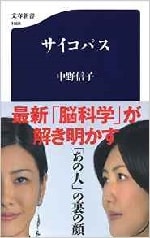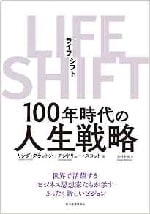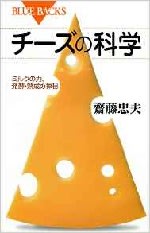(1)癌予防といえば野菜の摂取だ。国立がん研究センターが行った大規模な追跡調査では、野菜を多く摂ることで食道癌のリスクは「ほぼ確実に」下がり、胃癌もリスク減の「可能性あり」と評価されている。
(2)なかでも発癌物質を抑えるのに効果的だとされているのが、ブロッコリやキャベツなどのアブラナ科野菜だ。
アブラナ科野菜にはイソチオシアネートという硫黄化物が多く含まれていて、これが肝臓にある解毒酵素お活性を高めてくれる。人は食品からもいろいろな発癌物質を摂ってしまうし、体内でできることもある。そういうものが遺伝子を傷つける前に無力化してしまうという防御力の一種だ。しかも一部の癌ではなく、「守備範囲」が広いため、注目されている素材だ。
この成分が注目されるきかっけは、米国のブロッコリに関する研究だ。
どうもブロッコリに癌予防の効果があるようだと、ジョンズ・ホプキンス大学のタラレー教授が中心になって研究が進んだ。特にブロッコリのスプラウト(発芽直前の新芽)だとイソチオシアネートの量が多くなり、5グラムのスプラウトで普通のブロッコリ150グラム分と同じ効果があることがわかった。そこからさらに品種を特別選抜し、「ブロッコリースーパースプラウト」と名づけて、いまでは日本のスーパーでも簡単に入手できる。
(3)同じアブラナ科で日本原産のわさびにもブロッコリと同様の効果があるという。
大澤俊彦・愛知学院大学教授らはわさびのイソチオシアネートに関する研究をずっと続けてきた。わさびはたった5グラムでブロッコリ150グラム分と同じ効果がある。ただし、注意すべきは、これらアブラナ科野菜を摂りすぎると甲状腺などに副作用がでるので、過剰摂取はよくない。やはりなるべく多くの野菜をバランスよく摂るのが一番だ。
セリ科野菜にはポリフェノールが多いし、ユリ科野菜にはアリル硫黄化合物がある。ごまのリグナンやカレー料理のクルクミンにも解毒力を高める同じような作用がある。
できれば、これらで「城壁」を作るように、数日に1回は全体を食べるようなメニューを考えたほうがよい。
数日に1回でよいのは、この解毒力の持続性が高いからだ。
たとえば抗酸化成分だと食べて数時間で血液の中に入って抗酸化性を示すのだが、解毒力のほうはわりと持続性が高い。動物実験の結果では72時間(3日間)くらいは持続するので、ブロッコリなどを食べるのも週2回でよい。わさびやブロッコリスプラウトなら5グラムで十分だから簡単に摂れる。こういう持続性もイソチオシアネートの持つ優れた力だ。
(4)日本食でいえば、大豆食品も乳癌や前立腺癌で予防効果を発揮する。
世界中の60数地域で、大豆の成分のイソフラボン摂取量を尿で測定し、病気との関係を見た結果は、イソフラボンの量が多いと明らかに乳癌と前立腺癌の死亡率が低くなっていた。これまで大豆の摂取量が多かった日本や中国には乳癌や前立腺癌の患者が少なく、摂取量が減るとともに乳癌や前立腺癌が増えてきたこととも関係している。さらに、癌の死亡率全体も、大豆を摂っている地域で低いという研究結果もある。
癌が大きくなるときには血管を周囲に張り巡らせて、血流を取り込んで癌自身が大きくなり、血管を伝って転移して重症化する。大豆のイソフラボンは、その血管を作らせない「兵糧攻め」の効果があるとされている。
豆腐や納豆など日常的な食材にも、癌予防の効果はあるのだ。
□守屋浩司・編『人生を変える! 食の新常識/カラダにいい食事 決定版』(文春ムック、2016)の「身近な食品で今日から健康に!」(初出「週刊文春」2015年5月28日号)
↓クリック、プリーズ。↓



【参考】
「
【保健】身近な食品で今日から健康に(3) ~アボカド~」
「
【保健】身近な食品で今日から健康に(2) ~落花生~」
「
【保健】身近な食品で今日から健康に(1) ~チョコレート~」
「
【保健】意外や意外、卵で糖尿病は予防できる」