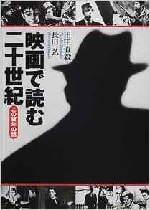音響は、地形や天候により微妙に違って伝播するらしい。井伏鱒二は悠然たる筆致で、大正期の時代性も併せて伝える。音響の伝播にも時代という環境条件が伴うのである。
---(引用開始)---
音響といふものは、どんな伝播の仕方をするか、容易に我々の推測を許さない。音は種類によつて、一つ一つ別途な伝播の仕方をするかもしれぬ。昔の人の書いた記録によると、山伏の法螺貝の音は岡を通り越して岡の向側まで聞え、尼さんの団扇太鼓の音は岡で行きどまりになるさうだ。また一説に、山寺の釣鐘の音は、谷間伝ひではなくて尾根から尾根に伝はつて、山越えで峠まで聞えて行くと言はれてゐる。すると、法螺貝の音と釣鐘の音を混ぜ合せたやうな汽笛の音は、森や林を越えて街の上空を流れて来るかもしれぬ。障害物となるものは何であるか。
「しかし弥次郎さん、物理学的に言つて、曇つた日や灰色の湿つぽい日は、遠方からの物音が、却つてよく伝はるといふことだね。関東大震災後、汽笛の音の伝播を阻害したのは何だらう」
この質問に、弥次郎さんは言つた。
「いや、品川の汽笛の音は、大震災後、晴雨にかかはらず聞えなくなつた。たしかにさうだ。府中の大明神様の大太鼓の音も、もとは祭の日に荻窪まで聞えたもんだ。大震災後、やがてこれも聞えなくなつた。この辺の澄んでた空気が、急にさうでもなくなつたといふことぢやないのかね」
何かプラス・マイナスの関係で、汽笛の音を消すやうになつたのだ。
大正十二年が関東大震災で、弥次郎さんは大正十三年に徴兵検査を受けた。そのころはもう汽笛の音が聞えなくなつてゐたが、府中大明神の大太鼓の音はまだ微かに聞え、お祭の当日は六の宮の御輿が出て、一番から六番までの大太鼓の音が聞えたさうだ。
「ところが大震災後も、品川の汽笛は、鳴子坂あたりでならまだ聞えてゐた」と弥次郎さんが言つた。
荻窪から京橋のヤッチャ場へ車を曳いて行く途中、たまたま鳴子坂の上に出ると早朝の汽笛の音を聞くことが出来たといふ。その後、また暫くすると、鳴子坂の上からも汽笛は聞えなくなつたさうだ。
---(引用終了)---
□井伏鱒二(『井伏鱒二自選全集 第12巻』(新潮社、1986)の「荻窪風土記--豊多摩郡井荻村」の「荻窪八丁通り」から一部引用

---(引用開始)---
音響といふものは、どんな伝播の仕方をするか、容易に我々の推測を許さない。音は種類によつて、一つ一つ別途な伝播の仕方をするかもしれぬ。昔の人の書いた記録によると、山伏の法螺貝の音は岡を通り越して岡の向側まで聞え、尼さんの団扇太鼓の音は岡で行きどまりになるさうだ。また一説に、山寺の釣鐘の音は、谷間伝ひではなくて尾根から尾根に伝はつて、山越えで峠まで聞えて行くと言はれてゐる。すると、法螺貝の音と釣鐘の音を混ぜ合せたやうな汽笛の音は、森や林を越えて街の上空を流れて来るかもしれぬ。障害物となるものは何であるか。
「しかし弥次郎さん、物理学的に言つて、曇つた日や灰色の湿つぽい日は、遠方からの物音が、却つてよく伝はるといふことだね。関東大震災後、汽笛の音の伝播を阻害したのは何だらう」
この質問に、弥次郎さんは言つた。
「いや、品川の汽笛の音は、大震災後、晴雨にかかはらず聞えなくなつた。たしかにさうだ。府中の大明神様の大太鼓の音も、もとは祭の日に荻窪まで聞えたもんだ。大震災後、やがてこれも聞えなくなつた。この辺の澄んでた空気が、急にさうでもなくなつたといふことぢやないのかね」
何かプラス・マイナスの関係で、汽笛の音を消すやうになつたのだ。
大正十二年が関東大震災で、弥次郎さんは大正十三年に徴兵検査を受けた。そのころはもう汽笛の音が聞えなくなつてゐたが、府中大明神の大太鼓の音はまだ微かに聞え、お祭の当日は六の宮の御輿が出て、一番から六番までの大太鼓の音が聞えたさうだ。
「ところが大震災後も、品川の汽笛は、鳴子坂あたりでならまだ聞えてゐた」と弥次郎さんが言つた。
荻窪から京橋のヤッチャ場へ車を曳いて行く途中、たまたま鳴子坂の上に出ると早朝の汽笛の音を聞くことが出来たといふ。その後、また暫くすると、鳴子坂の上からも汽笛は聞えなくなつたさうだ。
---(引用終了)---
□井伏鱒二(『井伏鱒二自選全集 第12巻』(新潮社、1986)の「荻窪風土記--豊多摩郡井荻村」の「荻窪八丁通り」から一部引用