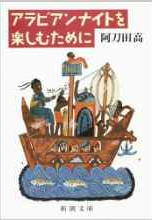
古い倉庫を始末し、新しく設置した際、古い倉庫から出てきた本の一。
(1)論文にはサマリーがある。議論の要点を提示して、関心が持てる内容なら本文に読み進める仕組みだ。
この伝で、小説や物語にもサマリーがあってもよい。あまりにも長すぎるとか、古典中の古典で、読みごたえがあるにしてもとっつきにくいとか、そういう本には論文のサマリーに相当する要約本があってもよい。リーダーズダイジェストは新刊について要約を紹介しているが、あいにく日本版は1986年に休刊した。
(2)『アラビアンナイト』も長すぎる本だ。しかも脇筋へ遠慮なくどんどん逸れていくから、主筋を追いにくい。追っても意味がない。主筋はあってなきがごとしで、独立した説話が次々に付け加わるだけなのだから。
全編が面白ければよいのだが、饒舌なだけでじつに退屈な挿話もある。
(3)煩瑣に耐えてバートン版(大場正史訳)、マルドリュス版(豊島与志雄ほか訳)、東洋文庫版(前嶋信次訳)の3種類を読破し、血わき肉おどる部分を12編の短編小説仕立てに料理したのが本書。
原作を読まないと読んだうちに入らない、というリゴリスムは無視してさしつかえない。ダイジェストであろうと翻案であろうと、まったく読まないよりマシだ。
阿刀田高は、古典について幾冊かものしているが、これはこれで貴重な仕事なのだ。現代の言葉で、忙しい現代人が古典中の古典に接する機会を提供しているのだから。
(4)そもそも、わが国には、黒岩涙香以来、翻案小説の伝統がある。比較的最近では、発達心理学の泰斗にしてわが国における文章心理学の草分け、波多野完治がジュール・ヴェルヌの『二年間の休暇』を翻案して『十五少年漂流記』に仕立てあげている(新潮文庫)。
本書も、作品紹介というよりも翻案だ。しかも、読みやすい阿刀田調の語り口にのせられて、読者は一編また一編と、ページをめくるのがもどかしい思いをするだろう。
本書は、『アラビアンナイト』をまったく読んだことのない人には読書案内となるし、一部しか読んだことのない人には覚えのある物語に再会する愉しみがある。そして、原作からぐんと離れて、星新一的に現代的な解釈をほどこした短編には、思わず微笑するにちがいない。
□阿刀田高『アラビアンナイトを楽しむために』(新潮社、1983)
↓クリック、プリーズ。↓


















