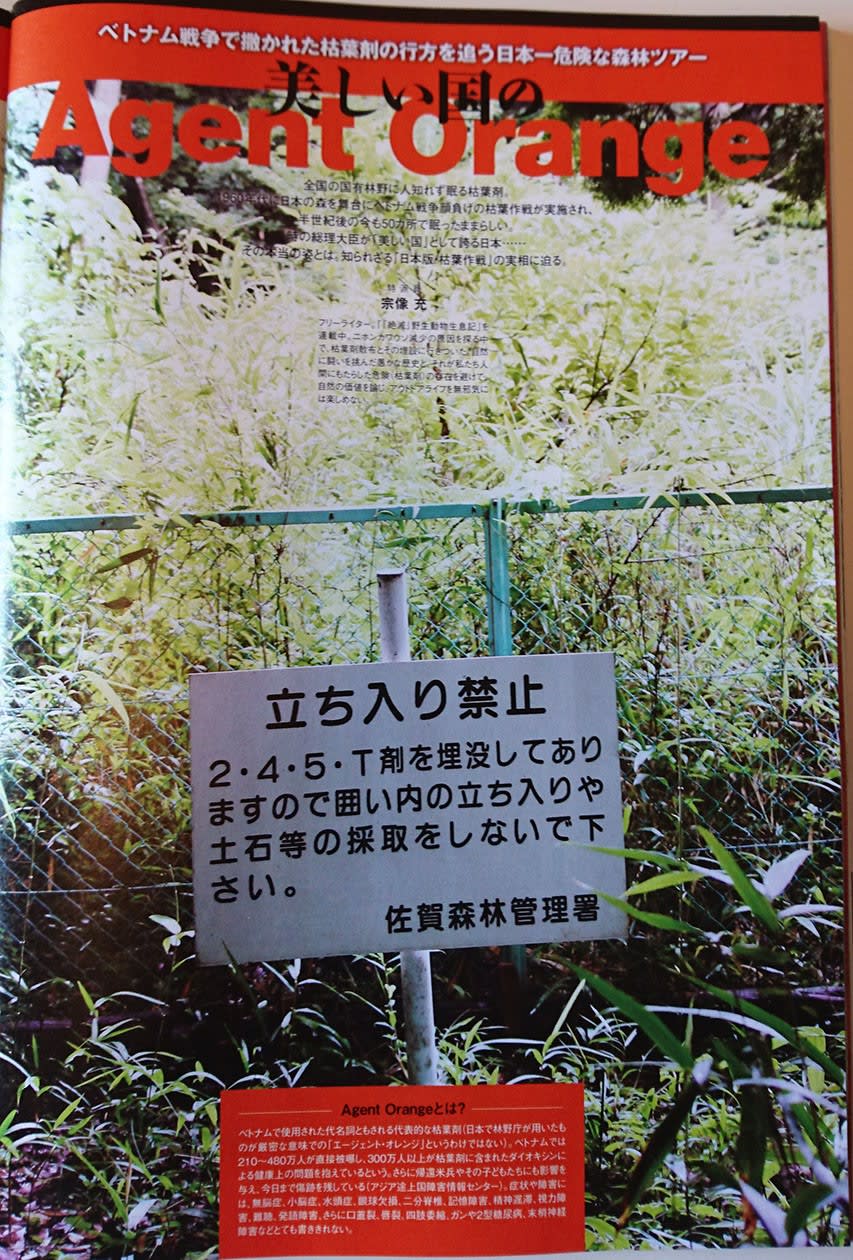先週(24日)、九州北部は平年より5日、昨年より15日遅く梅雨明けした。梅雨入り(6月26日)が平年より2週間遅れだったので、梅雨期間としては、ほぼ平年並みとなった。梅雨末期には、大型の台風5号(16日発生)による影響で、九州北部は各地で大雨となった。20日には長崎県五島列島や対馬で、21日には福岡県久留米市(1時間雨量90ミリ)や佐賀県鳥栖市(1時間雨量81.5ミリ)で猛烈な雨(それぞれ観測史上1位)となり、冠水などの被害が出た。ただ人的被害が少なかったことは幸いだった。
そういうわけで、心配されていた福岡県のダム貯水率は平年値まであと10%のところまで回復。グラフを見ると、まさにうなぎのぼり。(下図参照)データを見ると、30日現在、福岡県内主要18ダム貯水率は80.9%、南畑ダムは91.7%でほぼ満水の状態。五ヶ山ダムは79.6%、満水位まであと6mのところ。そこで、ダムの状況を確認するため、現地へ行ってみることにした。
昨日(30日)午前中、五ヶ山では小雨が降っていた。気温は27℃で福岡市内に比べ6~7℃低い。五ヶ山クロスベースにある、モンベルの方の話によると、このところ天候が急変することが多いとのこと。五ヶ山は標高500m、山の天気は変わりやすい。特に、梅雨明け後、気温が急上昇し大気が不安定になっているからだろう。そこで、まず大雨による異変がないかを確認し、ダム堤体に向かった。水位をみると、データどおり約401m、満水位まで6mだった。昨年の西日本豪雨では1日7m上昇したが、今月の大雨では4~5日で4m上昇。いかに西日本豪雨がもの凄い雨だったかがわかる。ふりかえってクレストゲート下の副ダムを見ると、すでに放流は行われていなかった。おそらく、南畑ダムが満水に近い状態まで回復しているからだろう。
帰路、南畑ダムに立ち寄ってみると、南畑ダムの吐水口からどんどん水が放流されていた。こうした状況から、現在、福岡市は五ヶ山ダムからではなく、南畑ダムから取水しているものと思われる。問題はこれから秋の台風シーズンにどれほど雨が降るか。昨年は西日本豪雨後に少雨傾向が続き、それは先月まで続いた。もはや豪雨でしか水は溜まらない状況になっている。ふたたび少雨となれば、(福岡市は)五ヶ山ダムから取水を行うことになるのだろうが、そうなると五ヶ山ダムの試験湛水は終わらないまま、運用が続くことになる。もうすぐ試験湛水がはじまって3年(今年10月)、終わりが見えない。
撮影日:2019.7.30

水を湛える南畑ダム

回復しつつある五ヶ山ダム

取水設備に貼られた水位表示

現在、水位は約401m 大雨前は約397mだったので4m上昇(4月405m⇒6月399m⇒7月397m)

副ダムを見ると、水は出ていない

放流停止 (注:五ヶ山ダムと南畑ダム間の河川維持のため、常時少量(0.5㎥/s)放流されています)

水を湛えた南畑ダムが見える

南畑ダム、並々と

堤体付近

南畑ダムから放流

ほぼ平年並みまで回復

貯水率100%が並ぶ
《追記》
福岡市は7月30日をもって渇水対策会議を解散した。昨年からの少雨傾向により、福岡市は6月26日から渇水対策会議を設置していたが、7月17日からの降雨で筑後川の流況が回復したことから解散したことを報告。一方、福岡県は油木ダムの貯水率が依然低い状況で、行橋市、苅田町が15%の減圧給水などの対策を継続しているため、渇水対策本部は設置したままである。
・福岡県。7月21日の大雨などによる主要ダム貯水率について(7.26)
《関連記事》
《関連資料》