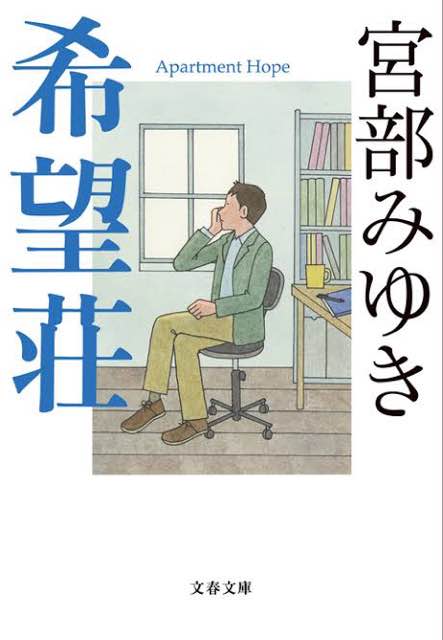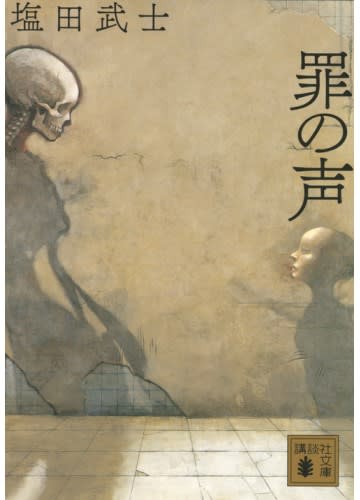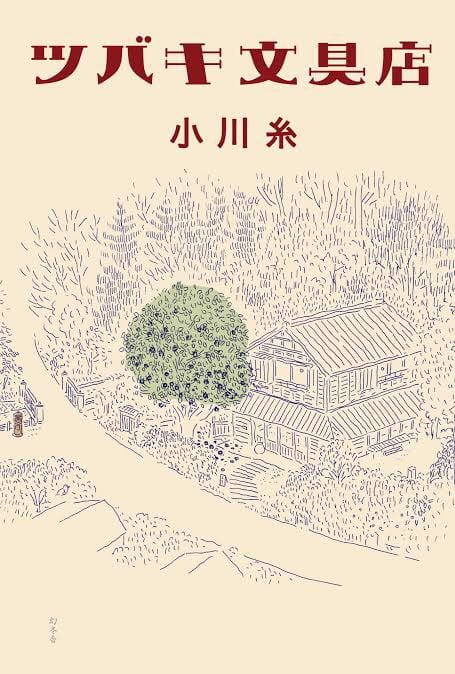○「そこに音楽があった~楽都仙台と東日本大震災」梶山寿子著(文芸春秋企画出版)
未曾有の大災害となった大地震とその後の大津波。
宮城県民、特に沿岸部の県民は命からがら避難ひて助かった人々も、途方にくれて何をすればよいか、何がしたいのか、どうすればよいのかも、しばらくは考えることもできなかったという。
そんな中、音楽に携わる人々は「こんな大変なときに音楽などやっていいのだろうか」と一様に悩み続けた。これは被災地のみならず全国のミュージシャンやマスコミが思ったこと。なのでコンサートは全国で相次いで中止になり、TVやラジオは音楽番組や娯楽番組を自粛した。TVをつければどこのチャンネルでも民間企業のCMは流れず、公共広告機構の暗いメッセージがこれでもかと繰り返し繰り返し放映された。
そんな中、こういうときこそ音楽で被災者を勇気づけよう、元気づけようと立ち上が人々が出始めた。
それが仙台フィルハーモニーの団員であり、ジャズフェスやとっておきの音楽祭の実行委員であり、避難所となった学校の合唱部や吹奏楽部の生徒であり先生、そして仙台ゆかりのミュージシャンたちだった・・・。
以前に仙台フィルメンバーの震災直後の奮闘ぶりがTV番組に取り上げられ、とても感動した。
この本を読んで他にもプロ・アマ問わず大勢の音楽家たちの活動がこんなにも熱く、そして被災地の人々をたくさん元気にしたんだと、改めて知ることができた。
そして東京の合唱団「お江戸コラリアーず」が、「こんなときに合唱なんかやっていいんだろうか、必要なんだろうかと悩みましたが、自分たちの歌で少しでも被災地の人々を元気にできたら」と、自分たちの演奏「くちびるに歌を」をFacebookにアップしたのを思い出した。
「つらいときこそくちびるに歌を持とう、心に太陽を持とう!」のメッセージがなんとも胸にしみて、涙が止まらなかった。
音楽の力は偉大なり!
聴いてくれる人に少しでも感動してもらい、そして自らもそれを楽しみ、豊かな気持ちになれる音楽活動ができたら、幸せだと思います。
PS)
ただ、本書にも度々登場する奥山仙台市長や行政が「仙台・楽都」を標榜することには、ちょっと違和感がある。
来年度の市の予算案も出ているが、前から要望の強い「音楽専用ホール」建設はまたまた遠のきそう。
市本庁舎の老朽化に伴い、建替えの計画が進んでいるらしい。優先順位はそっちが高いと奥山市長は明言している。
そりゃお金がふんだんにないのは分るけど、市庁舎と音楽ホールを同じ次元で語ることは、ちょっと違うと思うんですよ。民間との連携も含め、何かやりようはないんでしょうか。
仙台フィルのホームグラウンドが800人しか入らない?客席のキャパが足りなくて合唱コンクールの全国大会ができない?
東北の雄・仙台よ、100万都市・仙台よ、それはないでしょう!「楽都」が泣きますよ!