出版停止はおとり作戦か
2016年6月18日
首相はもちろん、安倍政権の閣僚が大勢、参加しているのが「日本会議」です。関係する国会議員は260人だそうです。神社系の宗教団体、霊友会、さらに生長の家の元活動家も加わっているとされ、宗教色が濃いようですね。その「日本会議」を題材にした新書「日本会議の研究」(扶桑社)が出版され、重版を重ねています。安倍首相の思想的な背景を知るのに役立つと思い、買ってみました。
買った本当の動機は、「日本会議」の事務総長が出版社に出版停止を申し入れており、何事かと思ったからです。書店に行ってみると、平台に多数、高く積み上げてあるではありませんか。1か月で3刷、4刷といいますから、売れているのでしょう。筆者は菅野完氏という著述家で、1974年生まれとあります。さて誰だろう。
読み始めてみると、いくつもの疑問というか謎が浮かんできました。ざっと読んでみると、出版停止を求められるほどのことは書いてないのです。団体内部の内ゲバが原因なのかなあ。ふと思い浮かんだのは、出版停止をおとりにして、話題に仕立て、本を売ろうとしたのではないか、ということです。安倍政権と密着する団体が題材ですから、出版停止は世間の耳目を集めますからね。私もおとりに引っかかったのでしょうか。
産経系の出版社が舞台を提供
次の謎は、出版社です。扶桑社といえば、フジ・サンケイグループの出版社であり、産経新聞は安倍政権にも日本会議にも極めて近く、同体みたいな関係です。その扶桑社が日本会議を中傷誹謗する本を出しますかねえ。扶桑社のWebサイトに連載していた記事を書籍にしたとあります。どうも、「日本会議」を国政選挙向けに宣伝するのがそもそもの目的だったのではないか。やりますね。
安倍政権や自民党批判の部分はあり、その狙いは何か。「自民党が表現の自由や立憲主義の諸原則を踏みにじる幼稚な政党に変質してしまった」と、書いてあります。「日本会議」は「今こそ憲法改正を。一万人大会」と、叫んできた組織だし、明治憲法の復元を望んでいるともいわれます。政権が安保法制で選択した「解釈改憲」方式が、気に入らないのかもしれません。安倍首相は本来、憲法改正派ですから、この本は政権を批判するふりして、首相の本音を代弁しているのでしょう。
第三の謎は筆者で、少なくとも私にとっては無名の人です。「サラリーマンとして勤務するかたわら執筆活動を開始、退職後の15年から著述活動を本格化した」との紹介があります。謎というのは、執筆の経験が浅い人物が「日本会議」に本格的に踏み込んだ本を書けるだろうか、です。かなりの筆力が感じられ、経験を積んだ筆者、たとえば専門家かノンフィクションライターが本当の筆者ではないか。
生長の家原理主義者に源流がある
この本のクライマックスは、「日本会議」、事務局の「日本青年協議会」の奥の院というべき場所に、安東巌氏なる人物が存在しているとの結論を強調するところに置かれています。この人物は、生長の家教団に奉職し、青年局の職員となり、「生長の家政治運動」の先頭を走り、その実務を仕切ったと、書かれています。教祖の谷口雅春に認められ、「谷口との個人的な紐帯に裏付けられた権威を持っており、安東巌にだれも逆らえない」と、強調しています。
生長の家は現在、政治活動との関わりを絶っているそうです。政治活動が止まり、宙に浮いてしまった活動家が複数、「生長の家原理主義者」として、今は「日本会議」、「日本青年協議会」を仕切っているといいます。出版停止を申し立てた事務総長の椛島有三氏、安倍首相のブレーン伊藤哲夫氏らもそうです。そのかれらよりも安東氏が格上で、普段は表にでてこない「神格化」された存在として扱っています。
とにかく「日本会議」の源流は、「生長の家原理主義」にあるといいたいのでしょう。内情に通じた人物が手引きしないと、経験の浅い著述家ではたどり着けない結論だと、思います。
宗教色の強い安倍マシーンか
安倍首相の行動部隊というか、選挙マシーンが生長の家原理主義に源流を持つとすれば、政治が宗教的思想に接近していることになります。「日本会議」は平成9年に発足し、退陣していた安倍氏を首相に復活させる狙いがあったようなことも書かれています。皇室中心、改憲、靖国参拝、愛国教育、自衛隊の海外派遣がキーワードになっています。安倍首相と相似形の団体ですから、かなり気になりますね。
「生長の家」は出版宗教といわれます。雑誌、多数の書籍を刊行し、それを売りながら支持者、信者を拡大し、組織を確立し、社会運動に発展させていく。創価学会にも似たところがあり、新興宗教に共通する手法ですね。そう考えると、「日本会議の研究」はかれらの得意とする出版戦略であり、「出版停止」はその一つなのかもしれません。











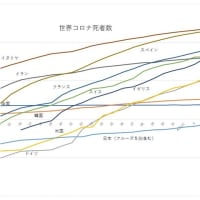









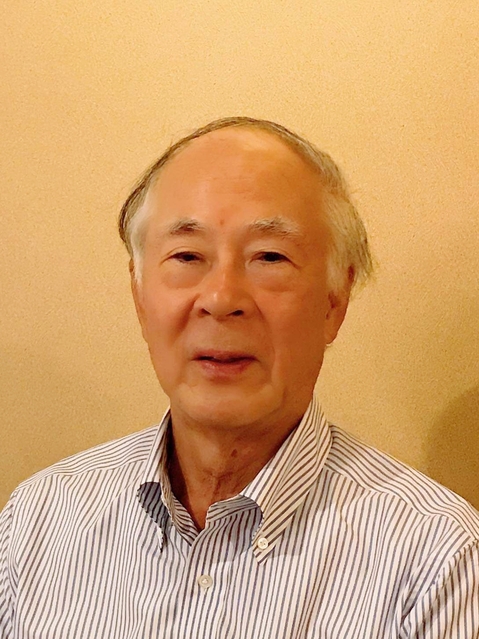

単に、扶桑社側としても日本会議の保守的な主張は同意できる部分もあるが、よく調べてみると危険な部分も同時に多いと考えて出版を行ったのかも知れません。実際の思惑は分かりませんが。それでは。