ドル高容認の背景には対中政策もある
2022年12月16日
日銀ウオチャーの加藤出氏(東短リサーチ)が最近書いたの記事の中で、1990年代のルービン米財務長官の「強いドルは米国の国益にかなう」との政策理念を想起しています。「強い通貨」は「対外的な購買力を高め、インフレ率を低下させる。良質な投資資金も流入する」との政策理念です。
加藤氏は「日本の通貨安は逆の悪循環を生む」と、日銀の金利政策を批判しています。OECDのデータでは、主要国の中で日本の名目賃金だけが過去30年間も横ばいです。米英加豪などはこの間2、3倍になっています。日本だけが世界経済の孤児になっている。異次元金融緩和、財政膨張の長期化に甘えて新陳代謝のなくなった経済構造がその要因になっている。
黒田日銀総裁は「異次元金融緩和の目的はデフレ脱却であり、円安誘導ではない」と、釈明を続けてきました。それに対し、元日銀理事の早川英雄氏は「アベノミクスの金融政策は円安政策だった。2%の物価上昇を達成するための手段は円安だった」と、ずばり指摘しています。
日銀を経て東大教授の渡辺務氏は「異次元緩和は大幅な円安を起すところまでは目論見通りだった。しかし、賃金が上がらないまま、物価だけが上がり始め、国民が悲鳴を上げるようになった」(講談社現代新書」と、これもずばりと、説明しています。
日銀にいた幹部の二人から「異次元緩和の目的は円安誘導だった」といわれては、黒田総裁はウソをつき続けてきたことになる。為替誘導は相場の乱高下などの緊急時への対応に限るというのが国際的な申し合わせです。黒田総裁はそれも破ってきたのです。
ここで想起すべきなのがルービン氏の「強いドルは国益にかなう」という経済的信念です。黒田氏は頑なに貨幣数量説を信じきり、目先の物価上昇率を注視し、金融政策を続けてきました。「弱い通貨(円)が国益にかなう」は、国際常識になじまない。
ここで注目したいのが、「米中経済の逆転はありうるのか」ということとドル高・元安との関係です。ルービン氏のころはまだ「米中経済の逆転」は現実的な問題ではなかった。今なら、「強いドルは米中逆転の阻止にもつながる」というに違いないと、私は思います。
2000年以降、「何年ころに逆転するか」という切迫した問題意識がもたれるようになりました。「為替レートが変わらなければ、2020年後半に逆転する」(2011年、伊藤隆敏・東大教授)と。「為替レートが不変」を前提をおく見通しはまず意味がなかったのに、そんな予測をした。
予測に熱心だったのは日本経済研究センター(日経新聞系)は、「2029年ころに逆転する」とのそれまでの予想を昨年「33年に逆転する」と先送りしました。さらに12月15日付の日経新聞一面で「米中GDPは逆転しない」(同経済センター)と、これまでと真逆の予想です。白紙撤回です。
「なんだこれは」と思いました。米中逆転があり得なくなった理由として、同センターは「コロナによる移動制限、米国の対中輸出規制、台湾有事を懸念する海外企業の中国離れ、長期的には人口減少・少子化による労働力不足」などをあげています。ドル高・元安も加えるべきです。
仏歴史人口学者のエマニュエル・トッド氏は「中国が強大は覇権国になることはない。教育水準や人口動態からみても、中国が世界のリーダーになる可能性はゼロでしょう」(文春新書、21年11月)と、一年前に言い切っています。まあ、日経グループの完敗です。
金利・為替政策を国際政治、国際経済全体との関係を考えて進めるべきです。権力志向、覇権志向の強い中国経済が米国経済を追い越してしまったら、中国の強国路線が加速するに違いありません。ドル高・元安はその点でも「米国の利益にかなう」ことになります。
ドル換算した中国のGDPは、ドル高・元安のため、その差を追い詰められなくなっている。最近は1㌦=約7元で08年以来の安値となり、元を基軸通貨の一つとして認知させようとの思惑も難くなっています。
米政府、FRBは長期的、歴史的な展望に立ったドル高政策を持っている。日々の動き、月々の動きとしては、物価、失業・雇用、賃金動向などを見極めていく。毎日の相場動向、FRB議長の発言ばかりに目を奪われてはいけない。政府、日銀はその後者の動きばかりを見ている。
人口減・労働力不足が深刻化している中で、外国人労働者が「円安で外貨換算した手取りが減り、祖国に送金できなくなった」というニュースが毎日のように報道されます。日銀は目を覚ますべきです。











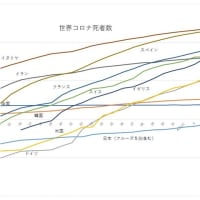









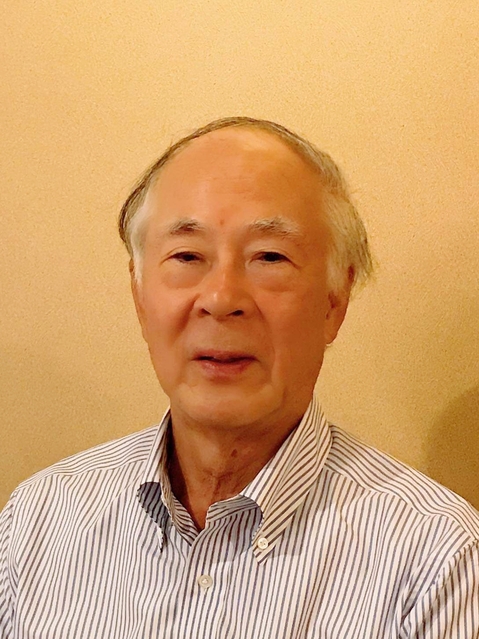

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます