
カウベルを担当することになったのですが、ここで一悶着ありました。






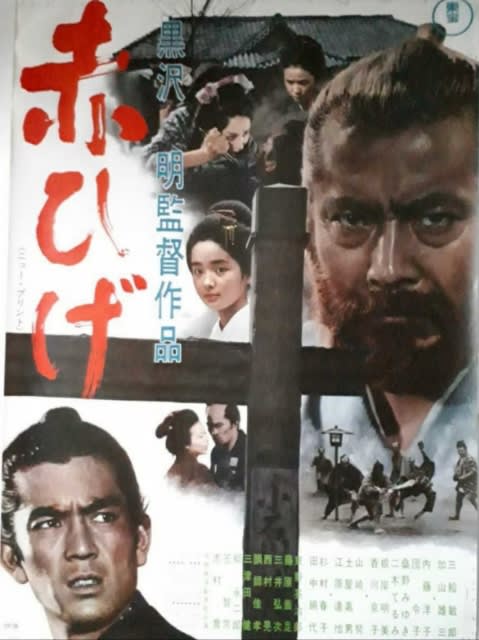











弦楽四重奏のために書かれていますが、コントラバスを加えた弦楽合奏による演奏もしばしば行われています。コントラバスが加わることで、弦楽四重奏では薄くなりがちな中間部に低音を充実させることができるので、成立の経緯もあってバーバーの《弦楽のためのアダージョ》とともに故人の追悼に使われることがあります。
そんなわけで、重陽の節句の今日はプッチーニの《菊》を弦楽合奏版でお聴きいただきたいと思います。モルドバ室内管弦楽団の演奏で、《マノン・レスコー》の世界観にも通ずる重厚な音楽をお楽しみください。


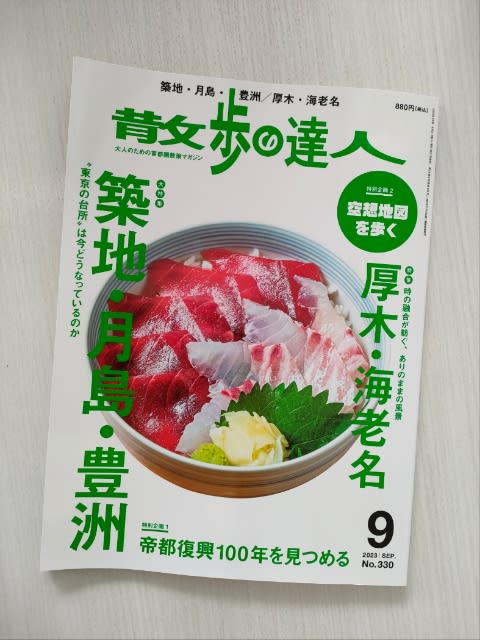

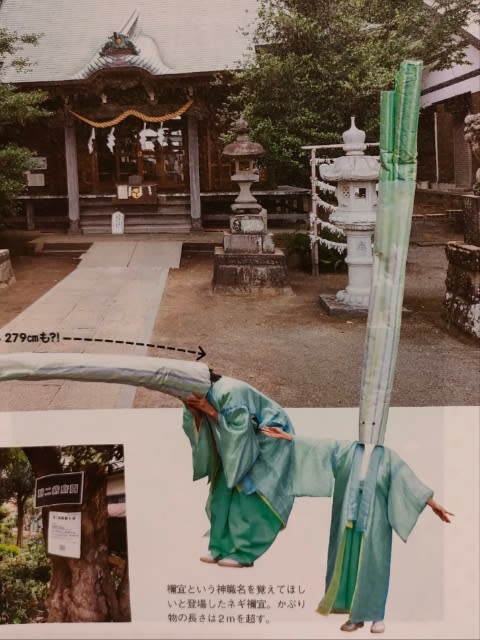
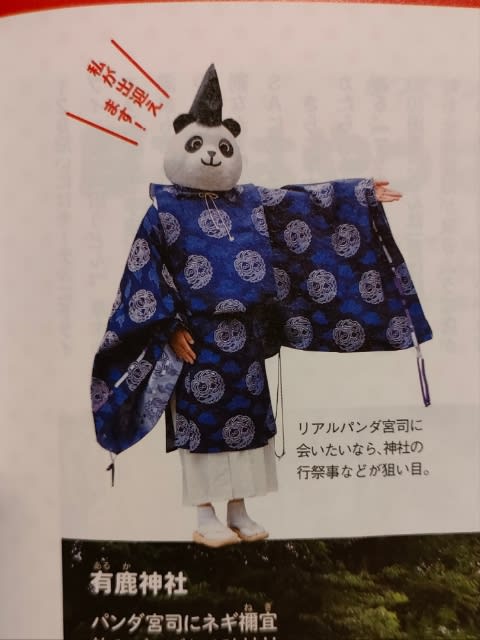











写真は当時の小田原駅付近のものですが、建物の一階部分がほぼ倒壊してしまっていることが分かります。『神奈川県震災誌』によると、小田原町では総人口約2万4千人のうち、実に1万1千余人が死傷したとあります。
相模湾では、海底に顕著な陥没と隆起を生じました。小田原海岸は地震によって約6尺(1.8m)もの高さが海底から隆起し、堤防の外に約30間(54.5m)もの砂浜が生じたといいます。
根府川では山津波(土砂崩れ)が起きて部落が埋没し、付近の海岸で遊泳していた児童数十人が海へ押し出されて行方不明となりました。熱海線の小田原発真鶴行きの列車が根府川駅構内にさしかかった時に地滑りがおきて、列車が停車場の地盤ごと海へ落ちたりもしました。
また当時、小田原町小峰(城山)の小田原城址内にあった閑院宮(かんいんのみや)邸には、閑院宮戴仁親王、同智恵子妃殿下、同寛子女王、同華子女王が滞在しておられましたが、寛子女王が倒れた建物の下敷きになって死亡しました(享年21)。今でも

小田原城址公園南側の石垣は崩れたままになっていて、当時の震災被害の凄まじさを物語っています。
未曾有の震災からちょうど100年後に生きているというのも、なかなかレアなことではあります。いつか起こるとされている南海トラフ巨大地震への警戒が呼びかけられている昨今、現在に生きる我々が100年前の災害から学ぶべきことは少なくありません。