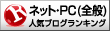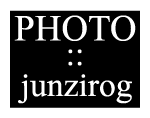今年に入って、ちょくちょくMac(PM8500)をいじっています。 この型落ち選手におまりお金をかけるのは、どうか?と思いつつ、このところの中古パソコンいじり病も伴って、ここ3、4ヵ月は結構、拍車がかかっております。 で、この夏、ついにいろいろやらせていただいたMacいじりの総決算とも言うべき、メモリの増設を挙行させていただきました。Winマシンもそうですが、やっぱり、パフォーマンスを上げるには、これが手っ取り早く、逆にこれをしないとパフォーマンスなんてそう大きく上がらないわけで、いくらCPUが速くてもメモリが少なかったら意味無しなのです。あと、細かいことを言い始めたら、ハードディスクのアクセス速度やら、ベースクロックの速さやら、いろいろあるんですが、話が早いのは、やはりメモリの増設でしょう。なので、多少貧弱なCPUでも、メモリがそこそこあれば、なんとかなるんですよパソコンは、はい。 さて、今回、書きたいのはそんなことではなく、今年に入ってから、そんなふうにかなりMacと縁が深くなっているのですが、PM8500、iBook、 iPod、と見てきて、それとやはり今までいろいろな機械もの、商品などを見てきた印象などと比べると、思ったのは、やはりアップルも「アメリカ仕事」だなぁ、と。 写真をやっていたころ、アメリカ製の印画紙やカメラなどを目にするたび思っていた感想とほぼそれに近いものを感じることができるんです。 特に、このPM8500は。 というのは、このPM8500、メモリの増設時には、ほぼ分解に近い状態(って、分解か。)にしなければなりません。匡体の外側をはずし、満員になっている拡張カードを全てはずし、スイッチをはずし、ロジックボード(マザーボード)につながっているコードを抜き、そして、そのロジックボードをごっそりはずし取るわけです。(はぁ、疲れた。) だいたい、こんなことさせること自体、設計がアメリカ仕事? で、ここまできて、こいつ(疲れさせたので、この呼び名)の中をすべて垣間見ることが初めてできたのですが、これが結構、ショックでした。「なんと、プラスチッキーなっ。」 このころのMacについて、うわさには、いろいろ聞いていましたが、実際、間近に見てみて、それなりにひどいな、と。見てはいけないものを見てしまった感じでした。 もちろん、パソコン(デジカメなどのIT関連商品もそうですが)というものは、技術の進歩がめざましく次からつぎへと新商品が出てくる部類のものであり、ペン(万年筆)やカメラなどのように「一生もの」というべき格のある商品が存在するほどの、それこそ永く使ってもらうために作っている商品がある部類のものではありません。 まぁ、たまにマニアでは古いパソコンをいつまでも使っていたりしますが(ぼく?)。 それにしても、です。 今回のこの、メモリスロット一つ取っても、「こんなんで、ええんか?」と。Winデスクトップマシン、もしくは最近のPowerMacのメモリ増設をやったことのある人なら、わかると思いますが、メモリスロットのストッパーが、メモリモジュールの切り欠きのところまで届かず引っ掛かる形状ではないんです。 おまけに、もともと、このころのPMは、永く使ってもらおうというコンセプトが開発時にあったのか、CPUをより高速の物にアップグレードが可能でした。しかし、ご存じの方もおられますが、当のアップルから、そのアップグレード用のCPUカードが発売されたのは、1回きり。そして、この造り。矛盾さえ感じ、本当にそのコンセプトがあったのかどうか、疑問です。 また、先日、iBookに関する疑問点を聞くために、電話で聞いたり、直接本体を持ち込み話を伺ったりしていましたが、今でも、製品1台1台の個体差は、数としてかなりあるようで、それに関しての問合せもかなりあるように感じました。(パソコン自体、デリケートな部品の複数の集まりですから、均質な製品づくりを高いレベルで行う事は、かなり難しいと言えるでしょうが。) と、ぐだぐだといろいろ羅列してきましたが、共通して思うことは、やはりアメリカ元来の「大量生産、大量消費」の精神が見えかくれし、簡素にできそうな部分は簡素にして、コストと手間をできるだけ少なくしようとするモノづくりの考え方が感じることができるように思います。そして、アジアの国に多い「ひとつのものを永く大切に使う」精神が、少なくともモノづくりの前提として、作る側にも使う側にも意識としてあまり存在していない国であることがわかるわけです。 ただ、そこまで思ってもやはりMacには魅力があるわけで、それはハードでもソフトでもなく、結局は、あの(ジョブスの?)コンセプトに人気があるのだろうと思うわけです。
カレンダー
最新記事
- 関西万博への懸念。
- トランプは、かまってちゃん???
- いしだあゆみ 「あなたならどうする」 =思い出す音楽 その219=
- トランプのこれからに気をつけなければならない。世界的混乱が経済だけで済むのかどうか?
- 新社会人の皆様へ。取り巻く状況は年々厳しくなっていますが、希望を捨ててはいけない。
- いしだあゆみ 「ブルー・ライト・ヨコハマ」 =思い出す音楽 その218=
- junzirogoo!!! は、おかげさまで21周年!!
- ミャンマー地震、犠牲者大幅増の可能性。
- 「すき家」は嫌いや。その2。(残念ながら3年ほど前の指摘が現実に…)
- 今日いち-2025年3月28日
- 松崎しげる 「愛のメモリー」 =思い出す音楽 その217=
- 警察署からの電話こそ信じない。そう思わせた過去の出来事。
- 地下鉄サリン事件から30年。
- 「idraft by goo」のサービス終了が残念でならない。
- 松崎しげる 「WONDERFUL MOMENT(ワンダフル・モーメント)」 =思い出す音楽 その216=
- ライバーだけの問題ではないでしょう。
- 石破総理の商品券問題に思うこと。
- もっと周りに頼っても良い優しい社会通念が浸透しないでしょうか?
- 「原子力に100%の安全ない」なら、やめましょう。
- 今日の被災地の涙を他人事と思ってはなりません。(東日本大震災から14年)
最新コメント
カテゴリー
- ひとりごと(3230)
- Weblog(62)
- 藤原新也(38)
- Apple(Mac iPhone etc...)(96)
- 大阪的広告考。(16)
- rei harakami(レイ ハラカミ)(39)
- 「美しき日々」病。(7)
- 国際・世界(40)
- 健康・病気(33)
- F1・SUPER AGURI(139)
- ペット(0)
- 映画(24)
- 芸能ネタ(16)
- 通販・買い物(69)
- 本と雑誌(12)
- 旅行記(71)
- 動画(2)
- 社会・経済(265)
- 株式(1)
- 資格・転職・就職(12)
- 坂本龍一(116)
- 日記・エッセイ・コラム(281)
- ニュース(96)
- 音楽(326)
- 写真(52)
- うんちく・小ネタ(205)
- 「冬のソナタ」病。(24)
- テレビ番組(29)
- まち歩き(49)
- 食・レシピ(52)
- DTP(14)
- 政治(179)
- スポーツ(58)
- PC(28)
- 悩み(2)
- アート・文化(42)
- デジタル・インターネット(95)
- ブログ(ブログ人)(198)
- 毎月勤労統計調査の不正などについて(2)
- 「徒然随想。」(33)
- 限定公開(0)
バックナンバー
検索
ブックマーク
- 森本敏基: PHOTOGRAPHER TOSHIKI MORIMOTO
- 東京で活躍するプロカメラマン・森本敏基氏のウェブサイト。
- わたしは価値を創る
- 経営コンサルタント・駒井俊雄氏のブログ。
- 写真日記と色々 - 写真と備忘録と日記 -
- おぽんちNote♪
- goo
- 最初はgoo ジャンケンポン!
ご利用上のご注意
2020年8月 ↓追加。
ビックカメラに関する当ブログの記述について。
このブログ上で引用されているX(旧Twitter)のポストについて。
免責事項。
ビックカメラに関する当ブログの記述について。
このブログ上で引用されているX(旧Twitter)のポストについて。
当ブログ上で引用されているX(旧Twitter)のポストの権利については、すべて、X(旧Twitter)のサービス利用規約に沿うかたちで、発言者に帰属します。
免責事項。
このブログ上のすべての記事・記述に関して、その内容の正確性・安全性、その他を保証するものではございません。また、月日の経過によって、その内容に変化が生じている場合があります。
このブログ、またはリンク先などによって生じたいかなる損害ついても、当ブログ管理者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
最新フォトチャンネル
アクセス状況
| 閲覧 | 440 | PV | |
| 訪問者 | 327 | IP | |
| 閲覧 | 2,237,751 | PV | |
| 訪問者 | 928,283 | IP | |
| 日別 | 2,264 | 位 | |
| 週別 | 3,220 | 位 | |