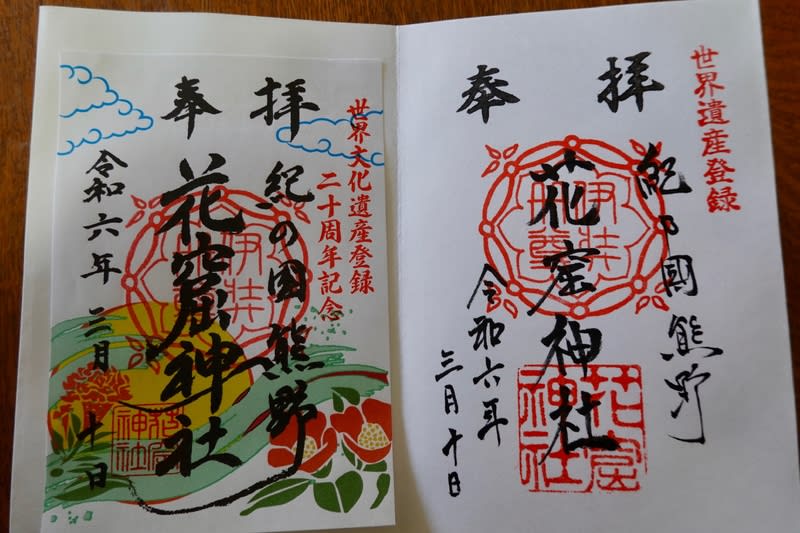この日は絶好のお出かけ日和になりました。
めざすは大原の里の奥にある古知谷 阿弥陀寺です。
実は前日にブログ仲間のtakayanさんからコメントをいただいたのですが、その中に阿弥陀寺に行かれたとありました。
阿弥陀寺では九輪草が見ごろを迎えているようです。
山が笑っています。

京都市内を抜けて大原の里にやって来ました。新緑が美しかったです。

阿弥陀寺の山門にやって来ました。2022年の秋(11/22)に訪れて以来です。

山門から本堂までは車なら3分ほどですが、歩けば10分です。道が狭いので、今回も歩きを選択です(笑)

緑の中を歩くので苦にはなりません。

静かな参道を進みます。

苔むした石仏もありました。

小さな滝もあります。

「くんしんしゅにくをきんじる」と読むのでしょうか。
要は、ニンニクなどの匂いの強い野菜や肉、酒を飲んだ者は入ってはならぬということでしょう。
昨日、餃子とビールを飲んだけど大丈夫かな(笑)

名前はわかりませんが、一面が黄色になっていました。

秋は紅葉が素晴らしい阿弥陀寺です。

苔むした石垣が歴史を感じさせてくれます。

阿弥陀寺の歴史を語ると長くなりそうなので、割愛させていただきます。

受付を済ませて本堂の前に立つと、素晴らしい景色が待っていました。

山深いところに阿弥陀寺はあります。

本堂前のカエデも新緑に輝いていました。

そして、客殿に入ると、お目当ての九輪草が咲いていました。

庭におりると見ごろを迎えた九輪草が咲き誇っていました。

今回はここまでです。次回につづきます。
※訪問日 2024.5.10
めざすは大原の里の奥にある古知谷 阿弥陀寺です。
実は前日にブログ仲間のtakayanさんからコメントをいただいたのですが、その中に阿弥陀寺に行かれたとありました。
阿弥陀寺では九輪草が見ごろを迎えているようです。
山が笑っています。

京都市内を抜けて大原の里にやって来ました。新緑が美しかったです。

阿弥陀寺の山門にやって来ました。2022年の秋(11/22)に訪れて以来です。

山門から本堂までは車なら3分ほどですが、歩けば10分です。道が狭いので、今回も歩きを選択です(笑)

緑の中を歩くので苦にはなりません。

静かな参道を進みます。

苔むした石仏もありました。

小さな滝もあります。

「くんしんしゅにくをきんじる」と読むのでしょうか。
要は、ニンニクなどの匂いの強い野菜や肉、酒を飲んだ者は入ってはならぬということでしょう。
昨日、餃子とビールを飲んだけど大丈夫かな(笑)

名前はわかりませんが、一面が黄色になっていました。

秋は紅葉が素晴らしい阿弥陀寺です。

苔むした石垣が歴史を感じさせてくれます。

阿弥陀寺の歴史を語ると長くなりそうなので、割愛させていただきます。

受付を済ませて本堂の前に立つと、素晴らしい景色が待っていました。

山深いところに阿弥陀寺はあります。

本堂前のカエデも新緑に輝いていました。

そして、客殿に入ると、お目当ての九輪草が咲いていました。

庭におりると見ごろを迎えた九輪草が咲き誇っていました。

今回はここまでです。次回につづきます。
※訪問日 2024.5.10