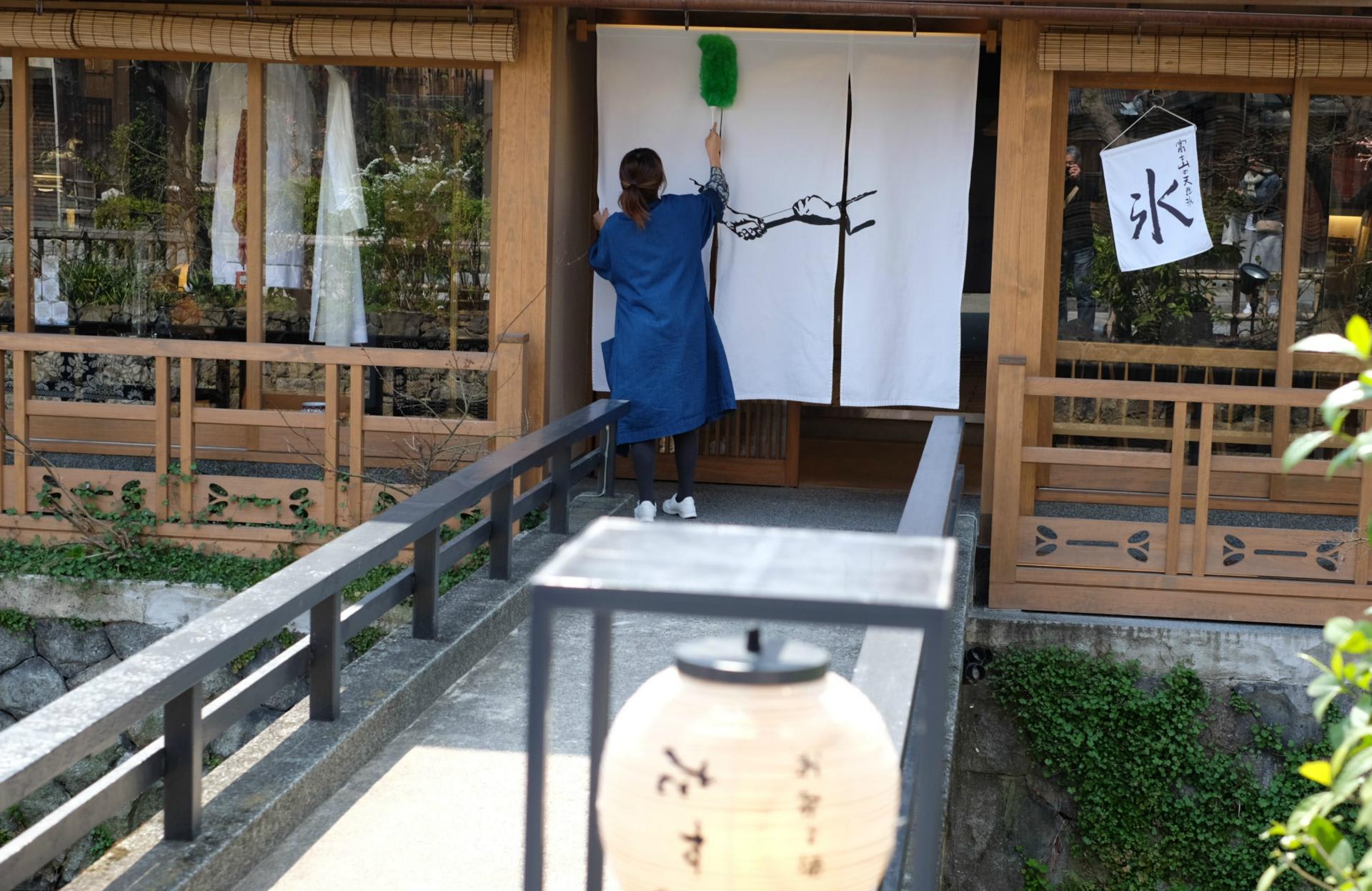前回は、松尾山から小早川秀秋の気分で戦場を眺めているところで終わりました。
今回は、松尾山を駆け下りて関ヶ原の主戦場を巡って行きます。
 (名神高速越しに松尾山を振り返る)
(名神高速越しに松尾山を振り返る)
宇喜多秀家が陣どった南天満山に向かう途中に、「不破の関」跡があります。不破の関は、壬申の乱に勝利した大海人皇子(天武天皇)が置いた関所です。このあたりは、壬申の乱でも戦場になりました。
 (中山道が通っています)
(中山道が通っています)
やがて西軍の宇喜多秀家の陣跡に着きました。東軍の福島正則の陣とは自転車で5分とかからない距離です。けっこう近い距離で両軍が向かい合っていたのが実感できます。
 (今は木立に囲まれています)
(今は木立に囲まれています)
※宇喜多秀家は、後に捕らえられますが、死罪を免れ、八丈島に流罪となりました。
宇喜多の陣から見る、開戦地です。このあたりで両軍の最初の衝突が起こりました。目を閉じると、両軍の鬨の声が聞こえてきます。
 (宇喜多の陣から開戦地を望む)
(宇喜多の陣から開戦地を望む)
 (開戦の地に建つ碑)
(開戦の地に建つ碑)
開戦の地から400mのところに、島津の陣跡がありました。
 (丸に十の字の島津の陣跡)
(丸に十の字の島津の陣跡)
※島津の軍勢は敗戦が明らかになった時、退却を開始するのですが、なんと敵の前を突っ切るという戦法を選びました。大きな犠牲を払いながらも島津義久は無事に薩摩に帰還しました。それから268年後に、薩摩は、ついに徳川を倒しました。
いよいよ、西軍の主導者、石田三成の笹尾山をめざします。
 (笹尾山への道)
(笹尾山への道)
 (石田三成の陣跡)
(石田三成の陣跡)
戦いの終盤には、ここに東軍の兵が攻め寄せたということです。(みんな三成の首が欲しかったのですね)
※三成は伊吹山めざして落ちて行きますが、やがて捕らえられ、六条河原で処刑されます。
笹尾山から最終決戦地までは、目と鼻の距離です。
 (決戦地です)
(決戦地です)
今は静かな田園風景ですが、このあたりで激しい戦いが展開したのです。この合戦での死者数ははっきりわかっていませんが、8千人にのぼるだろうと言われています。最後に首塚に合掌をしてしめくくりました。
 (建物があるあたりに家康の陣があった)
(建物があるあたりに家康の陣があった)
レンタサイクルで、松尾山の登山も含めて3時間の古戦場巡りでした。
関ヶ原の駅に戻り、14時24分発米原行きで帰路につきました。

おまけです。やっぱり新幹線を見れば撮り鉄です。

明日から4月ですね。
今回は、松尾山を駆け下りて関ヶ原の主戦場を巡って行きます。
 (名神高速越しに松尾山を振り返る)
(名神高速越しに松尾山を振り返る)宇喜多秀家が陣どった南天満山に向かう途中に、「不破の関」跡があります。不破の関は、壬申の乱に勝利した大海人皇子(天武天皇)が置いた関所です。このあたりは、壬申の乱でも戦場になりました。
 (中山道が通っています)
(中山道が通っています)やがて西軍の宇喜多秀家の陣跡に着きました。東軍の福島正則の陣とは自転車で5分とかからない距離です。けっこう近い距離で両軍が向かい合っていたのが実感できます。
 (今は木立に囲まれています)
(今は木立に囲まれています)※宇喜多秀家は、後に捕らえられますが、死罪を免れ、八丈島に流罪となりました。
宇喜多の陣から見る、開戦地です。このあたりで両軍の最初の衝突が起こりました。目を閉じると、両軍の鬨の声が聞こえてきます。
 (宇喜多の陣から開戦地を望む)
(宇喜多の陣から開戦地を望む) (開戦の地に建つ碑)
(開戦の地に建つ碑)開戦の地から400mのところに、島津の陣跡がありました。
 (丸に十の字の島津の陣跡)
(丸に十の字の島津の陣跡)※島津の軍勢は敗戦が明らかになった時、退却を開始するのですが、なんと敵の前を突っ切るという戦法を選びました。大きな犠牲を払いながらも島津義久は無事に薩摩に帰還しました。それから268年後に、薩摩は、ついに徳川を倒しました。
いよいよ、西軍の主導者、石田三成の笹尾山をめざします。
 (笹尾山への道)
(笹尾山への道) (石田三成の陣跡)
(石田三成の陣跡)戦いの終盤には、ここに東軍の兵が攻め寄せたということです。(みんな三成の首が欲しかったのですね)
※三成は伊吹山めざして落ちて行きますが、やがて捕らえられ、六条河原で処刑されます。
笹尾山から最終決戦地までは、目と鼻の距離です。
 (決戦地です)
(決戦地です)今は静かな田園風景ですが、このあたりで激しい戦いが展開したのです。この合戦での死者数ははっきりわかっていませんが、8千人にのぼるだろうと言われています。最後に首塚に合掌をしてしめくくりました。
 (建物があるあたりに家康の陣があった)
(建物があるあたりに家康の陣があった)レンタサイクルで、松尾山の登山も含めて3時間の古戦場巡りでした。
関ヶ原の駅に戻り、14時24分発米原行きで帰路につきました。

おまけです。やっぱり新幹線を見れば撮り鉄です。

明日から4月ですね。