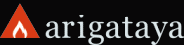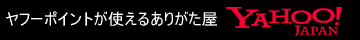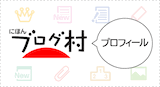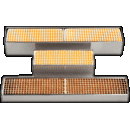薪ストーブ暮らしが大好きでブログ書いてます。
燃焼のこと、薪作りやメンテナンスのこと、そんな写真と駄文で毎日更新!
薪ストーブ|薪焚亭
ブルーフレーム

薪ストーブユーザーの全てとは言わないが、ボクを含めて薪ストーブをこよなく愛する人々は、手間ひまを惜しまない傾向にあるのではないか!? 薪ストーブは、たかが暖房器具なんだが、されどの暖房器具でもありつつ、焚付から安定継続、即ち着火と追加薪、とにかく手間のかかるものだからだ。 そんな薪ストーブ愛好家の一人であるボクが、今度これまた手間のかかる暖房器具を選択してしまった現実、これはもう笑うしかない、と言うか、そういう類の物が好きなんだからしょうがないのだ(笑)
1957年から日本に輸入されたブルーフレームは、もう半世紀以上にわたり基本的な構造、スタイル、機能の変更がないまま、せいぜいが対震自動消火装置を途中採用した程度で、現在でも販売され続けているという、驚くほどロングロングランな工業製品なのだ。
木綿の芯をいまだに使い続けていたりするなんてことも古めかしさの一つで、うっかり灯油切れに気付かないでいれば芯が燃えてしまうという空焚き厳禁の厄介な面がある。 他の灯油ストーブは燃えないガラス芯が一般的なのに、頑固?なまでに木綿芯を採用し続けているブルーフレームなのだ。 そしてもちろん着火もオートマティックじゃない。 マッチやライターがないと暖まることはできない。
こんな面倒な古臭いブルーフレームを何でわざわざ補助暖房として使おうとするのか、このことはたぶん一般的にはなかなか理解されにくいと思うが、薪ストーブユーザーのあなたならきっと解ってくれるに違いない、そんな気がしている。
現代の灯油ストーブと比較して良いところが何もない?と思われてしまいそうなブルーフレームの最大の魅力は、炎がブルーでキレイだと言うことだ。 あまりに単純な答えだが、基本的にはこの1点に尽きると思うのだ。 もちろん現在まで殆ど変わらないアンティークなデザインも良い。 ディテールに目をやれば海の向こうの匂いがプンプンしてしまう(笑)
 |
(違いについては こちら に歴代モデルについて書かれているので興味があればどうぞ)
39(Old)のデザインはシンプルな初期型に回帰しているところが何とも魅力的だ。
今回入手した39(Old)は1983年製造の物で、何とボクがまだ22歳の時のブルーフレームということになる。 日本での販売はグリーンとクリームがかったホワイトの2色なのだが、ボクは飽くまでオリジナルのグリーンにも拘った。
 |
注記:現行モデルを含めて1973年以降はライセンス生産の国産品です。
つづく・・・
いつも駄文にお付合いありがとーございます!
今日も人気ブログランキング 1クリックを何卒よろしゅうです。
薪ストーブ情報なら firewood.jp と 薪ストーブワールド
コメント ( 6 ) | Trackback ( )