甲良三大偉人
http://www.kouratown.jp/town/town01_03.html
■足利尊氏の知将として活躍したバサラ大名 http://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/40b8f0c49ba72cfb2aec28490f401d1e
http://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/0ab108c06826ee7c334b67d7f99aaa9f
■津城32万石余の大大名となった名築城家 http://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/06decefc9ab523b577634296817fd857
■日光東照宮の寛永大造替の大棟梁 http://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/05dbe3801c189a4fd64e3afc33f0cfdf
足利尊氏の知将として活躍したバサラ大名
佐々木道誉(1296~1373) 勝楽寺
 今から約700年前に滋賀県坂田郡山東町(現米原市)に生まれた道誉は、41歳の時甲良町勝楽寺に移り住み勝楽寺城を築いた。
今から約700年前に滋賀県坂田郡山東町(現米原市)に生まれた道誉は、41歳の時甲良町勝楽寺に移り住み勝楽寺城を築いた。
理由は京都の事変にすぐ応えるためであり、勝楽寺城は戦闘体制に適した土地であったからだ。
以降、鎌倉幕府の滅亡と南北朝、足利尊氏の室町幕府擁立に 活躍し、78歳で生涯をとじるまで勝楽寺を拠点とした。
エピソード1 ~ バサラ大名といえばこの人 ~
バサラ=婆娑羅とは、室町時代の流行語で「遠慮なく勝手気ままに振る舞う、派手な人」のことをいう。
この時代道誉はどんちゃん騒ぎを好み、自由奔放でバサラ大名の典型といわれていました。
特に京都の妙法院事件は有名である。
道誉の部下がこの寺の紅葉の美しさに思わずその枝を折ったことを理由に、僧に痛めつけられた。
これをきいた道誉は怒り、自ら200余りの兵を引きつれて、寺に火を放ったのである。
エピソード2 ~ じつは教養ある文化人、道誉 ~
バサラ大名といえども道誉はけっして無節操に勝手な振る舞いをしていたわけではない。
一見自由奔放に見えても道誉の行動には一本の筋が通っていた。
そのひとつが足利尊氏に対する忠実心で、もうひとつは日本の古典芸術・茶道、華道、能楽、連歌などを奥深く極めたことである。
歌集では最初の連歌撰集に道誉の81首が入り、茶の世界では道誉が選んだ茶器の中には近世になって信長や秀吉によって受け継がれた名器がある。
また能楽や狂言の保護と育成に力をそそいだ。バサラ大名道誉は、後世日本芸能の元祖といわれる教養文化人でもあった。
津城32万石余の大大名となった名築城家
藤堂高虎(1555~1630) 在士
 天文24年(1555)、現在の甲良町在士に生まれる。
天文24年(1555)、現在の甲良町在士に生まれる。
45歳の時、関ヶ原の戦いで家康に従軍し、功績をたて今治(現愛媛県)20万石の城主となる。
以後、 丹波篠山城・亀山城(京都府)の普請奉行に任ぜられ、59歳で江戸城の普請奉行となる。
62歳の時、東照宮(栃木県)の縄張りの功績で32万石余の大大名 となる。
75歳でその生涯を終え、三重県津市に葬られる。
エピソード1 ~ 15歳にして191センチの体格 ~
生まれたとき乳母一人の乳だけでは足りず、家来の女房から乳をもらった。
3歳には餅を食べ、6歳で大人の食事をし、7歳で40キロの荷物を持ち、元服の15歳には背丈が191センチもあったたくましい子どもであった。
エピソード2 ~ 誠意ある人柄 ~
生涯を通じて誠意を尽くす人であった。
若い頃仕えていた浅井家の滅亡後、豊臣秀吉の異父弟秀長に仕えたが、秀長とその子秀俊の死後、出家(僧になる)まで しようとした。
また、特に尽くした徳川家康にも、死後も奉公すると家康と同じ天台宗に宗派をかえたのも見事な献身ぶりといえる。
エピソード3 ~ 築城土木の天才 ~
高虎は築城工事にも優れていた。
秀吉時代は伊予大洲城、宇和島城、家康時代にはヨーロッパの技術を取り入れた今治城、二条城、石垣技術を生かした大坂城 (再建)、そして城主となった津城、日光東照宮などである。
家康の命で日光東照宮の大棟梁(責任者)になった甲良豊後守宗廣は高虎と同じ甲良町出身であ る。高虎45歳、宗廣28歳の時であった。
日光東照宮の寛永大造替の大棟梁
甲良豊後守宗廣(1574~1646) 法養寺
 豪華壮麗、世界に誇る近世日本建築を代表する日光東照宮は、寛永の大造替によって完成したもので、甲良豊後守宗廣を大棟梁(責任者)として造営したもので ある。
豪華壮麗、世界に誇る近世日本建築を代表する日光東照宮は、寛永の大造替によって完成したもので、甲良豊後守宗廣を大棟梁(責任者)として造営したもので ある。
その甲良宗廣は甲良町法養寺で生まれ、甲良家はもともと社寺の建築を担う大工をしていた。
30歳の時、宗廣は幕府に呼ばれ、江戸の僧上寺造営の棟梁 をはじめて務め、その後彼の業績が後世に伝えられる日光東照宮造営の大棟梁となったのである。
エピソード1 ~ 宗廣と甲良大工一門の匠の粋 ~
東照宮ははじめ、宗廣と同じ甲良出身の藤堂高虎が作事奉行として造営されたが、その後徳川家光の命により大造替工事の大棟梁に宗廣が呼ばれた。
総工費56万8千両、1日総延べ参加人数453万人、まさに徳川幕府の威信をかけた大工事は、わずか1年5ヶ月で絢爛豪華な現在に見る日光東照宮として完成した。
宗廣をはじめ、その子、その孫、そして甲良大工一門が総力を挙げて参加し、造りあげた匠の粋で群を抜いた才能の現れである。
ときに宗廣63歳のことである。
エピソード2 ~ 宗廣のとりもつ縁で・・・ ~
宗廣と藤堂高虎がとりもつ縁で、甲良町は昭和52年日光市と姉妹提携を結び、以来教育・文化・経済などの交流を通じ、お互いの友好と理解を深めている。
甲良町役場隣に建立されている宗廣の銅像と同じ像が日光市東照宮境内に建立されている。
本日も訪問ありがとう、ございます!










 石田三成の肖像画をスクリーンに映して話す田附さん(近江八幡市出町・湖灯ホール)
石田三成の肖像画をスクリーンに映して話す田附さん(近江八幡市出町・湖灯ホール)

 裃(かみしも)の家紋が「大一大万大吉」の紋である
裃(かみしも)の家紋が「大一大万大吉」の紋である 「関ヶ原合戦300年後の法要で、三成を捕縛した田中吉政の末裔が供養のために描かせたもの」
「関ヶ原合戦300年後の法要で、三成を捕縛した田中吉政の末裔が供養のために描かせたもの」

 【頭蓋骨を元に昭和51年に復顔された三成の顔】
【頭蓋骨を元に昭和51年に復顔された三成の顔】
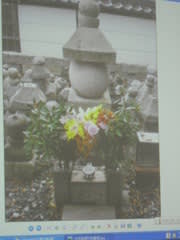
































 石田三成関ヶ原の合戦で敗れて、母の実家へ・・・
石田三成関ヶ原の合戦で敗れて、母の実家へ・・・









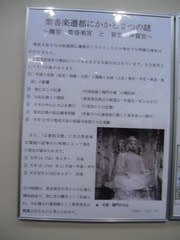





 近江国蒲生郡安土古城図
近江国蒲生郡安土古城図
 中井均・県立大学准教授を講師
中井均・県立大学准教授を講師
 レジュメ・・・
レジュメ・・・ 永源寺町内の中世城館跡分布図
永源寺町内の中世城館跡分布図 城跡周辺図・高野館遺跡(お鍋の方の屋敷=信長の側室)の石垣
城跡周辺図・高野館遺跡(お鍋の方の屋敷=信長の側室)の石垣 高野館遺跡検出遺構平面図
高野館遺跡検出遺構平面図 和南城跡の縄張り概要図「石井 均作図」2012.1.12踏査
和南城跡の縄張り概要図「石井 均作図」2012.1.12踏査 講聴者約60名
講聴者約60名













