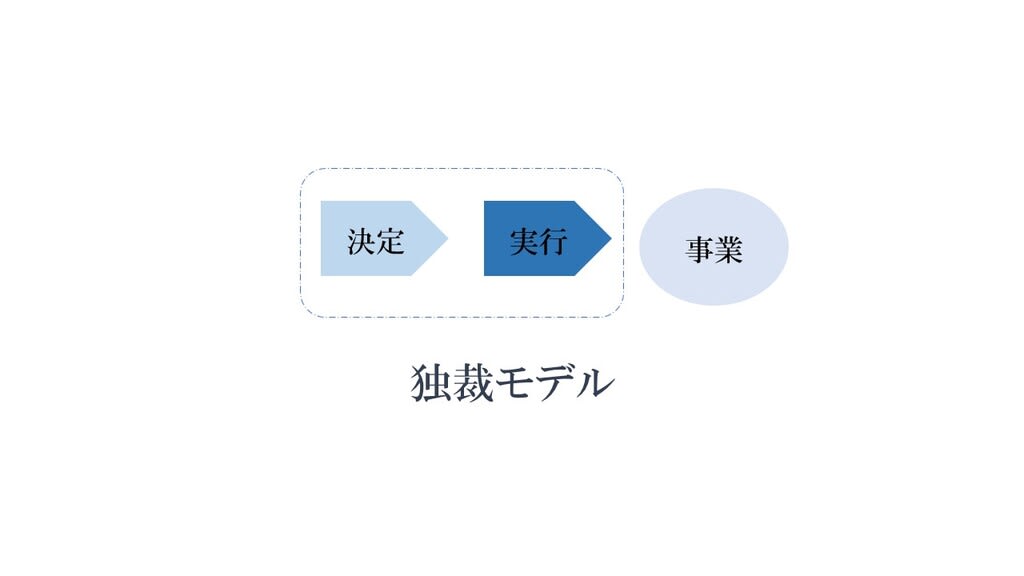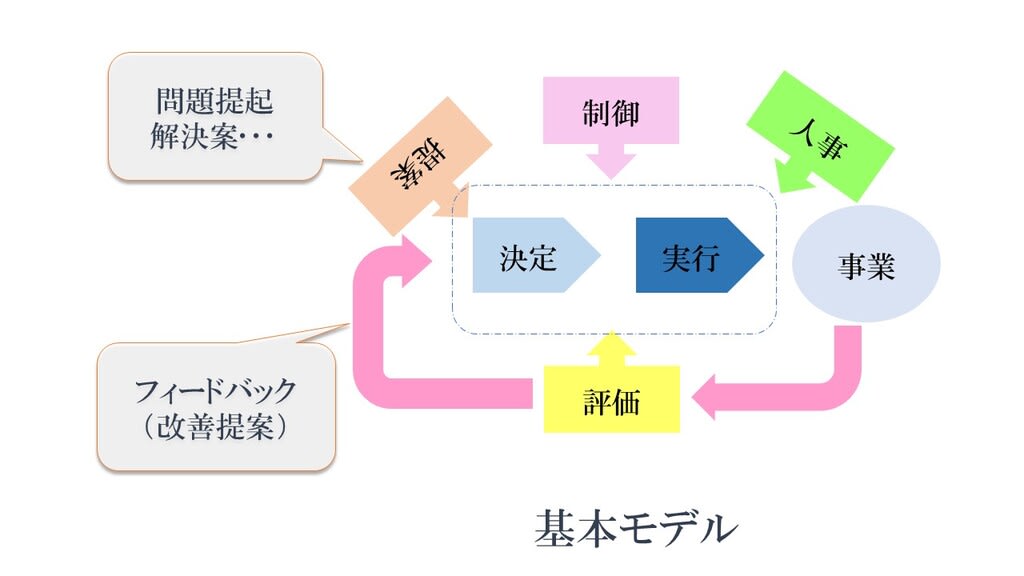1848年に世に現れた『共産党宣言』は、今日に至るまで共産主義のバイブル的な存在として読み継がれています。しかしながら、同書が掲げる政策綱領を見ましても、そこには、‘奴隷の平等’を想定しているとしか思えないような記述が見られます。そしてもう一つ、同書には、マルクス並びにエンゲルスが‘本音’が漏らしている箇所があります。
マルクス主義にあっては、国家の消滅を予測しながらも、その後に現れるべき国家、あるいは、協同体についての明瞭かつ具体的なヴィジョンが示されているわけではありません。未来ヴィジョンにおける抽象性や曖昧性が、ソ連邦であれ、中国であれ、また、他の共産主義国家であれ、共産主義革命後に出現した国家体制が非民主的な全体主義体制とならざるを得なかった要因ともされています。このため、ソ連邦の崩壊についても、共産主義そのものの失敗ではなく(政治イデオロギーとしての共産主義はあくまでも正しいとする立場・・・)、その実現手段が誤っていたとする擁護論がまかり通る余地を与えてきました。マルクス並びにエンゲルスが具体的な設計図を提示しなかったために、国権を掌握した革命家達が設計を間違えたに過ぎない、とする説です。
しかしながら、『共産党宣言』を読みますと、上述したように、共産主義国家のヴィジョンについて間接的に触れている記述があります。それは、同書第三章の「社会主義的及び共産主義的文献」の後半部分に現れます。同章では、過去や現在において唱えられてきたマルクス主義と競合する他の社会主義思想や共産主義思想を批判的に論じられているのですが、その中で、階級闘争の重要性を強調するに当たって、他の思想が提起する命題が、マルクス主義が主張する階級対立の消滅状態の別表現に過ぎないと述べている部分があります。そして、この命題の一つに、「国家を単なる生産管理に転換すること」という記述が見られるのです。
この一文を読みますと、マルクス主義における国家ヴィジョンが、経済全体が政府によって一元的に管理される体制であることが理解されます。そしてこの記述に従えば、共産主義国家の統制経済や計画経済は、まさしく同ヴィジョンを具現化したものであったこととなりましょう。全世界のプロレタリアートに檄を飛ばす『共産党宣言』の末節では、「共産主義者は、自分の意見や意図を秘密にすることを軽蔑する」とありますが、‘奴隷の平等’を意味しかねない「全ての人々に対する平等な労働強制」といい、生産管理国家への転換といい、正直と言えば正直なのですが、何故、こうしたディストピア的な記述がありながら、同思想がかくも多くの人々を惹きつけたのか、全くもってこれは共産主義最大の謎なのです。
以上に述べましたように、共産主義国家における経済の全面的な統制を伴う全体主義体制の出現は、既にマルクス主義が予定していたところとなるのですが、今日では、国家の生産管理が軍需優先に傾斜し、結果として自滅したソ連邦とは異なる方向から、共産主義国家の生産管理体制の脅威が迫っているように思えます。それは、一党独裁体制を堅持する共産主義国家である中国が、国家の総力を挙げて取り組んでいる、先端技術の研究・開発並びに同テクノロジーを搭載した製品の輸出攻勢です。かつてはハイテク製品の原材料としてのレアアースを経済的戦略物資に位置づけていましたが、今日では、太陽光パネルといった再生エネ発電装置、EV、ドローン、半導体などの製品や部品において大量生産を開始し、技術の先進性と低価格を武器に世界市場を席巻しようとしているのです。自由貿易主義、あるいは、グローバリズムは規模の経済が強く働きますので、政府が掲げるアグレッシブな産業戦略の下で特定の成長産業への集中投資や傾斜生産が可能となる共産主義体制にとりまして、競争上、極めて有利な状況にあると言えましょう。
突出した輸出競争力をもつ中国製品につきましては、アメリカであれ、EUであれ、ようやく高率の関税をかけることで防波堤を築きつつありますが、関税並びに非関税障壁を問答無用に‘悪’と見なす自由貿易主義やグローバリズムが、経済大国のみならず、先端技術の転用も手伝って軍事大国にしてデジタル全体主義国家をも育て、諸国の安全まで脅かしているとしますと、人類にとりまして、この路線をそのまま歩み続けることが正しいのか、現実を直視した上で考えてみる必要があるように思えます。横暴な強者に無制限な自由を与えるとどうなるのか、人類は、既に歴史の教訓として学んでいます。そして、自由貿易主義もグローバリズムも、共産主義を誤認して好意的に解釈したのと同じように、多くの人々の誤解の上に推進されているかも知れないのですから。