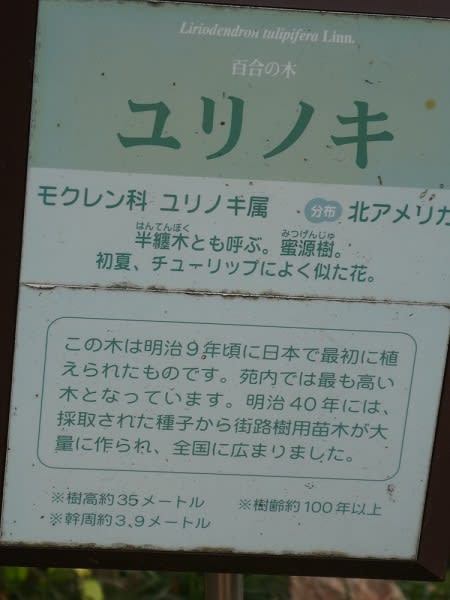結局、6畳間は畳床ごと全部新しくしました。
そこにあった小さな観葉植物もこの部屋(と2階)にきて、夏みかんの木にかけてあったポトスも
取り込みました。これで外に出してあった観葉植物の取り込みは終わりました。

観葉植物とは全然関係ないのですが、19世紀ロシアの作家ツルゲーネフの本をぱらぱら見ていたら、
「犬(サバーカ)」というタイトルの詩がありました。
詩に描かれている人間と犬との信頼と愛の関係は、家族の愛に恵まれなかった孤独で少々優柔不断なツルゲーネフならではのものでしょうか。
ツルゲーネフにとって犬はつねにいつまでもどこまでも信じられる存在だったのでしょうね。人間であること、動物であることを超越した存在として犬と対することは、多分、当時は珍しかっただろうと思います。
犬
部屋のなかに私たちふたり、犬と私と。外は、荒れ狂う嵐が
うなり声をあげる。
犬は私の真向かいに座り、まっすぐに私の眼を見つめる。
私も犬の眼を見る。
犬は私に何か言いたげだ。犬は口がきけず、言葉をもたず、
自分を理解できない。だが、私は犬のことが分かる。
私は知っている、この瞬間犬と私にはまったく同じ感情が
息づき、ふたりの間にはどんな違いもないことを。私たちの
心はひとつだ――それぞれの中にまったく同じおののく炎が
燃え、輝いている。
いつか死が、この炎めがけて冷たく大きな翼で襲いかかる…
それで、終わりだ!
あとになって、私たちそれぞれの心にどんな炎が燃えていたかを
誰が知るだろうか?
いや、動物と人間が眼差しを交わしているのではない……
たがいに見つめあっているのは二対の同じ眼だ。
動物と人間の、それぞれの一対の眼の中で、生命(いのち)が
そっとひとつになって寄り沿う。(1878)
ツルゲーネフは1818年、ちょうど200年前にロシア中部のオリョールで生まれ、1883年にフランスで亡くなりました。私は1989年にオリョールのかつての彼の広大な領地、今はツルゲーネフ博物館になっているスパスコエ-リトヴィノヴォを訪れたことがあります。5月だったので、屋敷の窓は日向のタンポポの黄色と日陰の忘れな草の空色が映っていました。
革命前の貴族の屋敷には必ず犬たちが飼われていました。貴族たちは猟を楽しみましたから、猟犬は必ず複数いました。あと、番犬や、愛玩犬もいました。ツルゲーネフは物ごころつかないころから、犬とともにいたことでしょう。
彼には『ムムー』という短編があります。そこでは耳が聞こえず、しゃべれない農奴と犬が描かれています。これは今でも人気のあるお話しです。ムムーの最後が悲しいので私は繰り返し読む気になれませんが、ハッピーエンドにしなかったからこそ、今も読まれつづけるのでしょう。






















 、暗くなってきたし、雨も降って来たし、あとから家を出た夫が電気をつけていったか心配で(暗がりだとジュリアが不安になるので)ホテルに寄らずに戻ってきました。
、暗くなってきたし、雨も降って来たし、あとから家を出た夫が電気をつけていったか心配で(暗がりだとジュリアが不安になるので)ホテルに寄らずに戻ってきました。