先日のネットニュースで、「現実逃避をするため映画館に行く人が、5人に2人いる」らしいと知りました。ロイターが23カ国2万4千人を対象に調査したそうで、現実逃避派ではトルコ67%、インド61%、韓国54%、日本41%。NOで多いのはハンガリー76%、オランダ・メキシコ74%、スウェーデン71&、ドイツ70%とか。お国柄による違いはよく解りませんが、映画の興行収入はメガヒットシリーズのパワーもあって、全体的には伸びているそう。不景気のとき、手軽なレジャー&現実逃避に映画館へ行く人が増える、というのは、なんとなく理解できますよね。
私の場合、映画館へ通う動機は、「現実逃避」と「創作刺激」を求めることが半々ぐらいかな。『ポニョ』とか『アバター』みたいなメジャーなヒット作を観るときは完全に「現実逃避」。そこそこのヒット要素が確保され、お金を払っても後悔しないと担保されているレベルの作品を何~にも考えずに観る。映画館という隔離空間で時間を過ごすことが目的になります。
今週はそうではなく、久しぶりに純粋に「創作刺激」を求めて3本立て続けに観ることができました。私にとって、静岡市内の映画館で同時期に3本も「創作刺激」をくすぐられる作品を観られるなんて滅多にないことで、本当にラッキーな週でした。
1本はアカデミー賞を獲った『ハート・ロッカー』。戦争モノってヒーローの武勇伝か、ドンパチをリアルに描いて人間の狂気をえぐり出す・・・なんてパターンが多くて、戦争を知らない世代にとっては、どこか遠い世界の遠い時代のお話、でしたが、この作品に描かれた戦争は、等身大の痛みや、痛みが麻痺してくる怖さをまざまざと実感させてくれました。
爆弾処理の仕事って、究極の「他人が嫌がる仕事」ですよね。これを請け負う人間の「もうたくさん」「あと何日で解放される・・・」という思いと、「他人がまねできない仕事」「現場に戻ってこそ自分の存在意義がある」という思い・・・。戦場を「職場」に、戦争を「仕事」に置き換えてみると、すごく伝わってきます。イラク戦争を、いわゆる戦争映画風ではなく、若者の自分の身の置き場として描いたことで、戦争が現代の若者を当事者とした現在進行形の出来事だと伝わってくる。・・・そのことが、現代の戦争の惨さを一層際立たせるのです。
戦争という、一般人から見たら非日常の世界を、一般人が日常感覚を掘り起こしてまで感じ取れる映像というのは、もしかしたら、政治や経済なども日常サイズで咀嚼して理解できる女性だからこそ撮れたのかな・・・とも思います。監督は「女性監督」という紹介のされ方を嫌がっているみたいですが、私は純粋に、こういう作品を女性が撮ったということに感動できました。
2本目は『チェイサ―』。私の大好きな韓国クライムサスペンス『殺人の追憶』に通じる作品で、静岡では未公開でしたが、シネギャラリーでこの1週間だけ特別上映されたのでした。
話の骨格は連続殺人犯と元刑事の、単純と言えば単純な追走劇なんですが、警察組織の建て前とか、粗暴な元刑事の隠れた人間味とか、動機が見えない殺人犯の不気味さとか、プロットとしては日本の刑事ドラマなんかにもありそうだけど、なぜだか日本では絶対に作れない映画だなって思えます。
映画評論家のようにうまく言えないのですが、『殺人の追憶』にも共通する、ジメジメとした湿気や、映像が醸し出す臭いを、スクリーン上のことなのに体感させられ、嫌悪感さえ覚える。・・・でもスクリーンから目が離せない。最後の最後まで心臓がドキドキする思いは、映画館では久しぶりの経験で、お気楽「現実逃避」のつもりで観に行ったら、エライことでした。たぶん、骨ある映像クリエーターなら、映画で観客にそんな体験をさせる作品を撮れたら!と思うでしょう。監督はこれが長編初メガホンの若手だそうですから、韓国の映像クリエーターの底力は末恐ろしい・・・。
3本目は『バクダッド・カフェ』。ライター稼業に就いたばかりのころ、映画通の友人ライターに薦められて観た作品で、20年ぶりにニューディレクターズカット版が公開されたのでした。20年前は、太ったドイツのおばさんと、更年期みたいな黒人カフェ女主人の組み合わせがとにかく斬新で、それにあの印象的な主題歌「コーリング・ユー」・・・。なんとも不思議な世界観に、「こういう映画の良さが理解できれば映画通になれるのかしら」などと背伸びして観たものでした。
ニューディレクターズカット版は、色彩が鮮やかで、上質な絵画を鑑賞しているよう。音楽はコーリング・ユーの印象が強すぎたのですが、バッハがこんなにも効果的に挿入されていたのかと再発見し、監督の色調と音へのこだわりが作品の世界観を創る大事な要素だったんだと改めて理解できました。
シナリオも、シンプルでとてもいい。ドイツのおばさんがなぜアメリカ西部の砂漠に来たのかも、砂漠のモーテルに集う怪しげなお客たちの素性もいっさい説明なし。カフェの女主人だけが、いびつな状況にいきり立っていて、終始怒鳴り散らしている。彼らが相互理解していく過程には、とくに大きなドラマはないのだけれど、人は、人に理解してもらいたい、理解し合いたい生き物なんだって自然に伝わってくる。・・・とくに『ハート・ロッカー』や『チェイサ―』を観た後に、これを観ると、なんだか癒しエステに来たみたいにホッとします。
映画館は、閉ざされた空間で他人と同じ空気を吸っているのに、ふだんの生活ではなかなか経験しないような感情が高ぶる、揺さぶられる体験ができる不思議な場所です。
それが「現実逃避」といわれるならば、街中で、こんなに気軽に「逃避」できる場所があるなんて、幸せなことですよね。











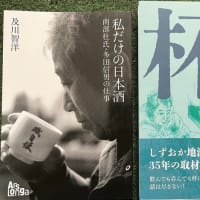




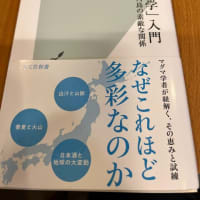

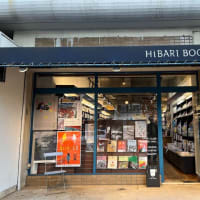

下記のURLから、相互リンクしてもらえると嬉しいです。
http://hikaku.link-z.net/link/register.html
ご迷惑だったらすみません。突然、失礼しました。
9kcjwjlo