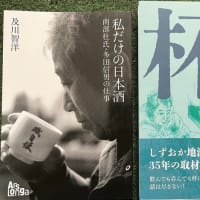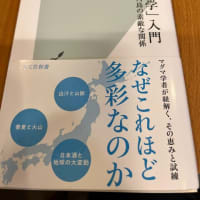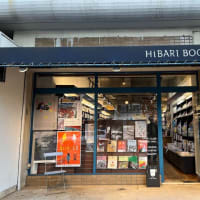私が主宰する駿河茶禅の会で、今年10月に福岡博多研修を計画しています。昨年、富士山静岡空港利活用促進事業に応募し認可された静岡空港出雲線を利用しての松江出雲研修に引き続き、今回は福岡航路を利用しての茶禅研修です。
博多と静岡とお茶といえば、なんといっても円爾弁円=聖一国師(1202~1280)。静岡市の藁科川中流の栃沢に生まれ、久能寺、園城寺(滋賀)、長楽寺(群馬)、寿福寺(鎌倉)等で修行した後、34歳のとき宋国に渡り、40歳で帰国。大宰府崇福寺、肥前万寿寺、博多承天寺の開山となって九州を拠点に禅道布教を始め、やがて関白九条道家に請われて東福寺(京都)の開山となりました。43歳のとき、かつての修行先・上州長楽寺へ帰朝の挨拶に出向いて、その帰路に故郷栃沢に立ち寄り、宋から持ち帰った茶の種子を足窪村へ播種したと伝わります。今までは単に「静岡にお茶を伝えた偉いお坊さん」というイメージしか持っていなかったので、今回を機に禅宗史における聖一国師の存在をしっかり学べたらと思い、いろいろな文献を読み漁っているところ。研修の資料作り程度の整理が出来たらこのブログでもご報告します。
今回ご紹介するのは、過去に駿河茶禅の会で訪ねた京都の大徳寺、堺の南宗寺、松江藩主松平不昧に関わり深く、博多にもその足跡が残る千利休の禅の師匠・古溪宗陳(こけいそうちん 1532~1597)です。越前の生まれで、大徳寺102世住持の江隠宗顕(こういんそうけん)、107世の笑嶺宗訢(しょうれいそうきん)に師事し、42歳で大徳寺117世となります。古溪の大徳寺住持就任時には千宗易(利休)が一族を挙げて出資をし、津田宗及や油屋紹佐など堺の豪商が祝儀を寄せています。住持期間は1年でしたが、退職後も茶人や豪商からの帰依者が多く、織田信長が本能寺で斃れた後、秀吉が信長の菩提寺として創建した大徳寺総見院の開山に就きました。
天正13年(1585)千宗易は、秀吉が正親町天皇を招いて開く禁裏茶会に参加するため、利休居士の称号を賜ります。いくら名高い茶人であっても町の納屋衆(倉庫業者)が宮中に上がることはできませんが、居士(仏徒)であれば大丈夫だからです。『利休』の名付け親は大林宗套(だいりんそうとう 大徳寺90世・南宗寺開山)と言われていますが禁裏茶会開催の17年前に入寂しており、本当の名付け親は利休の参禅の師であった古溪ではないかという説もあるとか。
そんなこんなで茶の湯の世界で広く人徳を得ていた古溪が、天正16年(1588)に突然、秀吉から博多への配流を命ぜられます。原因は古溪とソリが合わなかった石田三成の讒言だとか。なんだか政治ドラマみたいで面白いので、以下、花園大学の竹貫元勝教授の著書『古溪宗陳ー千利休参禅の師、その生涯』を参考にまとめてみました。

当時、古溪は秀吉から紫野船岡に天正寺、東山に大仏殿方広寺の造営を任されていたのですが途中で中止となり、紫野には天瑞寺という別の寺がわずか2か月で建てられました。この寺は秀吉が母大政所の病気平癒を祈願して建てたもので、開山は古溪ではなく玉仲宗琇という大徳寺僧。当時の大徳寺には「北派(大仙派)」「南派(龍源派)」「龍泉派」「大模下春作禅興派」という4つの派閥が存在し、各派閥から順番にトップ住持を輩出しており、最大派閥は南派。玉仲は古溪よりも5代前の南派出身住持でした。古溪が属する北派は住持になった者は多くはありませんが、堺の豪商・茶人がバックに付いていて、住持就任に必要な経済的支援も担っていました。これに対し、最大派閥南派は堺以外の地方の戦国大名を外護者につけていて、全国の派閥寺院から弟子を多く集め、勢力を蓄えていました。そこで、茶の湯に傾倒し古溪を偏重していた秀吉に対し、母の大政所が「最大派閥を敵に回さないように」とアドバイスをしたらしいのです。
古溪は当初指示されていた天正寺造営のため、堺の豪商たちに寄進を求めていたのですが、思うように集まらず、その過程で石田三成とギクシャクし、もたついている間に天瑞寺が創建されてしまい、ライバル南派の玉仲が開山に任命されたことで自分の立場が危うくなったと実感したでしょう。石田三成との間に何があったのか具体的にはわからないようですが、「三成の讒言は秀吉を納得させるだけのものがあったと思われる」と竹貫教授。
天正16年(1588)、57歳で博多にやってきた古溪は、彼を慕う小早川隆景や博多の豪商らの庇護のもと、茶会や散策をして心穏やかに過ごしたようです。彼は日本に最初に茶を伝えた栄西禅師が開いた日本で最初の禅寺・聖福寺を訪ね、さらに当時大宰府にあった崇福寺にも足を延ばします。前述のとおり駿河栃沢生まれの聖一国師が開創し、駿河井宮生まれの大応国師(南浦紹明)、そして大応国師の弟子で大徳寺を開いた大燈国師(宗峰妙超)が入寺した名刹で、大徳寺住持を経験した古溪にとっては感慨深かっただろうと思います。崇福寺は後に黒田長政によって博多に移されました。
今回の我々の博多研修では、古溪が滞在した大同庵跡をはじめ、崇福寺、聖福寺にも足を延ばす予定です。
博多配流生活は2年。天正18年(1590)に京都へ戻った古溪は、翌天正19年1月に亡くなった秀吉の弟・豊臣秀長の葬儀の導師を秀吉たっての依頼で務めます。そして秀長の菩提寺大光院(奈良)の開山にも就任し、秀吉から金襴の大衣を賜ります。手のひら返しのような厚遇ですが、博多蟄居中も秀吉から厳しく監視されていたわけではなく、竹貫教授は「秀吉には禅的精神文化への高い関心があり、古溪は秀吉の精神的欲求を満たす上で多大の貢献をした一人」「秀吉は形の上では三成の讒言を聞き入れ配流にしたが、もともと博多に関心があり、古溪は秀吉のその意を汲んで活動していたのでは」と読み解きます。
ところが秀長葬儀直後の2月28日、千利休が秀吉の逆鱗にふれて切腹するという一大事が起こってしまいました。大徳寺の山門「金毛閣」に千利休の木像が安置されたことが直接のきっかけと言われ、秀吉は大徳寺をつぶし、僧を磔にするとまで言い放ったとか。僧の磔は大政所や秀長未亡人がなだめて却下させたものの、大徳寺には徳川家康、前田利家、前田玄以、細川忠興の4人が秀吉の使者となり「破却」を言い渡したところ、これに対峙し「貧道は先ず死有らんのみ」と死ぬ覚悟で抗議したのが古溪でした。4人から報告を受けた秀吉は、大徳寺破却を思い留まります。愛弟子利休を救えなかった古溪としては、それこそ命がけで大徳寺を守ったんですね。
晩年の古溪は病身をおして千利休の墓がある大徳寺聚光院の住持を務めます。そして慶長2年(1597)66歳で示寂。翌慶長3年に秀吉が亡くなります。古溪が生前残した言葉をまとめた語録『蒲庵稿』は江戸時代に出版され、古渓を敬愛する大名茶人松平不昧が序文を寄せています。
茶道の歴史をかじっていくと、一度は目にする古溪宗陳の名。彼を挟んで秀吉や利休の言動を追ってみると、生々しい人間関係が見え隠れし、また一つ、歴史を学ぶ面白さを実感します。博多研修が終わったら現地レポートしますね!