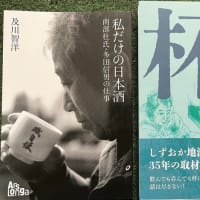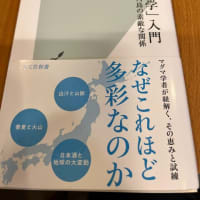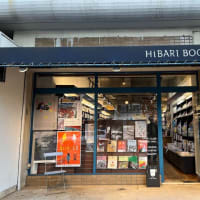正月明け締め切りの仕事にメドがつき、ゆうべ、年末にネットレンタルしていた『不都合な真実』を観ていたら、3年前のアラスカ旅行のことを思い出しました。
氷河クルージングをしたとき、目の前のラッコの大群と、氷河が勢いよく崩れ落ちる光景に多くの観光客に交じって喚声を上げていた私ですが、考えてみれば喜んで眺めている状況じゃないんですね。
アラスカには当時、現地で看護師をしている妹が、連邦海洋大気局(米国の気象庁)に勤めるアメリカ人の夫と住んでいました。妹の家では、ごみの分別をまったくせず、生ごみも燃えるごみもペットボトルも空き缶・空き瓶も、みんなひとつのダストボックスにポンポン捨てます。
2週間あまり滞在して感じたのは、「人間が生活するスペースなんて微々たるもの、少しぐらいごみが出てもなんら影響がない、それだけ圧倒的に自然が支配している土地なんだ」ということ。自然保護の必要性を切迫感を持って感じるようになるには、まだ余裕がある、ということでしょうか。確かに日本でも、都会ほど、ごみ分別が厳しく、地方ではまだ、燃える・燃えない程度の分け方しかない土地もありますよね。
それでも、アラスカにも油田ルートの大規模開発等で、都会化の波は否応なしに押し寄せるわけで、ごみ分別不要の暮らしがいつまで続くのか気がかりです。
アラスカで撮った写真ファイルを久しぶりに紐解いたら、帰国後、静岡コピーライターズクラブの仕事展に出展した自作の詩がファイルの中に混じっていました。タルキートナというのはアンカレッジから北へ180キロほど上った、マッキンリー登山口の村で、ちょうど、独立記念日のささやかなパレードを見ることができました(昨日の『ひまわり』に引き続き、まったく季節感を無視した内容ですみません)。同業者から珍しく「いい詩ですね」と褒められたことを思い出し、再掲しようと思います。
時計の針は午前零時を指そうとしている。
窓の向こうは白濁とした陽光を漂わせている。
マッキンリー山の登山基地として知られるタルキートナは、ゴールドラッシュやアラスカ鉄道開通で沸く開拓時代の残影を持つ、人口800人の小さな町。そして植村直己が最後に立ち寄った町だ。
2005年7月4日は一日中、雲に覆われ、白くどんよりした日だった。独立記念日のお祝いに花火が上がると聞いて、空の色が変わるのを待ち続けた。日付が変わろうというのに空は何も応えてくれない。
不意に、ポンポンと空砲が鳴った。光も色もない煙火の乾いた爆発音。あっという間の出来事だった。ワシントンDCにいる妹が首都の花火大会の華やかさを電話で伝えてきたが、アラスカの空は何も変わらなかった。
開拓者がやって来る前の静けさは、この空の下のどこかで凍りついたまま眠っている。独立記念日のない国の登山家も、どこかで一緒に眠っている。
音だけのささやかな花火は、彼らの眠りを妨げない、ささやかな心遣いであればいい。