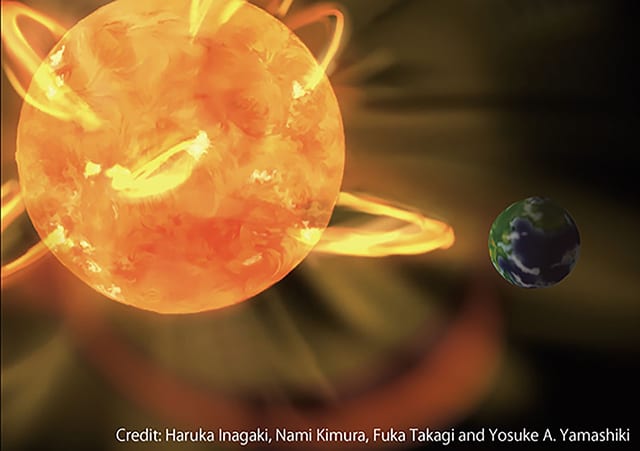2023年9月6日更新
ツーリングでスマホをナビやマップ表示に使っていると熱暴走することってありません?
特に気温が高い夏のツーリングは、スマホの温度が上昇しやすいので要注意。
気付くとスマホの画面が真っ暗っということもあり得ます。
自分が使っているのはHUAWEIの“Y6”というロースペックなスマホなので防水には未対応。
雨が降ることを考えるとスマホはケースに入れて使うことになります。
夏場はこのケースに熱がこもって温度が上昇… しばしばスマホが強制終了してしまうことがありました。
そこで、今回は夏ツーリングで熱暴走なく活躍してくれるスマホの選び方を書いていきます。
色々と考え、財布と相談したうえでタフネススマートフォンを購入しました。
 |
スマホの温度が上昇する原因
気温が高く、スマホの温度が上昇しやすい夏のツーリング。スマホの温度が上昇する原因を考えてみると、主な原因は3つになると思います。
- スマホを充電しながら使っている。
- スマホ本体に直射日光が当たっている。
- 急な雨に備えてスマホはケースに入れて使っている。
2~3時間の走行だと大丈夫ですが、日帰りツーリング以上だとバッテリー切れが心配。
どうしても走行中の充電が必須になってしまいます。
この充電によりバッテリー自体が発熱することになります。
バッテリー交換可能なスマホだと予備バッテリーを購入するのもいいかもしれません。
意外と盲点なのが直射日光による温度上昇です。走行中は風が当たっているので油断しがちですが、スマホが日に当たっていると本体はけっこう熱を持ってきます。
スマホが防水でないと、急な雨のことを考えてケースに入れてしまいがちです。
ケース内に熱がこもって排熱ができないので注意が必要です。
スマホの温度が上昇してしまったら…
よく言う熱暴走ですね。
手っ取り早いのは、電源を切る、充電をやめるです。
直射日光に当たっている場合はカバンの中へ。
保冷剤を当てるなど、急速に冷却してしまうと、スマホ内での結露の発生により故障の原因になってしまうのでお勧めしません。
よく言う熱暴走ですね。
手っ取り早いのは、電源を切る、充電をやめるです。
直射日光に当たっている場合はカバンの中へ。
保冷剤を当てるなど、急速に冷却してしまうと、スマホ内での結露の発生により故障の原因になってしまうのでお勧めしません。
温度の上昇を対策する
温度上昇の対策を考えてみました。- なるべく充電時間を短くする。
- 日差しを付けて直射日光を当たらないようにする。
- ケースは使わず防水対応の機種を使う。
さらに、低消費電力のSoC搭載スマホを選ぶことで、バッテリーの消費と発熱を抑えることもできます。
直射日光は日差しを付けて対策するしかないかも。
あと、スマホはブラック以外の色を選ぶのもありです。
防水対応の機種を選べばケースに入れなくても急な雨に対応できます。
雨が降ったら水冷効果も期待できます。さらに防塵対応だったりすると心強いですね。
ただ、防水対応の機種は密閉性が高く熱がこもる傾向にあるので、少しでも発熱を低くするため低消費電力のSoCがおすすめです。
選んだスマホはタフネス仕様
ちなみに、スマートフォンによく採用されているクアルコムのSoCだとこんな感じでシリーズ展開されています。ハイエンド性能の“Snapdragon 8シリーズ(800番台)”
最上位クラスのSoCなので、普段使いのWebや動画の閲覧などはもちろん、4Kや8Kの動画の撮影や3Dゲームのぷれいなど高負荷な処理を含む用途でも快適に使用できる。
ただ、それなりにバッテリーの消費と発熱は高くなる。
コストパフォーマンスに優れた“Snapdragon 6/7シリーズ(600番台/700番台)”
ミドルレンジクラスのSoCとしては、Snapdragon 6シリーズ(600番台)とSnapdragon 7シリーズ(700番台)があります。
Snapdragon 7シリーズの方が性能は高めでハイエンドに近い性能。
4Kや8Kの動画撮影や3Dゲームなどをしないのなら十分な性能を持っている。
エントリークラスの“Snapdragon 4シリーズ(400番台)”
性能控えめなエントリークラスのSoCで、WebやSNSなどライトな使い方なら十分使える。
2~3万台の価格帯で帰る機種が多く、型落ちならさらに安くなっている。
自分はマップ専用(googleマップ、YAMAP)と割り切って中古のスマホを購入。
マップ専用なので、ミドルからエントリークラスのSoCを搭載した機種で十分と考えました。
その結果、熱対策を考慮して選んだのは、パナソニックのタフネススマートフォンTOUGHBOOK P-01K。
エントリークラスよりもさらに下のSoCを搭載しているスマートフォンです。
2018年10月に発売された無骨なドコモ端末で、 端末の性格上、もちろんブラック以外の色展開は無しでした。
購入の決め手は以下の通り。
バッテリーの交換が可能で、SoCは途上国向け低価格端末に搭載されることを前提にしているSnapdragon 210。
CPUがQualcomm MSM8909(1.1GHz)クアッドコアとかなりロースペックなSoCなので、低消費電力と低発熱が期待できます。
米国国防省の軍用規格“MIL-STD-810”の試験17項目に準拠しています。
落下、衝撃、振動、風雨、侵漬、湿度、粉塵(砂塵)、耐日射、高温運転、高温保管、低温運転、低温保管、温度衝撃、着氷/凍結性降雨、凍結融解、低圧力運転、低圧力保管
もちろん、防水対応なのでケースに入れず使っていけます。耐衝撃・耐振動・防塵・直射日光・高温運転などの試験をクリアしているので、バイクツーリングならではの運用でも力を発揮してくれはずです。
あとはツーリングで役立ちそうな機能の紹介。
本体の両側面にあるカスタマイズ可能なショートカットボタンは、画面をタッチしなくてもアプリを立ち上げたりできるので便利かも。
水に濡れた手や手袋装着時でもタッチ操作可能な機能も付いています。
他機種での評判によると、この手の機能は微妙なことが多いようですが…
6980円と安かったので中古端末を購入。キズも全くない良品を手に入れることができました。
純正の電池パック(容量3100mA)は、リアカバー一体式で8,900円と少しお高めなので、ツーリングで使用してから購入の判断をしようと思います。
3年ほど使って感じたのは、少し動作が遅いけどマップ専用として十分使えるということ。
さすがはSnapdragon 210です消費電力や発熱は少ない感じ。
ツーリング(googleマップ)では電源ケーブルを挿して使ってます。
ケース無しの運用で発熱は気にならないけど、直射日光が当たるとそれなりに熱くなるかな。
登山ではYAMAPを使っているけど、フライトモードだと1日は十分に持ちます。
発熱は、ぜんぜん気にならないレベルです。
雨が降っても気にせず使えるのがいいですね。
TOUGHBOOK P-01Kを使い始めて分かったこと
本体を手にとって思ったのが、思っていたほど大きく無く、重くないなぁー っということ。さっそく充電しながら、初期設定とアプリのインストールを始めていきます。
“OCN モバイル ONE”のSIMを入れてAPNの設定をするとドコモの電波をつかんでくれました。
入れたアプリはGPS Status、YAMAP、GPS Test、Yahoo!天気、Edge。
“GPS Test”を表示させると、“P-01K”はアメリカのGPSとロシアのGLONASSに対応していることが分かります。
測位が速く、精度も問題なし。
一瞬喜んだのは、衛星のID 193・194・195が表示されたこと。
みちびき(初号機・2号機・4号機)を認識しているんですねー(日本の国旗が表示されてました。)
ただ、他の項目がブランク… 残念ながらデータの取得はできてないですね。
 |
あとは、ツーリングで使ってみてどうなるか?
ツーリング中はGPS ONでGoogleマップを表示させた状態にしているので、バッテリーの減りは気になるところです。
タフネススマホを持つのは初めてのことなので、ツーリングや登山にも持っていきたいですね。
こちらの記事もどうぞ