「工場から製造コミュニティー、メード・イン・イタリーの町へ」建築家ルーカ・セーヴィ氏講演会リポート(2015.2.25)@イタリア文化会館
2015年2月25日(水)夜 イタリア文化会館にて「工場から製造コミュニティー、メード・イン・イタリーの町へ(Dalla fabrica alla comunita' produttiva alla citta' del Made in Italy)」というテーマで 建築家ルーカ・セーヴィ氏の講演会が開催されました
氏が2012年ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展で行った展覧会「メード・イン・イタリーの建築」展で取り上げたテーマを掘り下げて論じました
メード・イン・イタリーの企業にとって 働く環境のクオリティは 洗練された生産システムとともに 優れたもの作りの重要な要素です
社屋や工場の建設は 進出する地域の再活性化に貢献します
こうした企業進出は その町の計画の有効活用において 歴史や文化を高める経済再生の鍵となることを示しています
* * *
講演会 講師:ルーカ・ゼーヴィ氏(建築家・都市計画家 歴史的地街区の再活性化や古い建物のリノベーションを専門とする)
日 時:2015年2月25日(水) 18:30~
会 場:IIC アニェッリホール
テーマ:工場から製造コミュニティー、メード・イン・イタリーの町へ
建築関係に詳しいゲストのM氏より 早速講演会のリポートが届けられました:
*講演概要(取材していた訳ではないので、全ての内容を把握していません)
2012年ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展の中で (当時)経済危機の中で 私達は建築家としてどのように貢献できるかを取り組んだ
1960~70年代では大きな(大規模)企業が成功し 80年代には中小企業 しかも大都市ではなく地方都市・中・小規模都市で台頭するようになり 「Made in Italy」としての伝統の力 職人の手になる成果を挙げてきた
しかも製品の品質向上を目指して来た
リーダー達が 工場建屋の中で 単に自社製品だけでなく 製品を作り上げる建屋の建設も又大事であると思うようになった
東京・表参道界隈の産業の製品への取組み姿勢・PRのあり方を見ても感ずることだが イタリアでは自分達の製品PRや 製品の高品質生産も大事であるが 素晴らしい環境を維持することも大事である
レンゾ―・ピアノが手掛けたフランスのポンピドゥーセンターは 多目的施設でありながら しかも文化の向上としての(付加価値)を生じている
1850年代から続いている(南イタリア)アマルフィ海岸に近い所の工場では 煙突柱をタイル張りにし 陶器のコマーシャルの役目も果たし 見せる工房を演出している
特に1980年以降は革新的建物が増え そこに組み立てラインを供するのではなく 製造過程の中で 質の高い働き方の演出を考慮している
外から見る外観ではなく そこに働く人達から感じられる景観を取り入れる生産現場が増えた
工場併設オフイスでは 今まで大きな違いがあったが オーナー(経営者)が設計に対する高品質な取り組みが 労働環境に一体感をもたらすようになり その町作りに溶け込む余裕さえ生まれた
農業景観の中の建築の視点で見ると ワイナリーとは云っても そこは単にワイン醸造所ではなく 見学する所であったり 途中試飲コーナーに出くわしたり 美しい景観を取り込むことによって 内・外でここに素敵なワイナリーがあるんだよ、と...
そこには日本の設計に対するノーハウも登場している
いずれにしても建築家とオーナー側とが一体になって 新しい生産方式も取り組む
更にトレビーゾのベネトーンでは 古い既存工場を再利用し そこで古い・新しい価値観を共有し 働きやすい労働環境を形成している
(オリベティの既存工場を ボーダフォンが買い上げ成功した事例も)
更にアブルッツオ(数年前、突如の大規模地震で町は壊滅状態?だった)の古い街を蘇らせて 緑を増やしホテル産業に特化して 消えかかる街を蘇らせる事業も行った(後半省略)
最後に名だたる大学教授や 設計専門の建築家や 他多数のリスナーによる質疑応答があり 終了後も熱心な出席者が列をなして講演者との懇談があり 日本の明日の建造物の再生を考える 非常に密度の濃い講演会となりました(終)
* 素晴らしい講演会を開催してくださいましたイタリア文化会館様に心よりお礼申し上げます
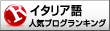 イタリア語 ブログランキングへ
イタリア語 ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村
2015年2月25日(水)夜 イタリア文化会館にて「工場から製造コミュニティー、メード・イン・イタリーの町へ(Dalla fabrica alla comunita' produttiva alla citta' del Made in Italy)」というテーマで 建築家ルーカ・セーヴィ氏の講演会が開催されました
氏が2012年ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展で行った展覧会「メード・イン・イタリーの建築」展で取り上げたテーマを掘り下げて論じました
メード・イン・イタリーの企業にとって 働く環境のクオリティは 洗練された生産システムとともに 優れたもの作りの重要な要素です
社屋や工場の建設は 進出する地域の再活性化に貢献します
こうした企業進出は その町の計画の有効活用において 歴史や文化を高める経済再生の鍵となることを示しています
* * *
講演会 講師:ルーカ・ゼーヴィ氏(建築家・都市計画家 歴史的地街区の再活性化や古い建物のリノベーションを専門とする)
日 時:2015年2月25日(水) 18:30~
会 場:IIC アニェッリホール
テーマ:工場から製造コミュニティー、メード・イン・イタリーの町へ
建築関係に詳しいゲストのM氏より 早速講演会のリポートが届けられました:
*講演概要(取材していた訳ではないので、全ての内容を把握していません)
2012年ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展の中で (当時)経済危機の中で 私達は建築家としてどのように貢献できるかを取り組んだ
1960~70年代では大きな(大規模)企業が成功し 80年代には中小企業 しかも大都市ではなく地方都市・中・小規模都市で台頭するようになり 「Made in Italy」としての伝統の力 職人の手になる成果を挙げてきた
しかも製品の品質向上を目指して来た
リーダー達が 工場建屋の中で 単に自社製品だけでなく 製品を作り上げる建屋の建設も又大事であると思うようになった
東京・表参道界隈の産業の製品への取組み姿勢・PRのあり方を見ても感ずることだが イタリアでは自分達の製品PRや 製品の高品質生産も大事であるが 素晴らしい環境を維持することも大事である
レンゾ―・ピアノが手掛けたフランスのポンピドゥーセンターは 多目的施設でありながら しかも文化の向上としての(付加価値)を生じている
1850年代から続いている(南イタリア)アマルフィ海岸に近い所の工場では 煙突柱をタイル張りにし 陶器のコマーシャルの役目も果たし 見せる工房を演出している
特に1980年以降は革新的建物が増え そこに組み立てラインを供するのではなく 製造過程の中で 質の高い働き方の演出を考慮している
外から見る外観ではなく そこに働く人達から感じられる景観を取り入れる生産現場が増えた
工場併設オフイスでは 今まで大きな違いがあったが オーナー(経営者)が設計に対する高品質な取り組みが 労働環境に一体感をもたらすようになり その町作りに溶け込む余裕さえ生まれた
農業景観の中の建築の視点で見ると ワイナリーとは云っても そこは単にワイン醸造所ではなく 見学する所であったり 途中試飲コーナーに出くわしたり 美しい景観を取り込むことによって 内・外でここに素敵なワイナリーがあるんだよ、と...
そこには日本の設計に対するノーハウも登場している
いずれにしても建築家とオーナー側とが一体になって 新しい生産方式も取り組む
更にトレビーゾのベネトーンでは 古い既存工場を再利用し そこで古い・新しい価値観を共有し 働きやすい労働環境を形成している
(オリベティの既存工場を ボーダフォンが買い上げ成功した事例も)
更にアブルッツオ(数年前、突如の大規模地震で町は壊滅状態?だった)の古い街を蘇らせて 緑を増やしホテル産業に特化して 消えかかる街を蘇らせる事業も行った(後半省略)
最後に名だたる大学教授や 設計専門の建築家や 他多数のリスナーによる質疑応答があり 終了後も熱心な出席者が列をなして講演者との懇談があり 日本の明日の建造物の再生を考える 非常に密度の濃い講演会となりました(終)
* 素晴らしい講演会を開催してくださいましたイタリア文化会館様に心よりお礼申し上げます




















