【上代・古代のあいさつ(2)】
≪鎌倉時代のあいさつ≫
鎌倉時代後期「問はず語り」のなかの記。
――いそぎ出で侍りしにも、「かならず近きほどに今一度よ」
とうけたまはりし御こゑ、あらざらん道のしるべにやとおぼゆ。(巻四)――
別れに際しての「さらば」というようなことばはまだなく、「またよ」
とか「今一度よ」などと、願望をそのまま言葉にしていたようである。
つまり平安時代には、まだ「あいさつ」をするという風習が無かった
のではないかと考えられる。
新年を祝うことば(「目出度き」など)
平安時代・・・「すばらしい」という意味
↓↓↓
南北朝時代後期・・・「祝う」意味へ
『庭訓往来』・・・南北朝時代後期または室町時代初期選集された
と言われる当時の書簡文の初歩的手習い書。
一年12ヵ月間の毎月の往信・返信と、8月の追加
一通の25通からなる手紙文で構成されたもの。
『庭訓往来』の正月状の前書き
往:「春の初めの御悦、貴方に向かって先ず祝ひ申し候ぬ。・・」
返:「改年の吉慶御意に任ぜられ候の条、先ず目出度く覚え候。・・」
時節の「あいさつ」文言があるのはこの2つだけらしい。
他の23通は単刀直入に用件から始まっているようである。
≪「おめでとう」の言葉ができたのは?≫
接辞語として「お」をつけることは一向宗がはじめたもの。
つまり、鎌倉・南北朝時代にもなく、一向宗が庶民に浸透して
いった室町時代後期にできたことばなのである。
浄土宗の僧・安楽庵策伝が室町時代の笑話を書き留めた
『醒睡笑』のなかにある話からもわかる。
――禅宗の旦那と、一向宗の旦那と寄り合い語りゐ、
「何といふことに、お御堂の、お寄り合いの、お讃談の、お勤めのと、
何にもおの字を付けてはいふぞや」と問ひければ、
「こちの宗旨ばかりおの字をいふでもあるまいぞ。そちの宗にも
おの字を付けていふは」と。
「なに物につけたぞ。」と。「おしやう様といふは、さて。」――
和尚の呼び方
天台宗・真言宗・・・「かしょう」
真宗(一向宗)・・・・「わじょう」
禅宗・・・・・・・・・・・・「おしょう」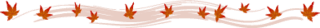
≪室町時代のあいさつ≫
室町時代初期の頃、狂言と言う芸能が現れる。
鎌倉時代の猿楽の能が、能と狂言に分立。
狂言・・・せりふとしぐさによる笑いの場面を主体としたもの。
能と能の間に演じられるようになった。
室町時代の物語集『御伽草子』には、それまでの貴族階級の
物語文学が僧侶・隠遁者・武家などによって、広い階層の読者を
予想して執筆したものらしく、素材・内容が多種多様である。
訪れを告げる時・・・「物言はん」「申さん」「物申さん」
別れを告げる時・・・「さらば」
話しかけの言葉・・・「しゝ申し」(しゝ=ちょっとの意)
現代のあいさつの原型・・・「ご無沙汰致して」「有難う御座る」
「目出度うおりやる」「唯今戻り申した」等
挨拶と同義語(漢語)・・・「時宜」「礼儀」「色代(しきだい・しきたい)」
この室町時代に、日本の伝統的なものの大半が造り出された。
生け花・茶の湯・連歌・水墨画・能・狂言・日本庭園(座敷、床の間)・
醤油・砂糖・饅頭・納豆・豆腐・・・・等々
この時代はあらゆる階層の人々、将軍・百姓でさえも旅をする時代で、
西国三十三箇所の巡礼や四国八十八箇所の遍路が始まったのもこの時代。
古くからの熊野詣や伊勢詣が庶民の間にも広がり、その費用
を捻出するために伊勢講や熊野講と呼ばれる頼母子(たのもし)講
なども考えだされたようです。
この時代の人たちは寄り合うことも好きで、いろいろな講が作り出され
楽しんでいたようです。
初心講・・・・・初心者が寄り合って連歌等習うカルチャー講
随意講・・・・・老若貴賤の隔てなく酒を酌み交わす無礼講
悋気(りんき)講・・・妻女たちの夫の浮気封じの為の情報を
交換する寄り合い
また夜遅くまで話しあうため、一日の長さが長くなり、二度で済んでた
食事が三度になったのもこの時代だそうです。
いろいろな階層の人々が集ってお喋りするにはやはり、
礼儀=挨拶がないと喋りにくかったのでしょうね。
特に政治を握っていた室町幕府においては礼儀作法の徹底をさせて、
荒々しい武家たちの猛気を抜こうと小笠原流の礼法を確立させ、武家
はこれを身につけることが第一条件と、地方へも普及させたようです。 『ごきげんよう 挨拶ことばの起源と変遷』 小林多計士著:参照
『ごきげんよう 挨拶ことばの起源と変遷』 小林多計士著:参照
~『仏教の話 ☆ 17 ≪挨拶≫』へ戻る~























