≪実在の名称と学問上の名称≫
☆「瓶(みか)」と「甕(かめ)」
「甕(かめ)」・・・日常の食物や飲み水を入れるもの
「瓶(みか)」・・・神に捧げるお酒や水を入れる神聖な容器
瓶は甕とも書き、(みか)とも(かめ)とも読めるとありましたが、
今の時代に生きる私たちにとっては、瓶=ビンの方が読み慣れて
いるのではないでしょうか。
なのでなんとなく小さいものとして感じとれるので形からして
大きいものを甕(かめ)と思い込んでしまっています。
考古学者が「甕(かめ)棺」と呼んできたものがある。
古代には権力者や高い階級の人を甕棺に入れて葬る風習が
あり、そのさい、日常生活の容器である甕(かめ)に入れたか、
神聖な神に捧げる「みか」に入れたかという謎が出てきた。
『倭人伝を徹底して読む』の著者である古田氏は神聖な方
「みか」ではないかと思うようになってきたという。
しかし、考古学者は形態からみて「甕(かめ)棺」と名付けてしまった。
基本的には共通しているから即物的に「仮に呼んだ名前」を
つけたわけだが、「歴史上の名前は別個ですよ」「考古学者の
任務外ですよ」と考古学者は言うべきだし、また一般の読者も
そのことを頭に置いて、読むべきだといっている。
そういう分類上の「仮説・名称」という概念を忘れ、「実態」だと
錯覚していることに問題があるという。
結果、ヒミコではなくて「ヒミカ」である、
「太陽のミカ」ではないかという問題にもいきついたという。
「名称批判」があり気づかれたようです。
☆「剣」と「刀」
埼玉県の稲荷山鉄剣は、普通鉄剣と呼ばれているが、
実際の銘文では「刀」と書かれている。
有名な七支刀も剣なので、本来なら七支剣と呼ばれるべき
なのに「七支刀」と書かれている。
剣・・・両刃
刀・・・片刃
しかし、実用上決して間違って使っていたわけではなく、実際に
六世紀の関東の人々は“稲荷山の両刃の利器”を刀と呼んでいた。
七支刀は、それを作った百済でも刀と呼んでいたのである。
四世紀の百済と六世紀の日本列島の関東とが共通して刀と
呼んでいるところからみると、歴史的に実在した名称であった
と考えるのが、筋だと著者は言っています。
『あの国宝・七支刀は「鋳造」 復元した刀匠、鍛造説覆す分析』
(1/2ページ) 産経ニュース
 『倭人伝を徹底して読む』 古田武彦:著
『倭人伝を徹底して読む』 古田武彦:著 
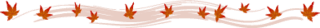
確かに、私たちは習ったことが正しいと思っていたら、
歴史が変わっていたとか、誰でも知ってる有名な写真が違う人
だったなんて話、最近よく聞きます。
つい先日も銅像が弟と間違えられていたなんて話も新聞にあったような・・
子供のころ、私たちは間違ったことを教えられていたのか~、
なあんてショックにも思いますが、その当時では最新のもの
だったのでしょう。新しい発掘や文献によって、歴史は変わる
ものとは、今じゃあ、皆が承知のことでしょう。
TVでも面白おかしく、かなり教えてくれてますからね。
学校に行っていない大人たちもお勉強できて有難く、便利な
世の中になったものです。
古文書があったら事実と思うことも最近では疑ってみたりもする
ことがあります。人に見られるものには嘘とは言わないまでも、
善い風に見られるように書かれている場合があるでしょうね。
また、書く人だけの思い込みってのもあるかも。
ま、そんなものは一般人が見る前に整理されているとは思います。
日記など、本当に大事なことを赤裸々に書いてあるのはやはり、
家に残ってるものが多いのでしょう。
家族や親類、誰もいなくなって初めて手放され、人目に触れ、
真実がわかるものなのでしょう。
他人に知られたくないものは、隠す。
ことも・・・
今、古文書が密かにブームになりつつあるそうです。
特に江戸時代は文字が多使用されていたので、
気をつけなければならない「仮説・名称」だらけです。
・・・ていうか~、単純な書き間違いもありま~す。
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
【瓶原(みかのはら)】
京都府の南端に位置する木津川市に、瓶原村があった。
現在は俗称になっている。
瓶原公民館がある正式名称は、加茂岡崎。
現在では「みか」とはいわず、
「瓶」=「甕」=「かめ」と読むことが多い。
古代人は、美しく流れる川を「御河(みか)」と呼んだ。
その川沿いにひらけた原野に、「御河之原(みかのはら)」と地名をつけた。
川の流れ込む形が甕(カメ)に似ていたからという説もある。
瓶原は、東西に流れる木津川沿いにひらけた土地で、
古代には、草花が咲き誇る風景が開けていたであろう。
そのあたりで伊賀街道と信楽街道が分岐していた。
聖武天皇がそこに恭仁京(くにきょう)をおいて生活していた
時期がある。(740~744年)
「三日原(みかのはら)、布当(ふと)の野辺を清(すが)みこそ、
大宮処(おおみやどころ)定めけらしも」―― 『万葉集』
恭仁京の穏やかな風景は天皇の心をなごませていたらしい。
布当とは瓶原の近くを流れる布当(ふたぎ)川にちなむ。
しかし、恭仁京は交通に不便だったこともあり、
国政の地に相応しい平城京に戻って行った。
≪実在の名称と学問上の名称≫
「みか」と「かめ」についての私のブログ参照→ こちら
 『意外な歴史が秘められた 関西の地名100』 竹光誠:著
『意外な歴史が秘められた 関西の地名100』 竹光誠:著 






















