「人に逢いに行く!」って事の方が優先になってるかな。
そのうちの一人、Tさん(としておこう)とは
ずーっと昔からの知り合いのようでもあり、親友のようでもあり、
悩みや身体の欠点でさえも、本当に何でも話せる人なのだ。
不思議なことに、話せるだけで心がスーとするっていうのは
Tさんだ けかもしれないなあ・・・
遠くに離れてるから返って何でも話せるのかもしれない。
人を裏切らない人、というより裏切れない人なのだと思う。
まるで、恋人?親?のような感じがする人でもある。
特に、家族のことを話しているときは羨ましいぐらいだ。
Tさんといると、いつも家族を大事にしてるなあ。。。と、心が和む。
一生涯を通じての“心の友”とこっちが勝手に思ってるだけかも
知れないけれど、そういう人がいるっていうことは幸せなことかもね。
「苦労を知ってるから今があるんだと思う。。。」
Tさんの言葉にはしっとりとした優しい重みがある。
一番大好きな、大事にしたい、私の尽生優人の一人です。
↓れんこんサブレー

ピーナッツ味噌 ピーナッツ煮豆
ピーナッツの煮豆って噂では聞いていたが、今回偶然見つけた。
お店に入ると「生はまだ置いてないんですよ」
と店主さんが言われたが、大阪では生ピーナッツなど売ってない。
ここら辺のお客さんにみな聞かれるぐらい普通なんだろうね。

ピーナッツ煮豆 ピーナッツ味噌
それにしても、柔らかくて美味しかった~!
柔らかいピーナッツは初めて食べたけど、やみつきになりそう~♪

蓮根粉末を使ったものだそうです。
れんこんの味がもっときついかなと思ったけど、
そうでもなかった。というより、サブレーの味だあ~♪
美味しかったで~す。
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
(ただし医療費の助成のある特定疾患治療研究事業対象の疾患ではない)
(ウィキペディア:参照)
へぇ~、治療費はタダにするほどの病気ではないけど難病なのね。
***************************************************
―――昨日の話。 (ダーリンであるマーちゃんの話)
「突発性難聴みたいやねん。」
私が帰るなりマーちゃんが言った。
叔父さんの仕事の手伝い中、本当に突然だったらしい。
行きつけの小さな病院では、無理があるので紹介状をもらったとのことだった。
意気消沈して、明日行ってくるわ、って言ってたのに今日朝起きると、
「治ったみたい!やっぱりやめとくわ。治ったのに行ってもしゃーないし。」
なあんて子供みたいなことをいう。
こういう症状事体が、最初の自身のからだからの警告だというのに・・・
「知らんで~!次に聞こえへんようになったら手遅れになってた、
なんてよくある話やで~。。。ま、私の身体違うからいいけど。」
といつもの私流の脅し文句をすぐに言っておいたせいか、
昼頃、今日金曜だし日・月と連休だから、今日中に行った方が
いいんじゃあないの、と念押ししたら「火曜日に行く!」だって。
今日は用事で義姉に会うことがあったので相談したら、
叔父に聞いて知ったらしく、入院中の母に心配させまいと内緒
にしておいて、と言ってたことを聞いた。
「ほんならうちから電話かメールしとくわ。お母ちゃんに言うでー!
って脅しといたるわ~。なあんてうちら、子供みたいやん!」
なあんて笑ってた姉の忠告が聞いたかな・・・?
男ってそういうところあるなあ、結局、母には弱しか。。。
なあんて思いながら、自分も母であることを感じるのでした。
今日は、相談できる家族がいることを有難く思う日でした。
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
「脊髄損傷すると一生歩くことは難しい!」
日本ではそれが常識とされてきたこと。
そんな言葉を覆えそうとしている人がいる。
脊髄損傷のトレーナー 渡辺淳さん 29歳
「無理と思っていることは絶対無理だから、できないと思って諦めてははいけない」
「1人歩いたら奇跡って言われても、自分がもし100人歩かせたらそれは絶対奇跡とは言わせない」
≪11年前アメリカで確立されたトレーニング方法≫
カリフォルニア州・サンディエゴ
世界初の脊髄損傷者専門トレーニングジムである
「プロジェクトウォーク社」
設立から11年約200人を歩けるようにしてきたと言う。
そのノウハウを日本に初めて持ち込んだのが渡辺さん。
脊髄損傷者専門のトレーニング施設を3年前(2007年)に設立。
ジェイ・ワークアウト株式会社 http://j-workout.com/
脊髄損傷・・・背骨の中を通っている中枢神経が事故などで傷つき
腕や足が麻痺してしまうこと。
現在日本に10万人以上もいるといわれている。
一度傷ついた損傷は再生することは無いので、歩くことは難しいと考えられていた。
しかし、渡辺さんのジムで回復した人がいる。
9歳で脊髄の腫瘍を患い、以来車椅子生活を続けてきた2008年北京
パラリンピックのテニスで金メダルを取った国枝慎吾さんは、17年間
歩くことを諦めていたといいます。
ところが、渡辺さんのジムに通い始めると、杖で歩けるまでに回復したという。
また、3年前ラグビーの試合中に脊髄損傷して、首から下が麻痺して
歩くことは難しいと言われた人もトレーニングから2年後の現在走るまでに回復した。
≪どのようなトレーニングか?≫
中吊りにするマシーンで身体を立った状態にし、トレーナーが足を
動かせながら歩く動作を反復させる。歩くたびに足をどう動くか意識
させるため、何百回、何千回も繰り返しながらトレーナーは声を掛け続ける。
脳からの指令は背骨の中の脊髄を通り、足を動かす。
この脊髄が損傷すると、脳の指令を伝えるルートが途絶え、
そこから先が麻痺状態になる。
一度切れた神経は二度と繋がらない。
ところが、少しでも神経線維が残っていると、残った神経に
歩行状態を教え込むことで歩ける可能性がある。
残っている所に歩行機能をもう一度再教育するというやり方。
しかし、そのやり方は何千回何万回と同じ動作を繰り返すこと。
かなり根気のいることだと思います。
「神様だ!」とある患者さんが感動して言ってました。
その練習中に自分が動かせたという感覚があったのでしょう。
車椅子生活が続くと筋肉は使われなくなりやせ衰えていきます。
しかし、使わなくなった筋肉をトレーニングすることで筋肉を鍛えておくのです。
いざ動かす時に耐えられるようにするといいます。
現状では常識を覆すものだと医師は言っていました。
本人の意志でなくても人に動かされていても、それにつられて筋肉
は動いているので、無理なことが出てきたら、それがなぜ動かせ
ないかを考えるそうです。そして、その人への運動メニューを増やす。
ある人は300ものメニューとかいってましたね。
もの凄い運動量だそうです。
「うちらにできるのは25%ぐらいしかない。ほとんどは自分たちがやることなんです。」

子供の頃スポーツ万能といわれた渡辺さんは、10代でかかった病(脊柱管狭窄症)のため自分が身をもって歩けなかった経験(2年)があったそうです。
病を克服した後、新しいことに挑戦するため2000年アメリカへ留学。
そこで運命的な出会いの世界初の脊髄損傷者専門トレーニングジムを知るのです。
そして、2005年、そのプロジェクトウォーク社へ入社。
そこでの様子に衝撃を受けて、歩けない人を歩けるようにしたいと
難関のトレーナー資格を取るために勉強して、2006年最高クラスの
トレーナー「スペシャリスト」の資格を取得。
米国人以外では初めてだそうです。
「多分日本だったら見捨てられていたような重度の人たちが
凄い結果を出してるので、やりたいなと思ったんですよね。」

そして、リハビリとその後の回復度に合った仕事の紹介、
支援など、彼らが生きがいを見つける手助けもしたいと、
就労支援センターを今年立ち上げたようです。
ジムとの連携をしたい。きめ細やかに仕事を探す。
またしたい仕事にあわせて回復させる機能をリハビリする。
など、これからの自分の人生を諦めていた人に、
希望を持たせたいと考えているそうです。
「奇跡はちゃんとした法則の中でしか起こらない」
という言葉が好きという渡辺さんのマイゴール。
≪2015年までに100人の脊髄損傷者の人を歩かせたい≫
来年春に、この大阪に新しいジムができるそうです。

私たち素人からすれば、吃驚ですね。
お医者さんに歩くことが無理と言われたら、奇跡でも起きない限り
無理だと思うのが普通ですよね。
リハビリも自分で出来た人は奇跡の復活と言われるけど、
何万回も他人の手で動かしても回復可能になるとは。。。
最初、それをしようとした人って凄い!
日本でもやってみようとする渡辺さんも凄い!!
歩けないと言われた人たちにとって救いの神ですね。
ご訪問の記念に、1クリック募金のご協力を!
↓↓↓

いつもありがとうございます!
【上代・古代のあいさつ(2)】
≪鎌倉時代のあいさつ≫
鎌倉時代後期「問はず語り」のなかの記。
――いそぎ出で侍りしにも、「かならず近きほどに今一度よ」
とうけたまはりし御こゑ、あらざらん道のしるべにやとおぼゆ。(巻四)――
別れに際しての「さらば」というようなことばはまだなく、「またよ」
とか「今一度よ」などと、願望をそのまま言葉にしていたようである。
つまり平安時代には、まだ「あいさつ」をするという風習が無かった
のではないかと考えられる。
新年を祝うことば(「目出度き」など)
平安時代・・・「すばらしい」という意味
↓↓↓
南北朝時代後期・・・「祝う」意味へ
『庭訓往来』・・・南北朝時代後期または室町時代初期選集された
と言われる当時の書簡文の初歩的手習い書。
一年12ヵ月間の毎月の往信・返信と、8月の追加
一通の25通からなる手紙文で構成されたもの。
『庭訓往来』の正月状の前書き
往:「春の初めの御悦、貴方に向かって先ず祝ひ申し候ぬ。・・」
返:「改年の吉慶御意に任ぜられ候の条、先ず目出度く覚え候。・・」
時節の「あいさつ」文言があるのはこの2つだけらしい。
他の23通は単刀直入に用件から始まっているようである。
≪「おめでとう」の言葉ができたのは?≫
接辞語として「お」をつけることは一向宗がはじめたもの。
つまり、鎌倉・南北朝時代にもなく、一向宗が庶民に浸透して
いった室町時代後期にできたことばなのである。
浄土宗の僧・安楽庵策伝が室町時代の笑話を書き留めた
『醒睡笑』のなかにある話からもわかる。
――禅宗の旦那と、一向宗の旦那と寄り合い語りゐ、
「何といふことに、お御堂の、お寄り合いの、お讃談の、お勤めのと、
何にもおの字を付けてはいふぞや」と問ひければ、
「こちの宗旨ばかりおの字をいふでもあるまいぞ。そちの宗にも
おの字を付けていふは」と。
「なに物につけたぞ。」と。「おしやう様といふは、さて。」――
和尚の呼び方
天台宗・真言宗・・・「かしょう」
真宗(一向宗)・・・・「わじょう」
禅宗・・・・・・・・・・・・「おしょう」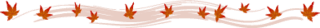
≪室町時代のあいさつ≫
室町時代初期の頃、狂言と言う芸能が現れる。
鎌倉時代の猿楽の能が、能と狂言に分立。
狂言・・・せりふとしぐさによる笑いの場面を主体としたもの。
能と能の間に演じられるようになった。
室町時代の物語集『御伽草子』には、それまでの貴族階級の
物語文学が僧侶・隠遁者・武家などによって、広い階層の読者を
予想して執筆したものらしく、素材・内容が多種多様である。
訪れを告げる時・・・「物言はん」「申さん」「物申さん」
別れを告げる時・・・「さらば」
話しかけの言葉・・・「しゝ申し」(しゝ=ちょっとの意)
現代のあいさつの原型・・・「ご無沙汰致して」「有難う御座る」
「目出度うおりやる」「唯今戻り申した」等
挨拶と同義語(漢語)・・・「時宜」「礼儀」「色代(しきだい・しきたい)」
この室町時代に、日本の伝統的なものの大半が造り出された。
生け花・茶の湯・連歌・水墨画・能・狂言・日本庭園(座敷、床の間)・
醤油・砂糖・饅頭・納豆・豆腐・・・・等々
この時代はあらゆる階層の人々、将軍・百姓でさえも旅をする時代で、
西国三十三箇所の巡礼や四国八十八箇所の遍路が始まったのもこの時代。
古くからの熊野詣や伊勢詣が庶民の間にも広がり、その費用
を捻出するために伊勢講や熊野講と呼ばれる頼母子(たのもし)講
なども考えだされたようです。
この時代の人たちは寄り合うことも好きで、いろいろな講が作り出され
楽しんでいたようです。
初心講・・・・・初心者が寄り合って連歌等習うカルチャー講
随意講・・・・・老若貴賤の隔てなく酒を酌み交わす無礼講
悋気(りんき)講・・・妻女たちの夫の浮気封じの為の情報を
交換する寄り合い
また夜遅くまで話しあうため、一日の長さが長くなり、二度で済んでた
食事が三度になったのもこの時代だそうです。
いろいろな階層の人々が集ってお喋りするにはやはり、
礼儀=挨拶がないと喋りにくかったのでしょうね。
特に政治を握っていた室町幕府においては礼儀作法の徹底をさせて、
荒々しい武家たちの猛気を抜こうと小笠原流の礼法を確立させ、武家
はこれを身につけることが第一条件と、地方へも普及させたようです。 『ごきげんよう 挨拶ことばの起源と変遷』 小林多計士著:参照
『ごきげんよう 挨拶ことばの起源と変遷』 小林多計士著:参照
~『仏教の話 ☆ 17 ≪挨拶≫』へ戻る~






















